俳句をはじめると、俳句では切れが大切で、「や」「かな」「けり」の主な切字を使ったり、名詞で止めて切れを生むのだと学ぶ。
だが、切れを生むのはそれらの言葉だけではない。句会に参加し始めて、「この句は『て』で軽い切れを生んでいますね」という、発言を耳にしたことがあった。「て」も切れになる、というのは軽い驚きがあった。この本ではそういった、助詞の切れの効果についても説明をしている。
「て」の効果については、この本の中の「便利な『て』の注意事項」という項目で解説されている。見出しを挙げていくと、なんとなくの「て」の効果が分かるのではないかと思い、ここに挙げさせていただく。
「散文化しやすい『て』」「単純な接続」「逆説の『て』」「原因・理由の『て』」「『て』止め」
「て」にはたくさんの役割がある。そして、文脈によって役割が違ってくるのだ。
井上氏は冒頭で、この本の大元となっている『俳壇』の「俳句文法」のエッセンスを説いた連載に反響があったことを、「(前略)単純な公式に終わらず、原則を使って自分で考える必要があります。そこを説いたところが、好評の理由でした」と書いている。俳句のステップアップには、ルールや公式を知った上で「自分で考える」に移行できることが大切なのだと考えさせられる。「自分で考える」ということは、難しいことでもある。そんな風に迷った時、指標となるのがまさにこの本なのである。そしてその自由さを楽しめるようになることは、俳句が上達したということなのではないだろうか。
私が句を作っていて「自分で考える」のが難しいものの一つに「字余り」がある。その字余りについても記述がある「よい字余り、悪い字余り」の項目だ。見出しからして、まさに私が知りたかったことである。句会で「中八は避けたいよね」とか「これは字余りだけど気にならないね」という評が出てくることがある。評を聞くと「なるほど」と思うのだが、いざ自分で作ってみると「この字余りは効果的なんだろうか、避けた方がいいものなんだろうか」と判断が出来なく、結局「字余りは止めておこう」と無難な定型を選ぶことがある。この章では字余りについて、調べ等の観点からとても理論的に解説がされている。
何個か書かれているテーマを取り上げてさせていただきながら文章を書いてみたが、結局直接本を手にとって目次を開くことが一番この本の魅力が伝わるかもしれない。きっとあなたがモヤモヤと悩んでいたこと、知りたかったことの答えが見出しとして書かれていることと思う。
書かれているのは、技術的なことだけではない。終盤の「『かたち』が『こころ』を集わせる」の辺りに書かれる「俳句のマナーとは、ルールとは」についての文章も俳句を作る心構えとしてとても勉強になる。
俳句の楽しみとは何か。作句はもちろんだが、句会という場所にもあると思う。句会の楽しみ方はたくさんあるのだが、その中の一つとして、句会でみんなで言葉を追求していく瞬間が好きだ。助詞を変えたり、語順を変えたりしながら、作者の言葉が一番輝く配置が見つかった時はこちらまで嬉しくなってしまう。
この本を読むことで自身の俳句のレベルアップはもちろんだが、鑑賞でも一目置かれる視点を獲得できることだろう。そうしてそのことは、句会全体のレベルアップへと繋がるだろう。
(諸星千綾)
【執筆者プロフィール】
諸星千綾(もろほし ちあや)
1982年生まれ。
「すはえ」「猫街」「よんもじ」「子連れ句会」に参加して句作中。
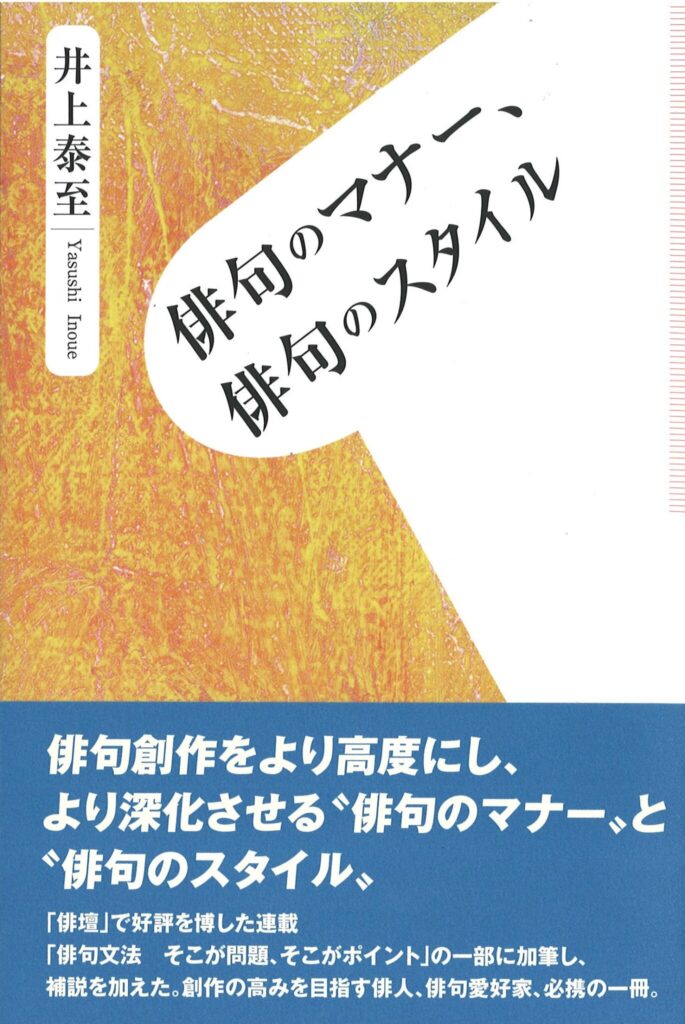
俳句創作のより高みを目指すために必要な「マナー」と「スタイル」とは? 「俳壇」好評連載の単行本化。