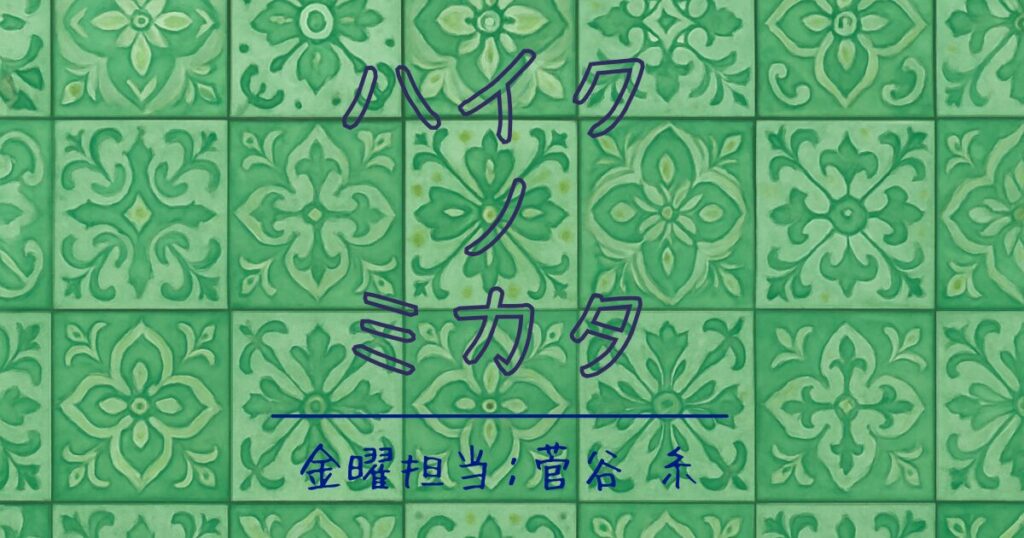
焼米を家苞にして膝栗毛
松藤素子
「焼米」という季題は、籾つきの新米を炒り、臼で搗いて籾殻を取り除いたものです。
香ばしく、甘さもあって滋養に富む食べ物で、かつては旅人が懐に入れて携える、心強い保存食でもありました。
句会の兼題で「焼米」が出た時、私は焼米を買って食べてみたことがあります。じんわりとした優しい甘さがあり、それを思い出しながら掲句を読むと、温かさが漂うのを感じます。
なぜでしょう。
徒歩の旅を意味する「膝栗毛」という言葉に導かれて、長い道のりを歩む旅人の姿が自然に浮かんできます。
旅の疲れや、家族を思う心が、焼米の甘さとともに胸に広がっていく。
そのぬくもりに、温かさが漂うのではないでしょうか。
「家苞」という言葉の響きもまた、単なる土産以上の意味を運んでいます。
家へ持ち帰るのは、食べ物そのものだけでなく、道中の記憶や、旅人が家族に向けた眼差しのぬくもりです。
その素朴さは、読み手の心に安心感を与えてくれます。
「ひねらない」俳句とは、工夫を放棄することではないと思います。
この素朴な一句の背後には、旅を支える労苦、家族への思いやり、そして生活の匂いが自然に息づいています。
言葉をひねらずに差し出すことは、実感にそっと触れることなのかもしれません。
(菅谷糸)
【執筆者プロフィール】
菅谷 糸(すがや・いと)
1977年生まれ。東京都在住。「ホトトギス」所属。日本伝統俳句協会会員。

【菅谷糸のバックナンバー】
>>〔1〕ありのみの一糸まとはぬ甘さかな 松村史基
>>〔2〕目の合へば笑み返しけり秋の蛇 笹尾清一路
>>〔3〕月天心夜空を軽くしてをりぬ 涌羅由美
>>〔4〕ひさびさの雨に上向き草の花 荒井桂子
>>〔5〕破蓮泥の匂ひの生き生きと 奥村里
>>〔6〕皆出かけスポーツの日の大あくび 葛原由起
>>〔7〕語らざる墓標語らひ合う小鳥 酒井湧水