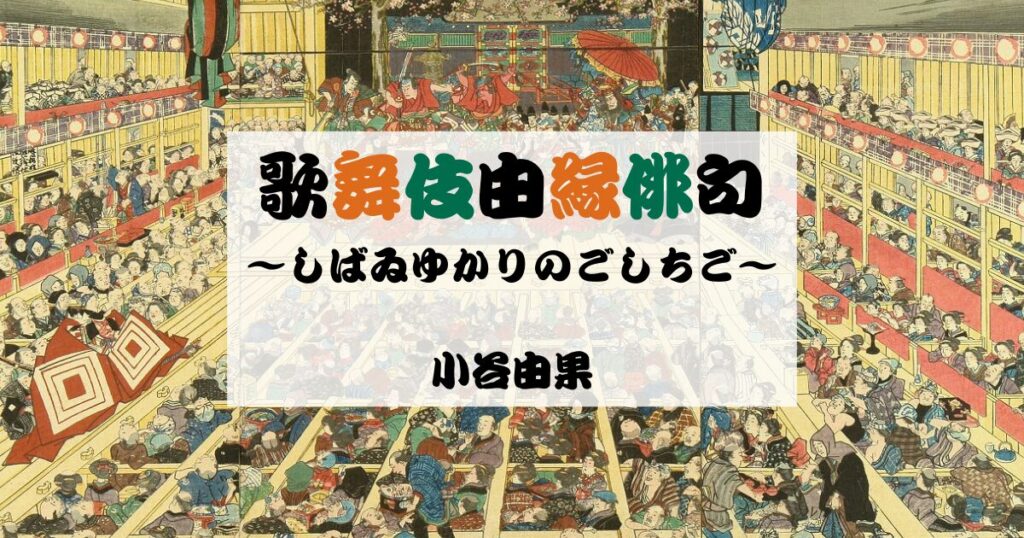
【第11回】
『蝶の道行』作者の並木五瓶の俳句

七月の歌舞伎座は、夜の部最終幕に『蝶の道行』という舞踊劇がかかった。人気の若手歌舞伎役者「染團」の市川染五郎と市川團子、二人の3年ぶりの共演とあって、連日幕見は完売。仕事帰りに行きやすい夜8時開演の幕ということもあり大人気であった。
『蝶の道行』は、恋が報われず世を去った助国(染五郎)と小槇(團子)が蝶の姿となって花咲く野辺で舞い踊る、儚く美しい舞踊劇。
この『蝶の道行』の作者は、狂言作者の初代並木五瓶(1747年〜1808年)である。
『蝶の道行』とは
『蝶の道行』は、天明4年(1784年)閏正月に初演。大坂嵐他人座へ並木五瓶が書き下ろした歌舞伎「けいせい倭荘子」のうち五段目にある道行で、名題を「道行二世の縁花の台」として上演された。初演は宮薗節で、のちに義太夫節に改曲、文政元年(1818年)に人形浄瑠璃にて初演。明治4年以降途絶えていたが、昭和11年(1936年)に復曲。歌舞伎では昭和31年(1956年)7月の歌舞伎座で『花台蝶道行』として取り上げられ、昭和37年(1962年)6月の歌舞伎座では“天明歌舞伎百八拾年振り復活”と銘打ち、武智鉄二の新演出で「けいせい倭荘子」の通しの中で『蝶の道行』として上演された。以後幾度もかかっている人気演目である。今回の『蝶の道行』は、主流となっている武智鉄二演出・川口秀子振付のものではなく、二世藤間勘祖振付のものである。
並木五瓶とは
初代並木五瓶は、延享4年(1747年)に上方の大坂に生まれ、並木正三に入門。道頓堀の浜芝居、大坂角の芝居、京都早雲座にて名作を続出させて京阪での地位を確立。三代目澤村宗十郎の招聘で江戸へ下り、浅草雷門に居を構え「浅草堂」「並木舎」と号し、江戸都座や市村座の狂言作者として活躍した。
代表作の一つは『楼門五三桐』で、安永7年(1778年)4月大坂角の芝居で初演。「南禅寺山門の場」での石川五右衛門の名科白「絶景かな、絶景かな」はあまりに有名である。
初代桜田治助とともに“江戸の二大作者”と謳われ、上方の写実合理性を江戸歌舞伎に融和させた点が高く評価されている。
江戸へ下った五瓶は、江戸座の俳諧も嗜み、『誹諧通言』という著書や自身の句も残している。
1 / 2