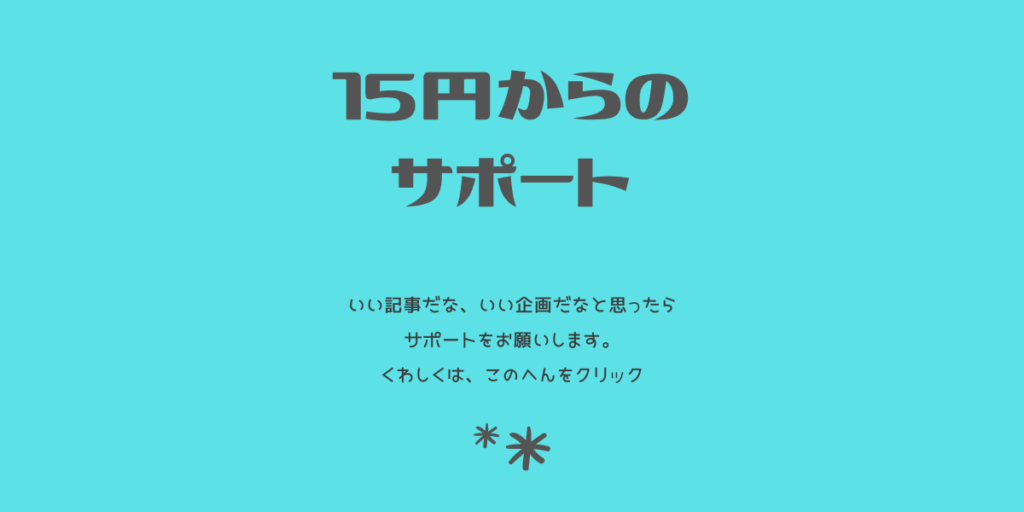あかさたなはまやらわをん梅ひらく
西原天気
梅の観覧がはじまったと聞くやいなや、わーい!と速攻で見にいく。そうすると、まあ見事に咲いていないものです、梅というのは。
京都に住んでいた学生時代も、梅園観覧の開始と同時に北野天満宮に出かけ、「うーん、ほとんど咲いてないじゃん。てか、どこもかしこも枝がすっかすかで寒いんですけど道真さん…」ってことがたびたびありました。かじかむ手をこすりながら梅園の茶屋で緋毛氈に腰掛け、菓子と茶を喫して、やっと生きた心地がするというありさまで。
「雀の涙ほどしか咲いてないのに、どうして『もう見頃ですよ』なんていうんだろう?」と思っていた当時のわたしは、「探梅」という言葉の意味を知らなかったのです。だから梅の花をわざわざ探し出してはしみじみする、という人生の心得もなかった。言葉を知らないと文化も歴史もさっぱり見えてこない。これ、かんがえてみると恐ろしいことですよね。探梅にかぎらず、言葉を知るというのが、他者の来し方や感じ方をどれだけ理解する助けになるかって話ですから。
あかさたなはまやらわをん梅ひらく 西原天気
なんと知的かつ愛らしい発想でもって、時間の推移そのものを写生した〈あかさたなはまやらわをん〉でしょうか。この〈あかさたなはまやらわをん〉からは、12個の音符をぴょんぴょんと渡ってゆくような、たいそう軽やかな音楽が聞こえます。また渡るといったイメージが時間の進行と重なり、下五の〈梅ひらく〉では小さな大団円の感触も生まれているようです。
さらに〈あかさたなはまやらわをん〉には、アブラカダブラ的パワーワードとしての力も具わっていて、この呪文を唱えた結果として梅がひらいたかのような、そんな仕掛けにもなっています。
もうひとつ面白いのは、五十音表のかたちや言葉のイメージを巧みにあやつることで、作者がこの句をモビールみたいにゆらゆらさせたこと。すなわち〈あかさたなはまらや〉までは明るいア行をぴょんぴょんと水平に渡り飛び、その先の〈わおん〉で一瞬大きく沈み、ふたたび〈ひらく〉という言葉のイメージによって明るく浮き上がるといった次第。うーん。時間だけでなく運動まで写生してしまうとは。花がほころぶところを描くのですから、動きがあったほうがより自然なわけです。 音楽、時間、魔法、運動。そんな四つの性質でもって語られた春。梅が咲くのって、こんなにうれしいことだったんですね。
(小津夜景)
【執筆者プロフィール】
小津夜景(おづ・やけい)
1973年生まれ。俳人。著書に句集『フラワーズ・カンフー』(ふらんす堂、2016年)、翻訳と随筆『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』(東京四季出版、2018年)、近刊に『漢詩の手帖 いつかたこぶねになる日』(素粒社、2020年)。ブログ「小津夜景日記」
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】