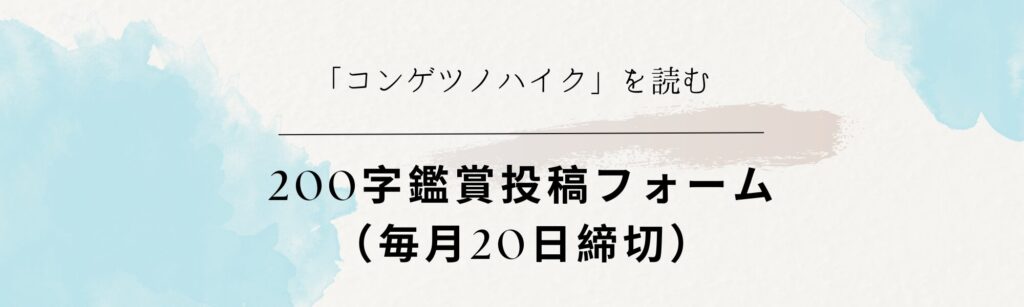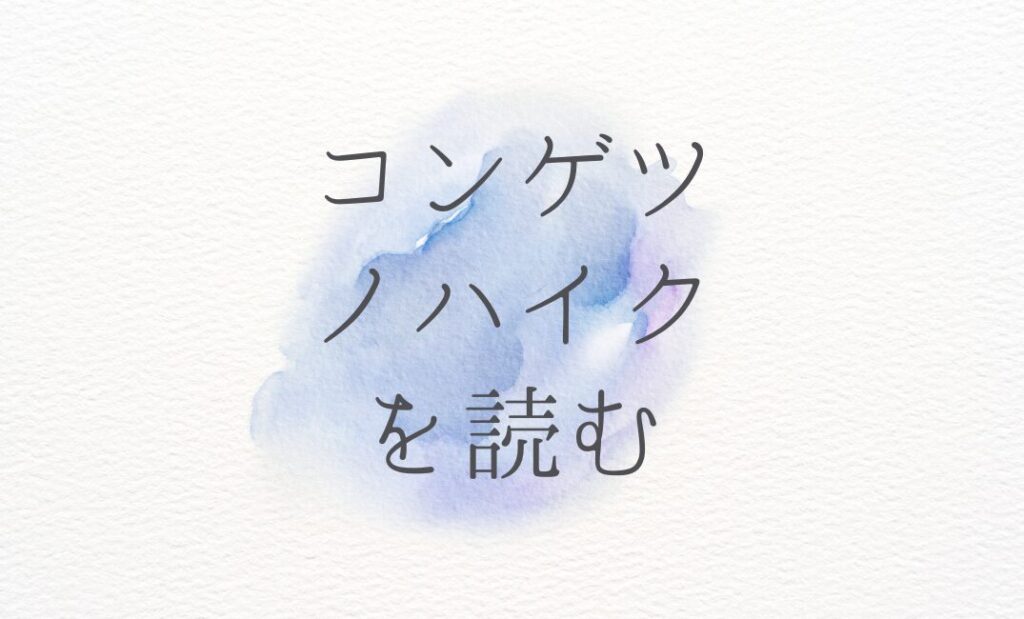
【読者参加型】
コンゲツノハイクを読む
【2025年7月分】
「コンゲツノハイク」から推しの1句を選んで200字評を投稿できる読者参加型コーナーです。今月は9名の皆様にご参加いただきました。ありがとうございます!
飴玉のいま溶け終はる桜かな
市原みお
「南風」
2025年7月号より
飴玉の最後の瞬間を舌で感じたことがある人はどれくらいいるだろうか。たいていは八割くらいまで来たら噛んでしまうものだ。このたっぷりとした時間軸にのんどりとした主体の心持ちがまず届いてきた。
口の中の飴玉がふっとなくなる。まさにそのとき、目の前の桜に気づく。
「いま溶け終はる」飴玉という小さな出来事と「桜」という大きな自然の流れが時間の一点で交わる瞬間。
個人的な時間が自然の大きな時間に重なっていく構造、そして、いつかは消えてなくなるという移ろいの甘やかさ・美しさという共通の感覚のなかで細やかな余情を届けてくれる佳句。
(押見げばげば)
閉業の学士会館サクラサク
鮫島沙女
「炎環」
2025年6月号より
学士会館は、旧帝国大学出身者からなる学士会会員の親睦と知識交流を目的とした倶楽部建築として、1928(昭和3)年に誕生。関東大震災後に建設された震災復興建築の代表作で、歴史ある建物。再開発のため、一部解体されるが、旧館はそのままの姿で移動させる曳家(ひきや)工事で保存する計画。後世に残される喜びも、サクラサクに感じる。
(野島正則/「青垣」「平」「noi」)
日が暮れて急に淋しく春浅し
野末トヨ
「ホトトギス」
2025年7月号より
たとえば投句一覧の中にこの句があったなら、わたしはこの句を採ることができるだろうか。まったく自信がない。正直にいえば、コンゲツノハイクの「ホトトギス」推薦の一句ゆえにこの句が急に光ってみえたのだ。難しい言葉はなにひとつ使われず、作者の感じたそのままを句にしている。季語「春浅し」にも一切作為が感じられない。それでいてこの句は、尋常じゃない素直さゆえに、読者のこころに驚きをもたらし、まっすぐに届いてゆく。俳句ってしみじみおもしろいものだと思う。
(千野千佳/「蒼海」)
都電より面影橋の桜かな
石川小鳥
「銀化」
2025年7月号より
都電、面影橋、桜。素材の味を活かしたシンプルなレシピ。桜のころ橋の上は花見客でいっぱいになるが、普段は静かな場所だ。ちょうど面影橋を過ぎたあたりで都電は新目白通りから明治通りに右折して神田川を離れ、車窓から桜は消える。学習院下への坂道を上る。音や匂いや当時の気分がこみあげてくるのは、私が面影橋のたもとに住んでいたせいだろう。十七音の言葉とリズムに共鳴して五感の記憶がざわめき、繋がり合い、今新たな質感を読者の体内に創り出す。俳句という装置の威力。
(小松敦/「海原」)
大根を入れる余地あり旅鞄
こしのゆみこ
「海原」
2025年6月号より
下五の着地が「旅鞄」。その意外性に驚き、とたんに想像が広がりました。
まず必要な物を入れた「旅鞄」。そこにまだ何かを入れる「余地」があることを知った作者は、そこに「大根」を入れようと決心します。旅前でしたら、旅先の誰かに食べてもらいたいと思う自分で収穫した「大根」でしょうし、帰路前でしたら、旅で手に入れた何方かによる丹精なる「大根」でありましょう。いずれにせよ、「大根」の存在感が際立つとともに、人と人との心の交流も大いに感じられる佳句であります。
(卯月紫乃/「南風」)
いつとうの黄蝶この世をはぐらかし
百瀬一兎
「炎環」
2025年6月号より
春を待ち望む人々にとって遅く浅い春に現れる蝶の一頭、残る寒さのなか、それは騙しのようでいて春のおとずれを告げる。加えて黄蝶ならその小ささから生まれたての春のように。普通ならそう読むのかも。
でも黄蝶なのだ。そんなやわなはずない。成虫、蝶のまま越冬もする。この老蝶は秋から冬を越しようやっとよろよろと出たと思ったらすぐ、まだ寒いなか見た人の感覚・意識を手玉にとりくるっとまるめて手品のようにはぐらかし・・・と思いつい大笑いしてしまったのはきっと黄蝶を飼ったことのある私だけです。
(haruwo/「麒麟」)
巣箱懸け覗かぬ日々を夢といふ
鈴木牛後
「雪華」
2025年7月号より
上五の「懸け」から、これからこの巣箱を使う鳥たちに思いを寄せ、心をこめて巣箱をかける作者の姿が浮かぶ。作者は巣箱を懸けたあと、その中を覗かない。親鳥の産んだ卵が孵化して雛となり成長し、巣立ちを経て巣箱が空になるまで。「覗かぬ日々」を「夢」と言い切ったところに、親鳥が安心してこの巣箱で雛を育て、その雛が成長して無事に巣立っていくようにとの祈りも感じられる。初めから終わりまで、作者の生きとし生けるものへの細やかな愛情が感じられる一句。
(さざなみ葉/「いぶき」)
花見上ぐ切腹前のやうな目で
竹内宗一郎
「街」
2025年6月号より
一読たちまち浅野内匠頭に同化して、読者も作中主体と共に桜を仰いでいる。この時点で、本作はポエムとしてすでに成功している。読者の心情も内匠頭や作中主体と並んでマナジリを決しており、明日無き、もとい、一刻の猶予も無き絶命の切迫感の淵に立つ。
この一瞬の死の美化と陶酔こそが、「花」の魔力か。危ないアブナイ。ワシは散らんぞ。
一方で、幸徳秋水や管野すが等の極刑後「春三月縊 (くび) り残され花に舞ふ」という悲痛なトリプル季重なり句で落花を見上げた、大杉栄を思う。関東大震災最中の外国人排斥に乗じて甘粕正彦陸軍憲兵大尉に虐殺された、彼と伊藤野枝と6歳の甥。「切腹前のやうな」日常を、大杉や野枝は生きていたのだね。私たちも、そうなるかもね。
(生倉 鈴/「楽園」)
啓蟄や分別かごに貯金箱
朝倉淳一
「伊吹嶺」
2025年6月号より
不要になった理由はわからないが、所持していた貯金箱を手放すということは、今までの生活の一部に別れを告げることでもある。新しく何かを始めるための準備かもしれない。貯金箱の中身はそのために使われたかもしれない。貯金箱をかごに入れた人物だけでなく、その貯金箱に目を留めた人物にも同じような変化があったからこそこの句ができたのだと思う。暗さやさびしさを感じさせないのは、啓蟄という季語があるからだろう。切れ字の「や」がこの句の景色を広くしている。
(弦石マキ/「蒼海」)
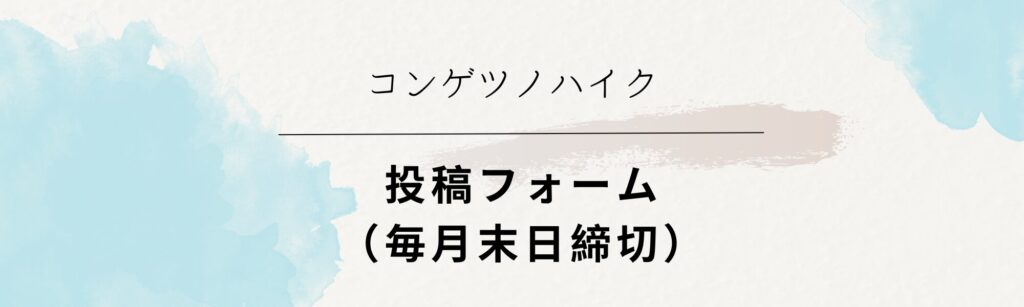
【次回の投稿のご案内】
◆応募締切=2025年8月5日
*対象は原則として2025年7月中に発刊された俳句結社誌・同人誌です。刊行日が締切直後の場合は、ご相談ください。
◆配信予定=2025年8月10日
◆投稿先 以下のフォームからご投稿ください。
https://ws.formzu.net/dist/S21988499/