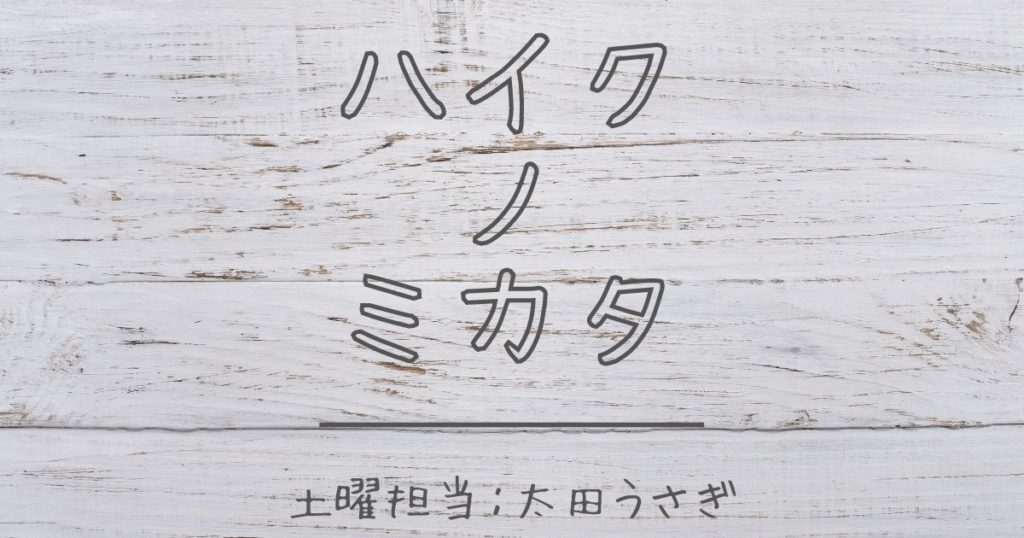
着ぶくれて田へ行くだけの橋見ゆる
吉田穂津
「着ぶくれ」はその姿がどこか不格好なことから、諧謔味やちょっとした哀感の漂う季語だが、薄くて軽くしかも暖かい肌着やアウターが安価に手に入る昨今では、かつてほどの実感はないのかもしれない。それでも、“着ぶくれて見せないコーディネート”のような使われ方は今でもよく見かけるし、身近な季語であり続けていることには違いない。
掲句は昭和50年前後に詠まれた句だ。ダウンジャケットやヒートテックの登場はまだまだ先の時代、寒さから身を守るにはひたすら着込むしかない。重ね着の揚句ふくら雀もかくやとばかりの姿で歩くうちに橋が目に入った。その橋の先に広がるのは寒々とした田圃ばかり、というのが句の趣旨で、衣類を何枚も纏うというある種の複雑さと、田へ渡ることのみを目的にした橋という単純さとが対照的な構図をなす。
ここで気になるのが<見る>と<見ゆる>の違い。<見る>は自分がその対象に目を向けて確認する自主的な行為、一方、<見ゆる>はその対象が先様から目に入って来る受け身な感じ。着ぶくれて些か不自由な身には後者の方がしっくり来る・・・んじゃないかな。どうでしょう。
作者の吉田穂津は略歴によると、「京鹿子」「沖」を経て波多野爽波の「青」に入会。以後、爽波の示す道を一途に学んだ人のようだ。掲句を収めた第一句集『インクスタンド』に寄せた序文で爽波は
句作りの実際の局面に於いて、辛抱に辛抱を重ねて、向こうから来るものを待つということは可成りの難事である。
しかし、その事無くしては写生は決して成就できない。
我慢して我慢して、その先に見えてくるもので勝負するのが写生であるといえよう。
と、持論の写生の重要性を説いた上で、自分の期待に応える数少ない女流との賛辞を彼女に与えている。
着ぶくれて田へ行くだけの橋見ゆる―これは紛れもないファクト、ありのままを述べたに過ぎない。けれど、爽波の言うように、“その先に見えてくるもの“を訴えかけてくる気がする。例えば、俳句は畢竟、”田へ行くだけの橋“なのではないか、というように。
(『インクスタンド』牧羊社 1988年より)
(太田うさぎ)
【執筆者プロフィール】
太田うさぎ(おおた・うさぎ)
1963年東京生まれ。現在「なんぢや」「豆の木」同人、「街」会員。共著『俳コレ』。2020年、句集『また明日』。