
【第7回】
集まる芸の「心」と「かたち」
盛夏の茶事
水無月も鼻つきあはす数寄屋哉 凡兆
旧暦六月は今の七月に相当する酷暑の時期。そんな中、茶室の狭さでは、「鼻をつきあはす」ようだ、というわけである。芭蕉の傑作撰集『猿蓑』でにわかに脚光を浴びた凡兆は、近代になると「写生」派の先駆けと位置づけられた。「も」は万葉以来ある「さえも」の意味でああって、「AもBも」といった現代に通じている意味用法ではない。
「膝をつきあわす」という言葉もあるが、それでは句が生きてこない。この酷暑の時期さえも、文字通り「鼻つきあはす」茶の湯の滑稽を詠んだ。ちょっと戯画っぽい描写で、確かに凡兆は、「眼」の俳人だ。さらに言えば、「鼻つきあはす」とは、いつも同じメンバーだという「月並」の含意もある。
秋近き心の寄や四畳半 芭蕉
これも酷暑の時期の、茶の湯や稽古を前提にした時、「秋近き」が効いてくるのであって、事程左様に、夏の茶事はハードで、会は月並みになりやすいのである。よって全ては「涼」がもてなしの基本となる。
盛夏の頃は昼にお茶事をしない。暑い中に四畳半のお茶室に火をおこして何時間もこもっていたら、熱中症になりかねない。そこで朝茶事となる。朝六時くらいには来てもらって朝ごはんを出して、九時すぎには終わる。あるいは夕涼みとなる。木地の肌に水を打った釣瓶の水指や建水、青々とした竹の蓋置、これらを茶の湯に用いて清々しさを取り入れ、楽しむのである。
美しき緑走れり夏料理 星野立子
この名吟は、茶の湯を詠んだものではないが、夏の接待の心はこの句に尽きる。「緑」と「夏料理」だけなら凡庸で、「美しき」と結論を言ってしまたら、さらに凡人度は濃くなるが、「緑」は料理なのか器なのかも限定せず大づかみに描写し、「走れり」でまとめることですべてが生きてくる。夏の涼は、視覚から、しかも一瞬のものだというのである。おそらく茶の湯にも大いに参考になる視点だろう。
余白の詩、余白のもてなし
盛夏の掛け軸も、さまざまあるが、絵で対象を具体的に描いたものより、余白のある紙の一部分に「滝」の歌だけ書きつけたような、軸を使ったりする。「白紙賛」という名まである。絵があるものと想定して、余白に賛だけを認めたものを言う。例えば大徳寺の大綱和尚が、半切の右上に細字で、
涼しさはたぐひもさらに夏山の峰よりおつる音なしの瀧
と賛をし、これは無地の白紙の部分を瀧に見立てて想像せよというのである。絵にかいてしまうと、それだけのことになってしまうが、余白の紙を前に、細い字で走り書きされた「音なし」の歌から想像すると、かえって滝の音が聞こえてくる。
古池や蛙飛び込む水の音 芭蕉
閑けさや岩にしみ入る蝉の声 同
音の詩人とも呼ばれる芭蕉一世一代の名吟も、「心」の音の発見が鍵だった。無音は音がないのではなく、ゼロ記号の音、すわなち休符の音なのである。この発想に「禅」を読み取るのは容易で、鈴木大拙から禅に入って、俳句の英訳に進んだブライスのステップもよく理解できる。立子の「夏料理」の句も、限りなく心の印象の「緑」なのであって、俳句の具象と抽象を考える上で恰好の題材となる。
一瞬を鷲づかみするには
「走れ」る「一瞬」であることは、二度とないという含意を孕む。「茶筅」で考えるのがいいかもしれない。利休の教えをまとめた『利休道歌』に、こんな歌がある。
水と湯と茶巾茶筅に箸楊枝柄杓と心あたらしきよし
名物を集めたお茶会であっても、おろしたてのくたびれのない茶巾、真新しい削りの茶杓、形の整った卸したて茶筅が置いていなければ、様にならない。消耗品こそ、少し贅沢にもので「心」を更新する。ホテルの良しあしは、消耗品にサニタリーに拠るのと近い感覚だ。特に茶筅は、閉じられた穂先が開いて、二度とは使えない。一度いいものを使うと、もう「もてなし」には、卸したてしか使えなくなる。
俳句も「心あたらしき」がいいのであって、だから芭蕉も旅に出て、心と五感を更新した。子供に詠ませる方が上手いといったのもそういう意味であろう。かのボードレールも『現代生活の画家』で同じことを言っているではないか。「天才とは意のままに取り戻された子供時代」に他ならないとし、「骨の髄からの散策者、熱烈な観察者」になることを求め、「物を大きく見て、何よりも、それら全体の与える効果」を考えて、「総合的、省略的な視線」でデッサンすることを推奨する。それは、日常の一期一会化なのであり、今ここに徹しきって、変化を逃さないことであろう(川本皓嗣『俳諧の詩学』「不易流行とは何か」)。
「かたち」が生む「こころ」
「不易流行」が俳句でも茶道でも様々に解釈されてきたが、ボードレールも、はやりのレトリックや意匠で飾り立てることなく、アンテナをはってルーティンの中に今起こるわずかな変化を捉え、誠実に言い留めることこそ肝要だと言う。日本でこういう西洋の現代芸術論を俳句論に転用したのは、桑原武夫が紹介したアランの言説(俳諧は寓意的デッサンに似た極東の短詩)であり、そこにヒントを得て俳句論の古典を成した山本健吉なのである。
最後まで対象を見失っていない、恣意なる情念の動きの抑制として、礼節として、俳句形式の身についた属性となっていること、それが季語の俳句における役割に外なるまいと思われます。 (「純粋俳句」)
茶道も俳句も四季の循環の生活文化と続きの世界から、花を開かせた。「かたち」=礼節の重要性を認知していたからである。礼節を軽く見たイマジズムは、後継を無くして消えていったが、礼節の重みをわきまえていた、季語の文化が営々と続いているのである。
人間はいはば礼節にかなふ時しか安静であり得ない。しかし、人間が人間として可能な限りの美に到達するのも、この道によつてである。そしてその反対に、何らかの永続的なものを表さない顰め面、愚かしい微笑、顔面痙攣、皺などは、安静にしてゐれば最も好ましかるべき顔を醜くしてしまふ。 (アラン『芸術論集』)
こうしたアランの言説を日本で最初に紹介しながら、戦後思潮に軽薄に乗って、俳句を第二芸術だなどと烙印を押した桑原への最大のプロテストとして健吉があったことは間違いない(井上「山本健吉の歳月1」『俳句』二〇二三年一月号)。彼が晩年茶道を論評しだすのも、けだし当然の帰結だったのである。
「こころ」から「かたち」が生まれる。それはそうだが、共有された「かたち」なしに「こころ」は集えないのである。
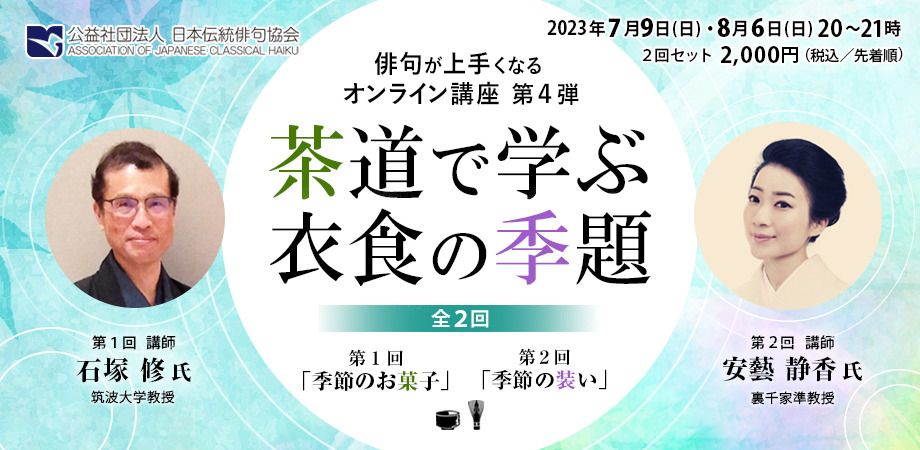
【執筆者プロフィール】
井上泰至(いのうえ・やすし)
1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。
【井上泰至「茶道と俳句」バックナンバー】
◆第1回 茶道の「月並」、俳句の「月並」
◆第2回 お茶と水菓子―「わび」の実際
◆第3回 「水無月」というお菓子―暦、行事、季語
◆第4回 茶掛け―どうして芸術に宗教が割り込んでくるのか?
◆第5回 茶花の心
◆第6回 茶杓の「天地」―茶器の「銘」と季語
【井上泰至「漢字という親を棄てられない私たち」バックナンバー】
◆第1回 俳句と〈漢文脈〉
◆第2回 句会は漢詩から生まれた①
◆第3回 男なのに、なぜ「虚子」「秋櫻子」「誓子」?
◆第4回 句会は漢詩から生まれた②
◆第5回 漢語の気分
◆第6回 平仮名を音の意味にした犯人
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
