
少し動く
春の甍の
動きかな
大岡頌司
私の連載は全8回の予定だが、2回ごとにひとまとまりとし、それぞれにテーマを設けてそれを中心に展開していく。第1、2回では、大岡頌司の俳句を取り上げ、彼の三行表記俳句と後の一行表記への回帰についてテクストベースで論じる。特に、一行表記への回帰については論じられる機会が少ない。本稿を通じて、その魅力を再考したい。
大岡頌司は主に三行表記俳句で知られているが、もとは寺山修司編集の「牧羊神」に安井浩司らと参加していた。第一句集『遠船脚』(昭和32年、私家版)には「青春俳句」の匂いを感じる一行表記の句が収録されている。その翌年から寺山の紹介で高柳重信の「俳句評論」に加入、多行表記へ転向した。以降長らく三行表記俳句を作り、『臼處』(昭和37年、私家版)、『花見干潟』(昭和38年、俳句評論社)、『抱艫長女』(昭和48年、端溪社)、『利根川志圖』(昭和50年、端溪社)と三行表記で句集を刊行した。のちに一行表記へと回帰するが、その話は次回に譲ろう。
特に、高柳重信が四行表記に収斂したのに対して、大岡頌司の三行表記は高柳重信とは異なる多行表記の作品世界を確立したと評価される。ここで高柳重信が引き合いに出されるのは、彼が多行表記俳句の創始者ではないにしても、一般に「多行俳句=高柳重信」というイメージが形成されているからだろう。
掲句は『抱艫長女』所収の三行表記俳句であり、内容としては、「春の甍」(いらか、瓦葺の屋根のこと)が少し動いたというそれだけだ。一行目で「少し動く」と何かが動いたことを示し、二行目で「春の甍」が動いたことが分かる。三行目でどのような展開をするのかと思ったら、「動きかな」と再び一行目の動きへ戻ってくる。一行目と二行目で春の瓦葺屋根の瓦が少しずれた様子を見せ三行目でその動きを改めて詠嘆するというこの句の回帰構造は、「望郷」の俳人と言われる大岡頌司を象徴的にあらわしているように思われる。来し方への視線である。
『臼處』より
かがまりて
竈の母よ
狐來る
*
祖母の茶が
さめてゐる
麥藁帽子の留守
*
『花見干潟』より
今は花なき花いちじくの
日は龍宮の
杖のつりざを
*
寸烏賊は
寸の墨置く
西から來て
『臼處』にはここにあげた句のように「母」や「祖母」など故郷を思わせる郷愁的で直接的なモチーフが多く登場する。「母」という言葉がもたらす望郷のイメージが一つのステレオタイプであることには注意すべきだが、当時の作者および読者はきっと故郷の映像をイメージしたはずだ。〈かがまりて〉句では、「母」という言葉の後に「狐來る」という言葉が置かれることで、故郷の現実と幻想が交錯する感覚が生まれる。改行によって「狐」の存在感はより際立っているだろう。「今は花なき花いちじくの」には、実際には無花果が美しい花をつけることはないが、過去にそのような花を咲かせていたかのような幻想が込められている。また、「西から來て」には、寸の烏賊が遥か西方(浄土)からやってきたというイメージが描かれており、遠い過去や理想郷へのまなざしを象徴している。そもそも、『花見干潟』の自序が「來し方へ來し方へ」と始まるように、確信犯的に過去を見つめるポーズをとっていたと言えるだろう。
では、内容面で望郷に意識的であったことは明らかだが、それが三行表記という形式によって表現されたという点ではどうであろうか。大岡頌司の三行表記は、三行を読み進めたときにイメージが発散してゆかず、三行で景が収束するように思われる。いくつか例をあげよう。
『花見干潟』より
ぎんなんいる
ひるのてぐせ
とおもふべし
*
『抱艫長女』より
冬のをはりの
丈餘の樹々の
けむりかな
*
『利根川志圖』より
手が沼の
夢の續きの
へびいちご
〈ぎんなんいる〉句は、「てぐせと/とおもふべし」によって銀杏の実を炒って食べるばかりの無為の昼をゆるそうとする感覚がある。〈冬のをはりの〉句は、三行目「けむりかな」に至って一行目、二行目で見えた寒林が白煙に包まれる。〈手が沼の〉句は、一行目で「手」と「沼」が重ねてイメージされ、二行目で夢うつつの感覚になり、三行目で「へびいちご」の赤い実が見える。「の」で繋がっていく句形では読みの速度が上がる傾向があるが、その速度が改行によって抑制され、「手」「沼」「夢」「へびいちご」と展開される名詞の連なりが言葉の質感で上滑りせず、確かなイメージを結ぶ。この句はそれぞれの言葉を貫くイメージの細い糸を読者がどこまでも手繰っていくような句ではなく、一つの映像(それは必ずしもリアルではない)の中に収まっている。
一つの景に収まるというのは、一行表記の「スタンダード」な俳句と同じだ。大岡頌司の三行表記俳句には、一行俳句での「スタンダード」な読み方がある程度通用する。また、三行の改行位置が五七五と一致する句が多いというのも読みやすさの一端を担っているだろう。形式では前衛的な多行表記を試みながらも従来の一行俳句と親和性があり、それに心惹かれるのが大岡頌司の俳句に感じる郷愁なのかもしれない。多行表記というフロンティアから、一行表記という故郷をはるか見つめているのだ。
次回は、大岡頌司が一行表記へと回帰した後年の作品を取り上げ、三行表記との比較を試みる。形式の変遷を辿ることで、大岡頌司にとって一行表記は「故郷」への単なる回帰なのか、それとも新たな表現の選択だったのかを考えていきたい。俳句という定型詩に関わる限り、形式との向き合い方は避けて通れないテーマであろう。
(句の引用は『大岡頌司全句集』(浦島工作舎、2002年)による。)
(関灯之介)
【執筆者プロフィール】
関灯之介(せき・とものすけ)
2005年生れ。2020年秋より作句。楽園俳句会、東大俳句会所属。第1回鱗kokera賞村上鞆彦賞、第12回俳句四季新人賞、第3回楽園賞準賞。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
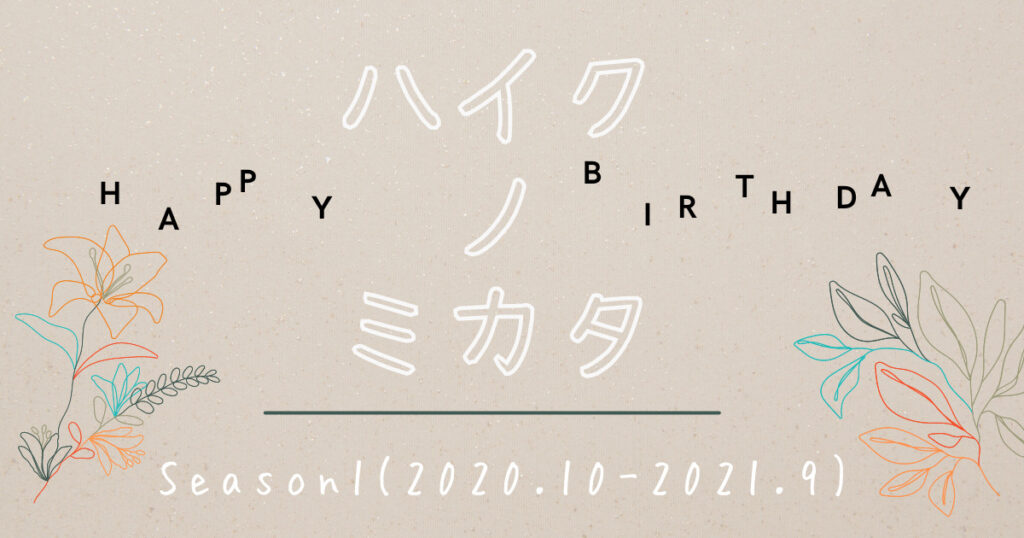
【2025年2月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔5〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
>>〔4〕水涸れて腫れるやうなる鳥の足 金光舞
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
>>〔9〕をちこちに夜紙漉とて灯るのみ 阿波野青畝
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
>>〔9〕千駄木に降り積む雪や炭はぜる 車谷長吉