
【第6回】
茶杓の「天地」―茶器の「銘」と季語
草花や動物に名前があるように、茶道具の中にも名前がある。茶の湯の世界では「銘」と呼ばれ、元来は優れた茶道具に付けられた尊称であり、14世紀の中頃に「茶壷」に付けられたのを始まりとして、茶入や天目茶碗などに銘が見られるようになる。由来は、道具の印象や旧所有者に因むものから、道具そのものの形象、物語などに因むものまでさまざまある。なかでも、季語の世界と相通じるのは茶杓の銘であろう。
茶の泡に春夕焼のとどまらず 加藤楸邨
試みに、新暦七月の茶杓の銘を挙げてみよう。山清水・風鈴・涼風・夕涼み・夏衣・青簾・涼扇・氷室・夏野・川風・打水・涼船・水中花等々。まさに季語のオンパレードではないか。その月の異名や年中行事に関する言葉も使われる。利休は、当時の常識だった能から取っている。能の詞章は、季語が溢れている。虚子が俳句と茶をパラレルに語る理由も見えてくるようだ。
ただし、禅語や和歌を銘とした茶杓は季節に関係なく使用できる。いわば「無季」の茶杓である。「好日」「無一物」「和敬」は平常時に、「瑞雲」「八千代」は慶事に使うといったように、茶会の趣旨に応じて使い分けられるのである。また、薄茶の場合、季語を銘とすることが多く、濃茶の場合は、和歌銘や禅語銘、風習銘などが付けられるケースが多い。
虚子は、40代で大病するあたりから禅語への関心が強くなるが、禅に影響を受けた世阿弥だけでなく、茶道のことも念頭に置いておくべきだろう。
さて、茶杓の「銘」が明かされるのは、会の最後の最後である。会席が進むうち、曖昧模糊とはいえ臨席する者一同に共有されるアトモスフェアというものが醸成される。そこで、亭主は当意即妙に銘を明かして、その会のアトモスフェアを主題化するのである。「銘」の存在は、座の文芸と呼ばれ、紙の記録は痕跡に過ぎないと言われた連歌・俳諧と同じ環境で成り立つものなのである。
こうした茶杓の機能や位置が見えてくると、茶の道を究めだせば、亭主は自身で茶杓を作るようにもなる。茶杓は、現在主に竹で作られる。元来は、薬匙が代替として使われていた。なので、象牙やべっ甲といった高級素材で作られていた。「わび」茶の利休の時代になると、竹が主流になってくる。 苦竹科の竹、なかでも「晒竹(白竹)」を利用することが多い。また、囲炉裏の天井部分などに使われている「煤竹」や樹木が使われることもある。
利休がべっ甲や象牙といったプロの職人の材料を棄てて、加工しやすい竹を使いだしのも、この辺の事情から見えてくる。亭主の「心」の表現のシンボルが茶杓の形状と「銘」なのだと気づいてみれば、自分の手で加工したくなるのは人情だ。
11月末から2月にかけて、まず竹を伐採するところから始まる。伐った竹は日の当らない場所に半年以上寝かせて、ガス台などで熱して「抜き」を行う。こうして油を抜いた竹は、数週間天日干しにしたあと、さらに数ヶ月から数年寝かせる。これでようやく茶杓の素材が出来上がる。
竹を割って、まげやすく削りやすいように裏全体を平らにして、形を整える。そのあと、水に入れた容器にこれを浸けて十分に水を吸わせてから、鍋などで煮て柔らかくする。次に蝋燭を使ってこれをまげて、水につけて冷やす。5日をみておけば削りの準備も万端となる。
次に茶杓の姿を鉛筆で描き、その線に沿って削っていく。太い方から細い方へ削っていくのが鉄則だという。あらかた形を削り終わると、ヤスリで仕上げ、形に満足できたら、「切り止め」と「櫂先(かいさき)」に一刀ずつ入れて完成となる。
抹茶をすくう茶杓の先端を、「櫂先」と呼ぶ。茶杓の形の「個性」がもっとも判別できる部位だ。その最先端は「露」と呼ばれ、丸みのあるものや尖ったものなどがあって、作者やこれを選ぶ亭主の好みが表れる。
節の部分から「櫂先」に向かう筋を「樋(ひ)」と呼び、「櫂先」と反対側の端を「切り止め」と呼ぶ。「切り止め」には仕上げに加える刀痕があり、これも焦点化されやすい。
私は茶道の素人なので、辞書的な説明に自分なりの解釈を施していったが、この茶杓の工程が、また俳句に酷似していると思うのである。
一種の職人芸に近いが、本物の職人の技術ではなく、素人もある程度の修練で、格好がついて、極めればかなりのレベルの自己表現ができる。俳句の主宰と弟子の関係に近くはないだろうか?五七五の無個性な洋式と、何よりもその短さ・小ささがプロと一般の差を縮めているのである。盆栽の芸に近いと言ったらいいだろうか。小ささと定型は、多くの参加者を呼び込むのである。
そして、茶杓の形状と銘は、会という集団の場の、「一期一会」で定立する。結社にしろ、一般誌や新聞の投稿しろ、選者とそれを信頼する人々との間で行われるやり取りの中で成立する。ここで「季」は重要なマナーとなる。共同の「心」の母胎となるからである。
「季」と「会」がなくなってしまったら、それは欧米の詩やパーティと何ら変わりないものになってしまう。虚子が頑固に俳句を「季題」の文学だと言い張り、茶会と同様の融通無碍の天地だと晩年述懐した意味は、この茶杓という小さな制約の中に生まれた自由の世界を想起してみた時、初めて理解できるのである。
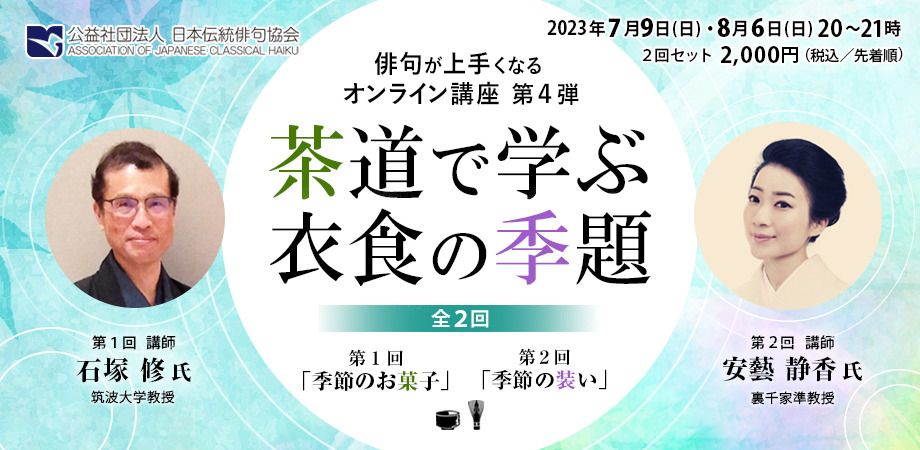
【執筆者プロフィール】
井上泰至(いのうえ・やすし)
1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。
【井上泰至「茶道と俳句」バックナンバー】
◆第1回 茶道の「月並」、俳句の「月並」
◆第2回 お茶と水菓子―「わび」の実際
◆第3回 「水無月」というお菓子―暦、行事、季語
◆第4回 茶掛け―どうして芸術に宗教が割り込んでくるのか?
◆第5回 茶花の心
【井上泰至「漢字という親を棄てられない私たち」バックナンバー】
◆第1回 俳句と〈漢文脈〉
◆第2回 句会は漢詩から生まれた①
◆第3回 男なのに、なぜ「虚子」「秋櫻子」「誓子」?
◆第4回 句会は漢詩から生まれた②
◆第5回 漢語の気分
◆第6回 平仮名を音の意味にした犯人
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】
