
銀行へまれに来て声出さず済む
林田紀音夫
林田紀音夫(1924-1998)は実生活とその作品が密接した作家であった。戦時中は川西航空機に徴用され、終戦の年には最後の現役兵として華北に渡った。復員してからもなかなか職を得られない中で、肺結核を患って入院するといった苦しい生活を送った。復員してから定職を得るまで、ついに11年もかかったようである。昭和30年代、日本の経済成長がはじまり、俳句史では金子兜太が造形俳句論を唱え高柳重信が「俳句評論」を創刊するなど、前衛俳句が勃興した頃のことだ。林田紀音夫自身は、戦前は新興俳句系の雑誌を転々とし、戦後は下村槐太に師事して「金剛」編集同人となる。槐太のもとで謄写印刷を手伝うなど、生活の面でも深い関りがあったようだ。「金剛」廃刊後、昭和28年に堀葦男、金子明彦らと「十七音詩」を創刊、「青玄」「風」同人を経て昭和37年「海程」創刊同人、「花曜」客員同人。系譜的にも時代的にも前衛の戦後派俳人の一人に数えられ、その作品は新興俳句系の無季俳句の流れを引きながらも意味内容と内面意識の深化を散文的な文体に結実させる独自の作風を形成した。
句集はその多作に対してたった二冊、『風蝕』(昭和36年、十七音詩の会)、『幻燈』(昭和50年、牧羊社)のみ。生活苦にあえいだ昭和20年から昭和32年の作は『風蝕』に収録されており、掲句もそのうちの一句だ。銀行にたまに来て、残り少ない貯金を引き出す。窓口の職員と交わすのは事務的なやり取りだけ、「引き出しで」「三万円」など短い言葉で済んでしまう。声を出すことは、ときに自分の存在を証明することになる。声を出さないで済んでしまう生活は、自分という存在がだんだん小さくなっていくような感覚に陥るだろう。掲句は韻文的な調べよりも意味内容に比重が置かれており、散文的で無機質な句の感触に、社会に生きながら個々がばらばらになってしまった現代人の孤独感が宿る。以下に、『風蝕』から何句か引用しよう。
顔洗ふときにべとつく雨の音
鉛筆の遺書ならば忘れ易からむ
煙突にのぞかれて日々死にきれず
隅占めてうどんの箸を割り損ず
マーガリン不覚に匂ふ口噤む
子供の足ながらひびきて朝刊来る
舌いちまいを大切に群衆のひとり
引廻されて草食獣の眼と似通う
消えた映画の無名の死体椅子を立つ
醱酵槽の円ならびこころから痩せる
これらの句は、「顔洗ふ」「うどん」「マーガリン」など日常生活に取材しながら、その生活の中で感じる孤独感や劣等感といった主体の内面を深く刻み込む。一人でいるときよりも大勢の中にいるときの方がかえって孤独を感じることがあるが、その孤独感が根底にあるのが「隅占めて」や「群衆のひとり」であろう。ここで、群衆のそれぞれの人は代替可能な誰かだ。散文的な叙述をしながら主体を明示しないことで生じる空白に、「あなた」が代入可能になる。具体的な社会生活を詠いながら、普遍的な社会詠を成立させている。
私はこれらの句に「社会性」を感じるが、林田紀音夫が「社会性」という言葉で評価されることはあまりないようである。
「ペシミズム」は林田紀音夫を評するときによく用いられる言葉だ。
林田君の作品の基調にはどうしようもないペシミズムが、ちようどあの水害時の溢水のように胸元までひたひたと浸して来るところがある。このようなふかいペシミズム。受身で傷つき易い魂。それが直ちにいわゆる庶民大衆の底辺感情と速断することは出来ないにしても、少なくともそれは底辺的存在を意識することによつてひときわ人間であることに悲傷し、絶望する、多感な魂のおののきにほかならない。良心などという生温かいものではない、鋭敏な詩質。(堀葦男、「仲間のことばⅠ」『風蝕』昭和36年)
この「ペシミズム」やアンニュイさは、林田紀音夫の俳句の抒情だ。抒情性に「社会性」を見出すか否かという問題は、安里琉太が「俳句四季」2022年11月号の特集「今こそ『社会性俳句』」で触れていた。
〝現代社会を背景に広く共感されるであろう気分〟とでも言おうか、そういう感慨や抒情性によって読者を共感させる句も「社会性俳句」の範疇になるのだろうかと少し悩んだ。(中略=筆者)興味深いのは、このような〝気分〟の共感性の方が、今日、ともすれば冒頭に挙げた欣一や公平の句(筆者注:それぞれ〈主婦たゝら踏むメーデーやヒロシマに〉〈川へ虹プロレタリヤの捨て水は〉)の方法よりもはるかに、「社会全般に関連する性質」として心を惹く、理解されやすい方法のようにも見える。(「俳句四季」2022年11月号)
〈鉛筆の遺書ならば忘れ易からむ〉〈消えた映画の無名の死体椅子を立つ〉といった「死」を主題にした俳句の抒情も、社会性のもとに立ち上がってくる、というのが私の感覚だ。「忘れ易からむ」「無名の死体」に表れている個人が希薄化あるいは匿名化する感覚は、肥大した大衆社会という時代性を背景に読み取れる。それに加えて、「忘れ易からむ」とわざわざ言うところや「椅子を立つ」といって主体の存在を明示することで、苦しい現実をペシミズムで観察するというナルシズムがあらわれる。それは時に、「インテリ」とさえ言われた。
林田紀音夫の俳句に「社会性」を見出すことができたからといって「社会性俳句」と評されないのは、「社会性俳句」というと、狭義に昭和20年代末から30年代初頭にかけて巻き起こった俳句の社会性に関する論争を言うからであろう。林田紀音夫は、論争の影響を受けているに違いないが、作家としての活躍は論争よりすこし後になる。
昭和28年頃から昭和31年頃にかけて、俳壇で俳句の社会性を巡る議論が盛んに行われた。その経緯は省略するが、結論はおよそ以下の通りだ。
社会性俳句の主張は、意識的に社会、思想を俳句の対象としてクローズアップさせた。社会性俳句論は俳句を文学本来のあり方に戻そうとする運動であって、俳句で詠うテーマ、内容を重視した。また、社会性を素材のみの問題とせず、俳人の態度、モラル、主体性の重要さという問題も浮び上がらせた。中でもそのモラルは常識的、皮相的なものではなく、劃期的な新しいもの、本質、核心を求めるべきであるとする意見がみられたことは貴重なものであった。もっとも、これは社会性俳句の実績としては実現しなかった。(松岡潔、『現代俳句評論史』角川書店、平成17年)
これまで、俳句の「社会性」に関する議論は主に俳句の作者の立場から論じられてきた。というのも、「社会性俳句」は、思想性が欠如している俳句には現代の人生を表現することができないという桑原武夫の第二芸術論へのひとつの応答であったため、「社会性俳句」論争が実作者側の議論になったのは必然だろう。また、終戦からまもなくは、新たな俳句をいかに作り上げていくかという時代の要請もあっただろう。しかし、兜太の「社会性は作者の態度の問題である」(「風」昭和29年・11月)という言葉はあまりにも有名であり、今でも社会性をいかに詠み込むかが盛んに議論される。「俳句四季」2022年11月号の特集「今こそ『社会性俳句』」でも多くの寄稿が社会的な事物をいかに詠むか或いは詠むことの意義という議論を展開し、中には「社会性は俳句の素材として排除されるべきではない」という結論で終わっているものさえある(もちろん「べき」論の再考はつど行われる「べき」だが)。
令和に入ってすぐのCOVID-19パンデミックやロシアによるウクライナ侵攻によって俳句の「社会性」は再び脚光を浴びるようになったが、「社会性」が今の時代を詠むために必要になったのではなく、具体的な危機によって社会のほつれが顕在化し、俳句においてもそれが意識されるようになったにすぎない。ただし、その「社会性」の内実は、戦後すぐの論争が行われていた時代とは異なるはずだ。「俳壇年鑑2024年版」の鼎談「俳句史という視座」で、神野紗希が俳句の主体の性質の変化として、今の主体は「私」でありながら「同時に今を生きている入れ替え可能な複数の私たちのうちの一人」(「俳壇」2024年、5月号増刊)であるという指摘をしている。また、「希薄でありながらしっかり世界を見つめている主体」(同前)とも言い換える。つまり、個としての強固な「私」ではなく、より流動的で、多くの人が共有しうる視点としての「私たち」へと変化しているのではないか。
この指摘は、俳句の「社会性」との関わりにおいても示唆的である。重要なのは、主体の性質が本質的に変わったかどうかではなく、俳句の作者・読者の意識の中で、「主体」をより広がりのあるものとして捉える動きが生じていることである。かつては、作者が社会と繋がった主体を立ち上げ、それを読者が受け取るという構造だった。しかし、現代では、俳句の主体が「私」から「私たちのうちの一人」へと広がり、より読者と共有可能なものへと変化している。もっと言うと、読者が意識的に俳句を読み取りに行こうとする必要がある。「社会性」と接続されるのは、もはや作者ではなく(作者を含めた)読者自身となった。それを実感したのが、自句で恐縮だが、「楽園」第4巻第2号の〈風鈴や月を凹ます星礫〉という句の堀田季何による選評である。
美しい字面のようで、何気に恐ろしいことが詠まれている。風鈴を風が打てば涼やかな音が響き渡るが、同じ夏の夜、月の裏側を星礫(主に隕石)が打っても私たちの殆どはそれに気づかない。(中略=筆者)仮に地球のメディアでたまに報道されても、人類の大半はスルーするであろう。それよりも、眼前の風鈴を風が打つ方が大事なのだ。勿論、万が一(確率的にはそれよりもはるかに少ないが)、(地球を凹まし得る)巨大な星礫が地球に迫ってきたら、ようやく騒ぐことだろうが、時すでに遅し。たぶん助からない。あっ、これって、地球の裏側で起きている虐殺などについても同じようなことが言えるでは、と思ったら作者冥利に尽きるであろう。(「楽園」第4巻第2号、令和6年、傍点=筆者)
あえて言い切ろう。現代において、社会性は読者の態度の問題である。解釈において読者は絶えず自分の生き方に対峙しているが、この対峙の仕方が作者の態度を決定する。これは、俳句に込められるべき社会的メッセージを過剰に意識せよ、ということではない。むしろ重要なのは、現代という時代において、あなたが俳句をどのように読み取り、それがどのように社会と関わるのかを意識することだ。
(関灯之介)
【執筆者プロフィール】
関灯之介(せき・とものすけ)
2005年生れ。2020年秋より作句。楽園俳句会、東大俳句会所属。第1回鱗kokera賞村上鞆彦賞、第12回俳句四季新人賞、第3回楽園賞準賞。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
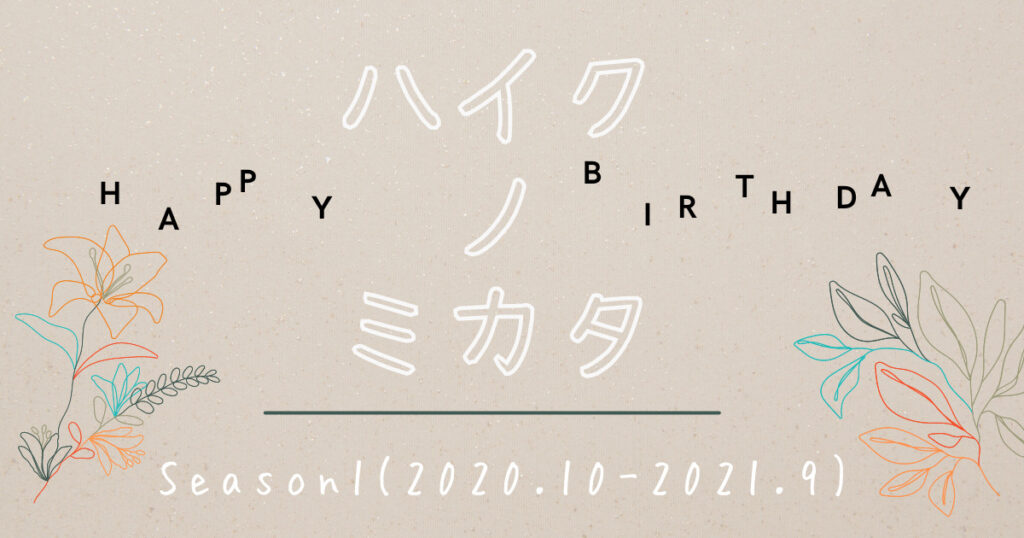
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
〔2月12日〕体内にきみが血流る正坐に耐ふ 鈴木しづ子
〔2月13日〕出雲からくる子午線が春の猫 大岡頌司
〔2月14日〕白驟雨桃消えしより核は冴ゆ 赤尾兜子
〔2月15日〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣
〔2月16日〕百合の香へすうと刺さってしまいけり 平田修
〔2月18日〕古本の化けて今川焼愛し 清水崑
〔2月19日〕知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる 村上海斗
〔2月20日〕銀行へまれに来て声出さず済む 林田紀音夫
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
>>〔4〕水涸れて腫れるやうなる鳥の足 金光舞
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
>>〔9〕をちこちに夜紙漉とて灯るのみ 阿波野青畝
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
>>〔9〕千駄木に降り積む雪や炭はぜる 車谷長吉