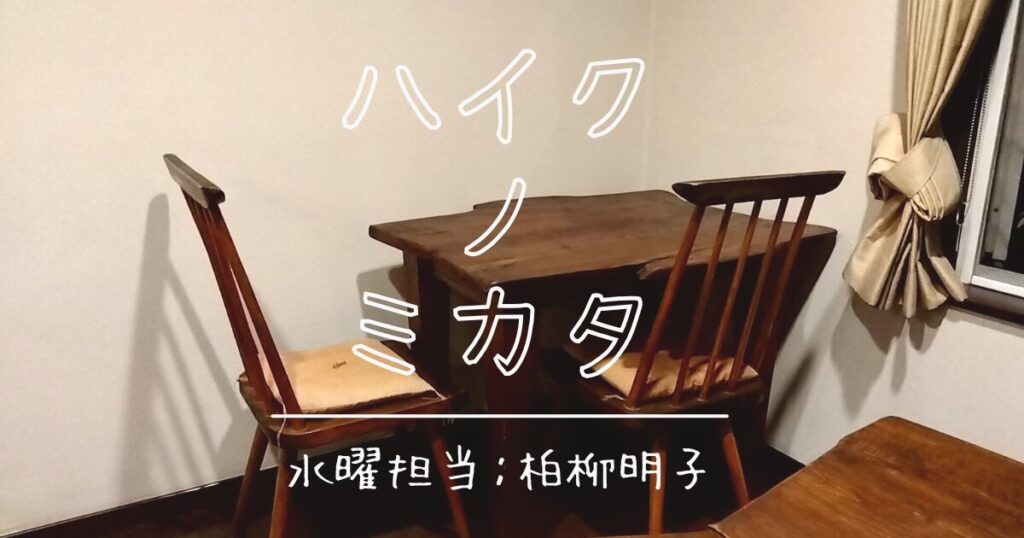
猫消えて真紅の林檎垂るるのみ
加藤楸邨
「猫は警戒心が強い」と言われる。遠くにいても人間の気配を察知して、警戒のまなざしをまっすぐに向けてくる。なかには近づくことのできる猫もいるが、大概は一定の距離を越えた途端に素早く走り去る。仔猫時代に母猫から教育をしっかり受けているのだろう。特に野良猫にとって生きるためには当然の本能であり行動だろう。
掲句の猫はなぜ消えたのか。上述のように人間を警戒してだったのかもしれない。あるいは、飼い猫や地域猫のように人間にとって「親しみのある猫」が死んでしまったことを「消えて」と婉曲的に表現しているのかもしれない。どちらにせよ、しなやかでどこか謎めいた存在感と猫の生命が上五に漂っている。
その猫は林檎園を根城としていたのだろうか。真っ赤な林檎がたわわに実る美しく豊かな様子を「垂るる」を表現することで、前半の猫の透明感がいやまし、つやつやとした林檎のボリュームと色の鮮やかさが読者の眼前にクローズアップされる。
この原稿を書いている一か月半ほど前、掲句のような風景を目にした。
遅い夏休み、句友への初対面の前に家人とともに小布施に立ち寄った。千曲川を渡ると、既に赤く色づき始めている林檎園や栗畑が一面に広がっていた。まだまだ暑さは容赦なかったが、眼前の景色には確実に秋の訪れが感じられた。小布施でのお目当ては岩松院の天井画「八方睨み鳳凰図」と小林一茶の句碑。葛飾北斎の晩年に描かれた天井画の鳳凰の眼力は凄まじく、鮮やかな羽根を巴紋のかたちに見せながら仰ぐ者たちを悠々と見下ろしていた。一茶直筆の句碑「やせ蛙負けるな一茶是にあり」は蛙合戦の池のほとりにあり、蟬の声に包まれていた。寺の背後には青い山が広がり、静かで緑の匂いが濃い、豊かな時間だった。
寺を堪能した後、小布施の街へ向かおうとした時だった。
「あ、猫」
家人が小さく囁いた。見ると、曼珠沙華の赤に紛れて猫がいた。大人になりかけといった感じの灰色のしなやかな体つきだが、ひょこひょこと右足をひきずっていた。二人で少し近づくとこちらに気づき、暫く互いに見つめあう形となった。でも、すぐに足をひきずりながら家の隙間へ消えていった。
猫の去った近くには投句ポストがあったが、現在は使用していないようでその旨が書かれた注意書きが貼られていた。
「一茶ゆかりのお寺なのに、もったいないね」
ぽつりと家人が言った。私も頷いた。
駐車場の前には林檎園があった。これから熟れていく途中の林檎もあれば見事に熟した林檎もあった。なかには、台風が近かったこともあったのか地に散乱して朽ち始めているものも見受けられた。でも、林檎の輝きは山々や空の青と呼応して、心をのびやかにしてくれるかのようだった。
その日、宿泊した場所は台風の影響で楽しみの外食もままならなかった。家人も私も俳句をやる同士だった。私たちは近所のデパ地下で食料と酒を買い込み、宿で「俳句でも作るか」と歳時記を取り出したものの、結局「水曜どうでしょう」の再放送を見てゲラゲラ笑って終わってしまった。
翌日。台風の余波を何とか交わしつつ無事に句友との初対面を果たし、今春亡くなった私の母の死を母の実家の墓前へ報告に行くこともできた。
まだほんの少し前のことなのに。
家人は突然、天へ旅立ってしまった。ある朝、あまりにも静かに。
猫が大好きな人で、いつか猫と三人で暮らそうと話していた。
猫は死期を悟ると消えるというが、そんなところを真似しなくてもいいのに。
私たち二人とも加藤楸邨や田中裕明が大好きだった。特に家人は彼らの句の中の「哀しみ」に共鳴しているようだった。
消えてしまった猫。
でも、いつか林檎の木の下にひょっこりと姿を現すかもしれない。
私にはたくさんの家人の俳句が残っているから、俳句を続けている限りはどこかで彼と再会できるだろう。だから今は此処で俳句と共にいようと思う。そして、いつか二人の夢だった猫との暮らしを実現したいと思っている。
加藤楸邨『猫』(1990)所収。
(柏柳明子)
【執筆者プロフィール】
柏柳明子(かしわやなぎ・あきこ)
1972年生まれ。「炎環」同人・「豆の木」参加。第30回現代俳句新人賞、第18回炎環賞。現代俳句協会会員。句集『揮発』(現代俳句協会、2015年)、『柔き棘』(紅書房、2020年)。2025年、ネットプリント俳句紙『ハニカム』創刊。
note:https://note.com/nag1aky
【2025年11月のハイクノミカタ】
〔11月1日〕行く秋や抱けば身にそふ膝頭 太祇
〔11月2日〕おやすみ
〔11月3日〕胸中に何の火種ぞ黄落す 手塚美佐
〔11月4日〕降誕の夜をいもうとの指あそび 藤原月彦