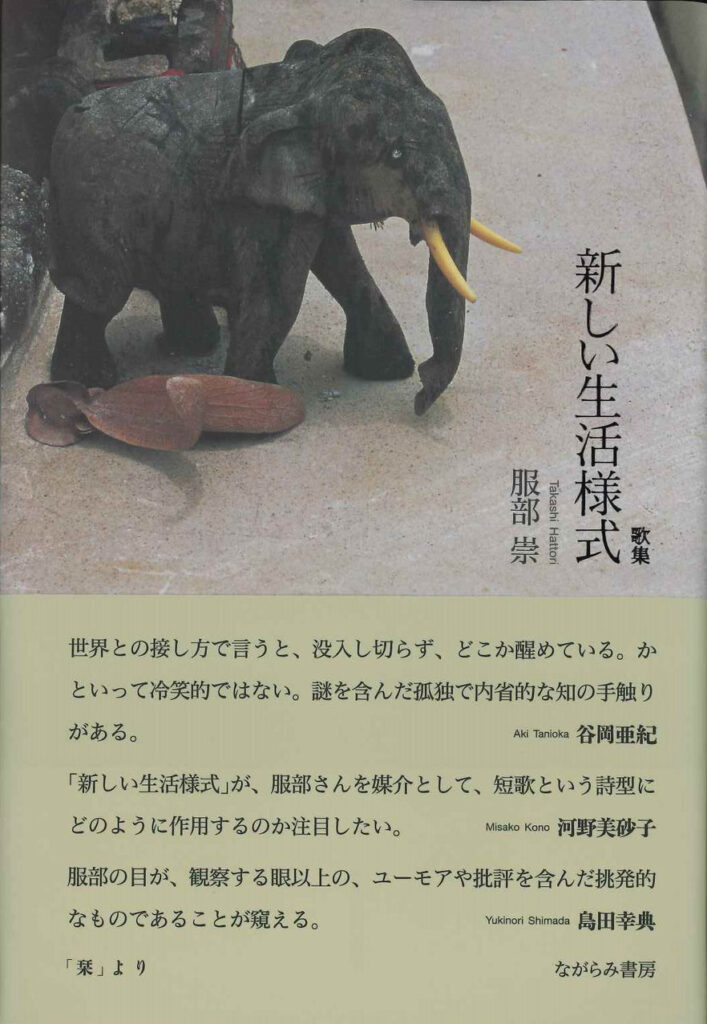毎月第1日曜日は、歌人・服部崇さんによる「新しい短歌をさがして」。アメリカ、フランス、京都そして台湾へと動きつづける崇さん。日本国内だけではなく、既存の形式にとらわれない世界各地の短歌に思いを馳せてゆく時評/エッセイです。
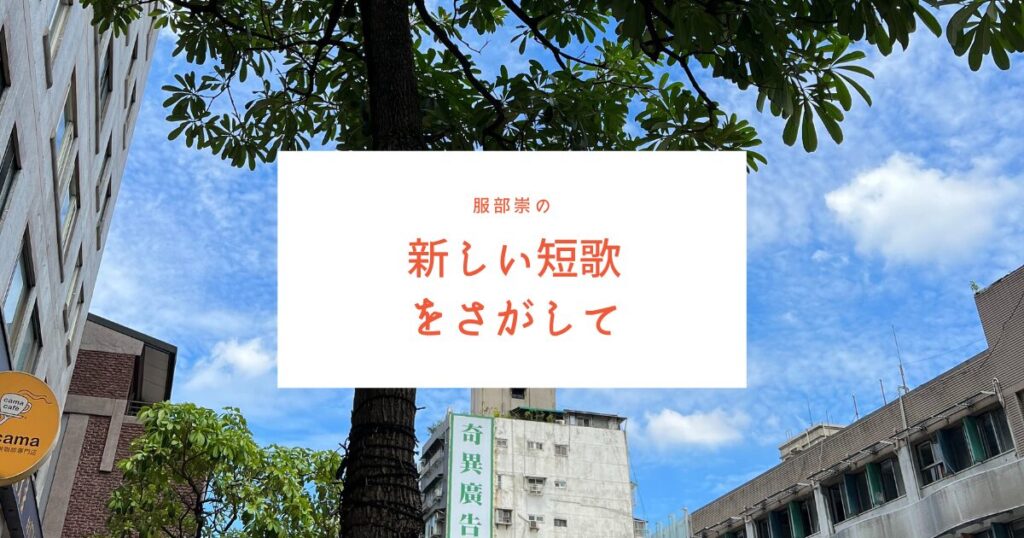
【第36回】
啄木とクレオール
去る4月26日、台湾新北市にある淡江大学において開催された2025年日本人文知国際シンポジウム並びに国際啄木学会台湾大会に参加した。大会においては、韓国から参加した梁東国(リャン・トゥングック)祥明大学教授が「韓国における啄木文学の受容は特殊なるものであったか。」、邱若山・静宜・東呉大学(非)教授が「日本文学史教科書における近代詩歌の引用例の教え方と翻訳について」と題して基調講演を行った。日本、台湾、韓国の研究者が石川啄木に関する研究発表を行う貴重な場に立ち会うことができた。私からは、日本台湾交流協会では、2024年3月には「台湾短歌大賞」、また、2025年4月には文化講座「台湾の短歌を語る」を開催したことを紹介するとともに、様々な形で日本と台湾の間の文化交流が深まることを期待していることを述べた。
国際啄木学会のホームページによると、同学会は、1989年12月に創設されて以来、石川啄木に関する国際的な研究交流を積極的に進めてきているようである。特に、台湾の啄木研究者との間では深い交流が行われてきたようである。今回の大会における国際啄木学会会長の挨拶はこのことに触れている(挨拶文は国際啄木学会のホームページにも掲載されている)。
今回の国際啄木学会は今から36年前の1989年、その年の12月に設立されました。その最初期から、ここ淡江大学の林丕雄先生が学会に参加されておりました。本日は林丕雄先生の奥様がこちらにご来場されています。たいへん優れた啄木研究者でもあられた林先生のご尽力により、早くも2年後の1991年11月には、第二回大会として台北大会を淡江大学で、国際啄木学会は開催しております。このようなご縁もあり、国際啄木学会に参加する研究者が台湾にはつねに10名前後おられ、現在も8名の会員が在籍しています。1991年台北大会の後も、台湾では2002年に高雄大会(高雄第一科技大学)、2012年に台北大会(台湾大学)、2014年には南台国際会議(南台科技大学)と、合わせて4回の大会・国際会議を開催してきました。それほどここ台湾は、国際啄木学会が学術交流を重ねてきた、なじみ深い地です。
邱若山教授の基調講演「日本文学史教科書における近代詩歌の引用例の教え方と翻訳について」では、邱若山教授自身による日本の近代詩歌の中国語訳が試みられている。特に興味深かったのは、短歌を中文に訳す際には三連に分けると訳しやすいという指摘だった。これは啄木に限らないことであるようだ。邱教授が啄木の短歌を翻訳することを通じて感じられた苦労について予稿集に書かれているのでここに引用しておきたい(29頁)。
(前略)言葉遣いにおいて、例えば同じ語彙であっても「いのちなき砂のかなしさよ」と「函館の青柳町こそかなしけれ」「かなしきは小樽の街よ」では、「かなしさよ」「かなしけれ」「かなしきは」は違った意味合いがしていて、同じく「悲哀、哀傷、悲傷、傷心」などの言葉で、一律理解し翻訳したりすることは出来ない。「かなしけれ」に懐かしさが、「かなしきは」に同情の気持ちが入っている。
また、「ふるさとの訛りなつかし/停車場の人ごみのなかに/そを聴きにゆく」(煙48)で「ふるさとの訛り」を第三行で啄木は簡潔に代名詞「そ」を使って、言葉の重複を避けている。翻訳において、「訛り」を「郷音」や「口音」にしたら、「郷」や「音」の字が二度使われ重複の嫌いがある。「懷念故郷的腔調/至(上野)車站的人群裡,去聽那口音」と訳してみた。「砂山の沙に腹這ひ/初恋の/いたみを遠くおもひ出づる日」(我06)では「日」のことを詠み、「初恋のいたみ」の日を指して詠んでいるのではない。試みに「那一天/我趴在沙丘子上/遙憶初戀的痛」と翻訳した。また、「いたみ」は現代中国語だと「疼痛」「心痛」「苦痛」「傷痛」「痛苦」などの二字語になりがちで、かえって意味の制限になる。「痛」の一時語でその理解の幅を持たせた方がいいと思う。
今大会では、淡江大学客座教授として在台している今福龍太氏が研究発表セッションの一つで座長をされていた。かつて読んだ今福龍太氏による<クレオール>についての論考を思い出した。クレオールとしての日本、クレオールとしての台湾について妄想が浮かんだ。
【参考】淡江時報(學習新視界 2025-04-27)
https://tkutimes.tku.edu.tw/dtl.aspx?no=59105
【執筆者プロフィール】
服部崇(はっとり・たかし)
「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)、第二歌集『新しい生活様式』(2022、ながらみ書房)。X:@TakashiHattori0
【「新しい短歌をさがして」バックナンバー】
【35】静宜大学を訪れて
【34】沖縄を知ること──屋良健一郎『KOZA』(2025、ながらみ書房)を読む
【33】「年代」による区分について――髙良真美『はじめての近現代短歌史』(2024、草思社)
【32】社会詠と自然詠──大辻隆弘『橡と石垣』(2024、砂子屋書房)を読む
【31】選択と差異――久永草太『命の部首』(本阿弥書店、2024)
【30】ルビの振り方について
【29】西行「宮河歌合」と短歌甲子園
【28】シュルレアリスムを振り返る
【27】鯉の歌──黒木三千代『草の譜』より
【26】西行のエストニア語訳をめぐって
【25】古典和歌の繁体字・中国語訳─台湾における初の繁体字・中国語訳『萬葉集』
【24】連作を読む-石原美智子『心のボタン』(ながらみ書房、2024)の「引揚列車」
【23】「越境する西行」について
【22】台湾短歌大賞と三原由起子『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022)
【21】正字、繁体字、簡体字について──佐藤博之『殘照の港』(2024、ながらみ書房)
【20】菅原百合絵『たましひの薄衣』再読──技法について──
【19】渡辺幸一『プロパガンダ史』を読む
【18】台湾の学生たちによる短歌作品
【17】下村海南の見た台湾の風景──下村宏『芭蕉の葉陰』(聚英閣、1921)
【16】青と白と赤と──大塚亜希『くうそくぜしき』(ながらみ書房、2023)
【15】台湾の歳時記
【14】「フランス短歌」と「台湾歌壇」
【13】台湾の学生たちに短歌を語る
【12】旅のうた──『本田稜歌集』(現代短歌文庫、砂子屋書房、2023)
【11】歌集と初出誌における連作の異同──菅原百合絵『たましひの薄衣』(2023、書肆侃侃房)
【10】晩鐘──「『晩鐘』に心寄せて」(致良出版社(台北市)、2021)
【9】多言語歌集の試み──紺野万里『雪 yuki Snow Sniegs C H eг』(Orbita社, Latvia, 2021)
【8】理性と短歌──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)(2)
【7】新短歌の歴史を覗く──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)
【6】台湾の「日本語人」による短歌──孤蓬万里編著『台湾万葉集』(集英社、1994)
【5】配置の塩梅──武藤義哉『春の幾何学』(ながらみ書房、2022)
【4】海外滞在のもたらす力──大森悦子『青日溜まり』(本阿弥書店、2022)
【3】カリフォルニアの雨──青木泰子『幸いなるかな』(ながらみ書房、2022)
【2】蜃気楼──雁部貞夫『わがヒマラヤ』(青磁社、2019)
【1】新しい短歌をさがして
挑発する知の第二歌集!
「栞」より
世界との接し方で言うと、没入し切らず、どこか醒めている。かといって冷笑的ではない。謎を含んだ孤独で内省的な知の手触りがある。 -谷岡亜紀
「新しい生活様式」が、服部さんを媒介として、短歌という詩型にどのように作用するのか注目したい。 -河野美砂子
服部の目が、観察する眼以上の、ユーモアや批評を含んだ挑発的なものであることが窺える。 -島田幸典