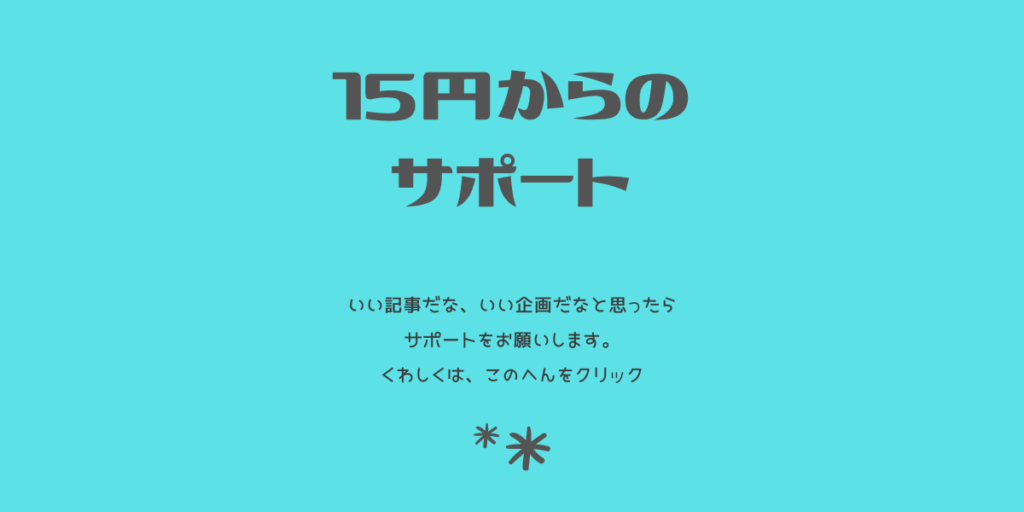人とゆく野にうぐひすの貌強き
飯島晴子
前に書いた、飯島晴子にとっての「畏れ」の対象について考えてみたい。
晴子は「鶯というのもなぜか私の好みの題材」と言う。ところが、実際には鶯の句は案外少なく、例えば春の季語では紅梅の句などの方が断然多い。同じ鳥でも、鶴・鴉・孔雀などの方が明らかに頻用されている。
〈鶯に蔵をつめたくしておかむ〉〈雨の上人うぐひす近すぎはせぬか〉〈容赦なき夏鶯の近さかな〉といった句から推測するに、晴子は、鶯が身近な存在であってはいけないと思っているようである。「実物の鶯というよりも、古典から続いて一つの様式のようになった鶯に惹かれる」と述べるように、鶯という大きくて遥かなる概念が、晴子の鶯の句を支えていよう。晴子の畏れの対象は、いわゆるアニミズム的なものにとどまらず、「古典から続いて一つの様式のようになった鶯」、その人工的できらびやかな概念にまで及ぶのである。
掲句では、隣にいる人の顔が薄れゆき、鶯の貌が強まってくる。近くにあってはいけない鶯の貌がありありと見えてしまった違和感、そこから生ずるおかしみが骨格になっている一句だろう。
なお、晴子は鶯を「春の穏やかな暖かさではなく、寒色の方に寄った引き緊まったイメージ」だと言っているのだが、実際には冬の鶯よりも春の鶯が、そして春の鶯よりも夏の鶯が句の数としては多い。これについては、また別に書こうと思う。
***
季語の本質はその即物性にはあるまい。季語は物ではなく言葉である。季語を季語たらしめるのはその様式、本意、象徴性だろう。有季俳句ではそこを重視すべきであるし、即物的な作り方は、むしろ有季俳句の本領ではないと私は思っている。
この時期になると私は毎年、鶯と菫の句を大量に作る。まず実際の鶯の声をきき、実際の菫をみることが原動力とはなるが、一旦走り出してしまえば、これらの季語のもつ様式だけで頑張れるのである。
(小山玄紀)
【執筆者プロフィール】
小山玄紀(こやま・げんき)
平成九年大阪生。櫂未知子・佐藤郁良に師事、「群青」同人。第六回星野立子新人賞、第六回俳句四季新人賞。句集に『ぼうぶら』。俳人協会会員
【小山玄紀さんの句集『ぼうぶら』(2022年)はこちら↓】
【小山玄紀のバックナンバー】
>>〔2〕やつと大きい茶籠といつしよに眠らされ 飯島晴子
>>〔1〕幼子の手の腥き春の空 飯島晴子
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】