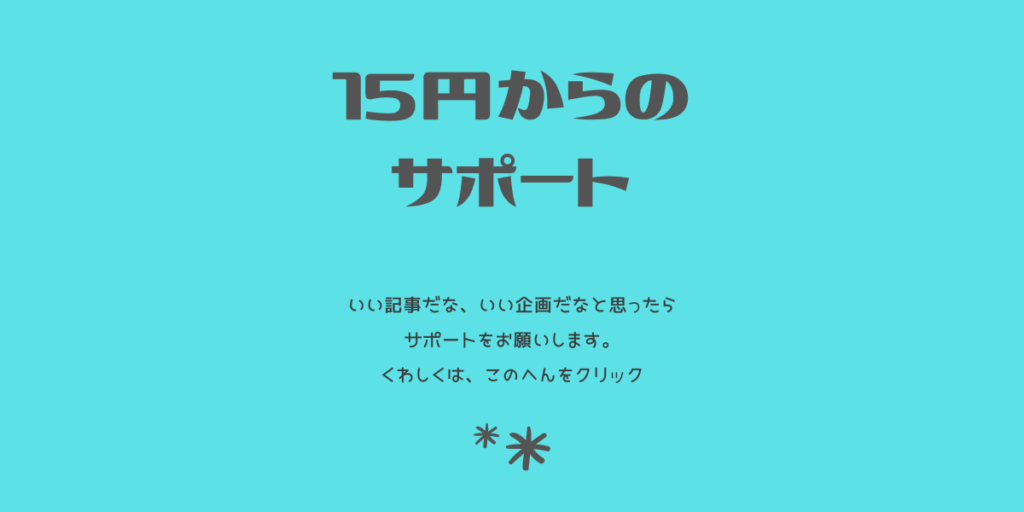【春の季語=初春(2月)】二月
「立春」は毎年2月3、4日ごろにあるので、新暦の「二月」は春の季語。
また、二月はもっとも短い月でもあるので、なんだか忙しいと感じることも多々。「二月が終わってしまった」という感慨を俳句では「二月尽」という言葉で表すことがある。
旧暦の一月(正月)は、現在の新暦の二月にあたることが多い(新暦の一月下旬となることもある)ので、「旧正月」も初春の季語となっている。
季語としては「にんがつ」と四音で用いることもあり、「二ン月」と表記することもある。
【二月(上五)】
二月の岬の社の四季ざくら 高濱年尾
二月や人の形見の絣着て 細見綾子
二月まだ夜明けの遅き伊予蜜柑 福田甲子雄
二月には甘納豆と坂下る 坪内稔典
二月絵を見にゆく旅の鴎かな 田中裕明
二月来る子どものをらぬ学校に 津川絵理子
【二月(中七)】
人のよく死ぬ二月また来りけり 久保田万太郎
詩に痩せて二月渚をゆくはわたし 三橋鷹女
畑に出ぬ日がちに二月すぐに来る 長谷川素逝
跳ばず教ふ二月障りのバレリーナ 田川飛旅子
眼帯や街に二月の風荒き 桂信子
兄逝きて二月たちまち了りけり 山田みづえ
何もなき二月と思へば霰降る 百合山羽公
鮒かさね煮る火も二月墓の母 宇佐美魚目
靴下を洗う二月の陽のように 対馬康子
【二月(下五)】
花の咲く木は閙がしき二月かな 支考
燕に賑ひそめる二月かな 蓼太
鴨減りて水のさびしき二月かな 樗堂
栴檀のほろほろ落る二月かな 正岡子規
水盤に麦の穂高き二月かな 富安風生
種の事に暦を見れば二月閏 大谷句佛
奥津城に犬を葬る二月かな 芝不器男
日の照れる石も愛しき二月かな 三好達治
葉牡丹の火(ほ)むら冷めたる二月かな 松本たかし
雲かぶる不二におどろく二月かな 久保田万太郎
腹水の水攻めに会ふ二月かな 野見山朱鳥
かはらけの宙とんでゆく二月かな 桂信子
登枚にあらがひの風澄む二月 成田千空
索道の松渡しをる二月かな 大峯あきら
忙しさのひとかたまりとなる二月 黒川悦子
断りの返事すぐ来て二月かな 片山由美子
みどりごの爪伸びやすき二月かな 堀切克洋
痛さうな私の体二月の眼 西生ゆかり
【二ン月】
二ン月や天神様の梅の花 小林一茶
二ン月の雪が山葵のみどりに降る 細見綾子
二ン月のペン胼胝うづく一行詩 高橋千賀子
二ン月や鼻より口に音抜けて 桑原三郎
【その他(日付順)】
汽車はしる二月一日絶景などへ 阿部完市
豆皿に塩豆二月二十日雨 藤田哲史
灰色の雪と見るにただならず二月二十六日 栗林一石路
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】