
Arab and Jew
walk past each other:
blind alleyway
Rick Black
2024年7月7日、ホテルグランドヒル市ヶ谷で開催された東京四季出版の第21回七夕まつりにおいて、「楽園」の堀田季何主宰が「現代世界の戦争俳句」と題して講演をした。その講演録は「俳句四季」2025年1月号にまとめられている。第12回俳句四季新人賞の授賞式も兼ねていたため私もその場におり、主宰の講演を目の前で聴いていた。掲句は、その時に紹介されていた句である。主宰の訳は、〈アラブ人とユダヤ人/すれ違う:/見えない袋小路〉。Rick Blackはアメリカのユダヤ人で、ニューヨーク・タイムズのイェルサレム支局などでのジャーナリスト活動を経て、現在は詩人、ブックアーティストとして活動しており、“Two Seasons in Israel: A Selection of Peace and War Haiku”(Turtle Light Press, 2024)などの句集を発表している(掲句もこの句集に収録)。Blackはジャーナリスト時代にパレスチナとイスラエルの衝突を目にし、それに対処する方法として、短い音節で多くの感情を伝えられる俳句に注目し、戦争それ自体を告発しようとする。
私は、第12回俳句四季新人賞の受賞スピーチで、パレスチナの現実に目を向けることを訴えた(そのときのことはnoteに書きました)。その直後での主宰の講演だったため、この句のことはよく覚えている。「blind alleyway」は、ユダヤ人とパレスチナ人が互いに目をそらし、どちらかの悪を告発するのではなく、問題が「袋小路」になっていること自体を告発する。
私は、正直、この句を受け止めきれていない。ガザで進行している虐殺にあらわれているパレスチナの抑圧は、イスラエルの植民地主義に端を発し、それが現在も持続している。イスラエルが一方的にパレスチナを抑圧してきた問題を、「戦争自体の告発」という形で表象してしまうことで、取り落とされてしまうものがあるのではないか。パレスチナの、長いあいだ抑圧されてきた弱い立場にある人々の声。そして、イスラエルによる加害の歴史。
俳句は短いが、その短さがかえって強力なイメージ喚起力を持つ。だからこそ、反戦教育に有用だと言われる。では、その反戦教育で、掲句のような句が用いられたらどうなるだろうか。戦争に至るまでの経緯を抜きに戦争自体を告発するような「反戦」の句は、その経緯で抑圧された弱者の声を透明化してしまわないか。ましてや、そのような形での「反戦」が加害国から発せられる場合は、むしろ世界を反戦とは真逆の方向へと進ませるようにも思われる。加害の歴史の忘却は、必ず次の加害を引き起こす。原爆による被害を中心にした反戦教育が東アジア・東南アジア諸国への加害の歴史に覆いかぶさってしまった今の日本、そこで横行する外国人差別を考えると、その懸念を抱かざるをえない。
戦争を告発する俳句は新興俳句以来あったが、白泉も赤黄男も、戦争は自分ごとであった。〈戦争が廊下の奥に立つてゐた〉や〈やがてランプに 戦場のふかい闇がくるぞ〉などは「反戦」というより「厭戦」というか、戦争が自分ごとであり自らの生が戦争に晒されているからこそ書けるものに感じられる。そして、戦時下で言論が制限されていた中で言葉によって表現するという力強さを思うと、言論の自由がある現代で「反戦」を叫ぶ俳句が白泉や赤黄男のような生の言葉の強度を得られるだろうか。戦争を地球規模で自分ごととして捉えて思いをはせるという姿勢も言われるけれども、地球規模で思いを馳せた結果が「戦争をやめろ」「戦争はこんなに悲惨」ではあまりにナイーヴだ。
いま私が俳句によって反戦を引き受けるとしたとき、キーワードになるのは「加害性」だと思っている。戦争は「人が死ぬ」のではなく、「人が人を殺し、人が殺される」。そういった加害性の現実を俳句の中で表現できなければ、安全圏から叫ぶ「反戦」俳句はとても空虚に響いてしまうだろう。
最後に、イスラエル軍による空爆で命を落としたガザの詩人Refaat Alareerが、亡くなる約一ヵ月前にTwitterに投稿した詩の書き出しを引用して稿を終えよう。
If I must die,
you must live
to tell my story
(もし私が死ななければならないなら/あなたは生きなければならない/私の物語を語りつぐために)
If I must die――Refaat Alareer (訳文:筆者)
https://x.com/itranslate123/status/1719701312990830934
(関灯之介)
【執筆者プロフィール】
関灯之介(せき・とものすけ)
2005年生れ。2020年秋より作句。楽園俳句会、東大俳句会所属。第1回鱗kokera賞村上鞆彦賞、第12回俳句四季新人賞、第3回楽園賞準賞。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
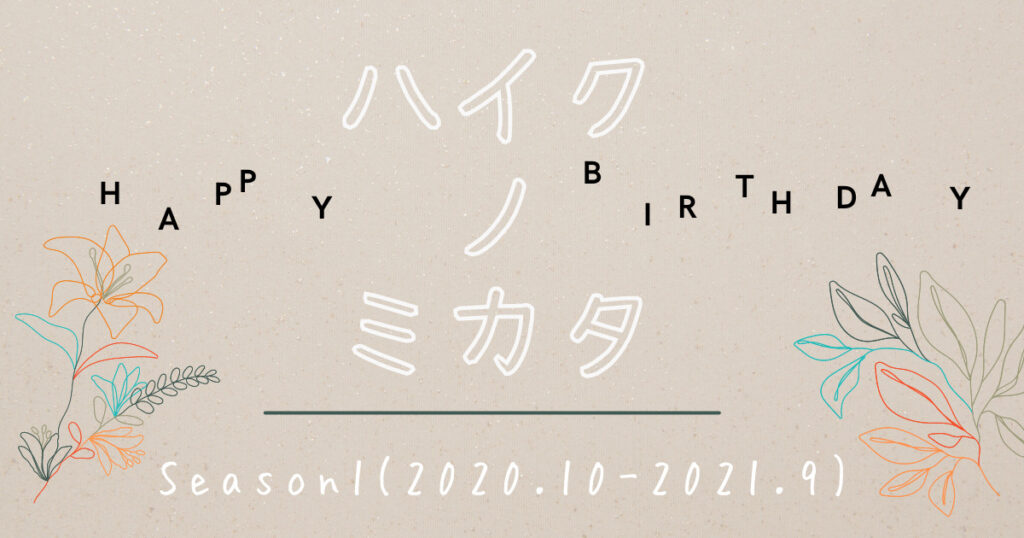
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
〔2月12日〕体内にきみが血流る正坐に耐ふ 鈴木しづ子
〔2月13日〕出雲からくる子午線が春の猫 大岡頌司
〔2月14日〕白驟雨桃消えしより核は冴ゆ 赤尾兜子
〔2月15日〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣
〔2月16日〕百合の香へすうと刺さってしまいけり 平田修
〔2月18日〕古本の化けて今川焼愛し 清水崑
〔2月19日〕知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる 村上海斗
〔2月20日〕銀行へまれに来て声出さず済む 林田紀音夫
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
>>〔4〕水涸れて腫れるやうなる鳥の足 金光舞
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
>>〔9〕をちこちに夜紙漉とて灯るのみ 阿波野青畝
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
>>〔9〕千駄木に降り積む雪や炭はぜる 車谷長吉