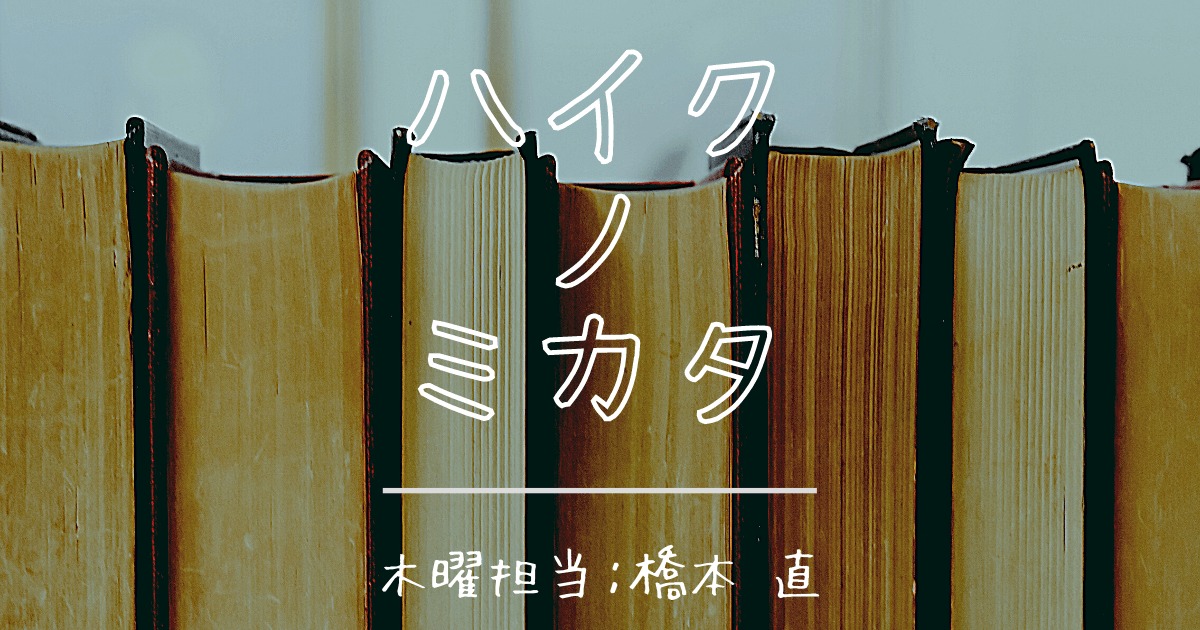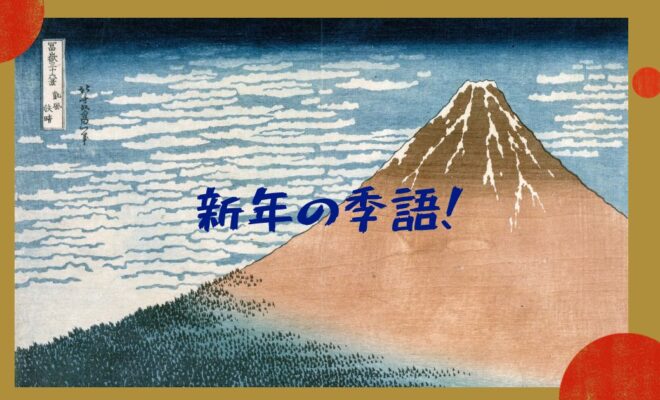天高し男をおいてゆく女
山口昭男
「天高し」という季語は、もともと「秋高くして塞馬肥ゆ」という杜審言の詩「蘇味道に贈る」のワンフレーズに由来する。
つまり、「馬肥ゆ」という景が省略されているわけだが、そこに馬がいるかどうかは別にして、やはり草原や花野のような「だだっぴろさ」を思う。
その広い空間で、女が男のもとを離れてゆく。もちろん、別れのような(貫一とお宮のような)劇的な場面とは限らない。
ただ、すたすたと離れて歩いていっただけ、という可能性もおおいにある。俳句としては、むしろ後者の「ごくありふれた景」のなかに、「天高し」という季語を配することで、何でもない動作が象徴性を帯びてくる。
なぜなら、人間は「天」から離れた低い「地」にいるからで、作者(男性)からすると、「女」は遠く理解の及ばない「天」にいるようにも感じられるからだ。
つまり、水平性(というか遠近感覚)が垂直性のアナロジーとして、語られている。
ちなみに、西村和子がこの句を評して「これからの女はこうあらねば(笑)」と言っているのだが(『2020年度版 俳句年鑑』230頁)、それはあくまで「天」からの発言であり、「地」にいる男からすると、ただただ女という存在を遠く、遠く見上げるばかりである。
(堀切克洋)



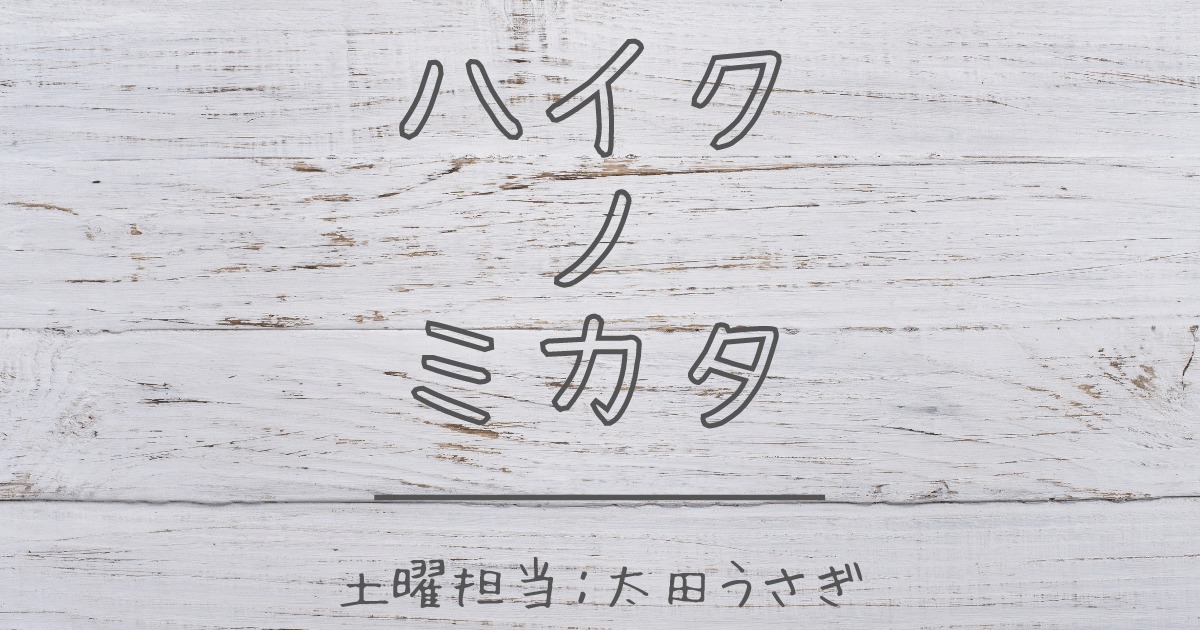







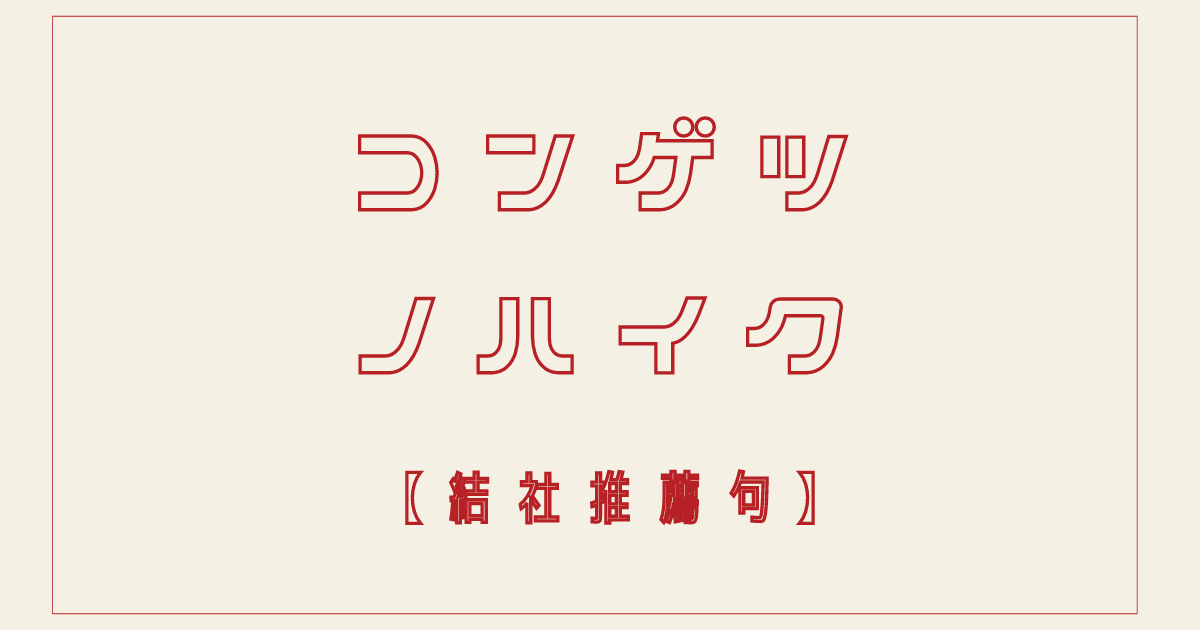

.png)