
古本の化けて今川焼愛し
清水崑
作者は1912年長崎県生まれ、1974年没。漫画家としての活躍が有名だが、随筆等幅広く活動。姉夫妻は俳人で妻は歌人という環境で、本人も三十歳ごろに作句を開始し、「寒雷」に同人として投句するなど精力的に取り組んだ。
掲句の魅力は、なんと言っても愛らしい人間味である。主体は読み終えた本を売るなりして、そのまま今川焼を手にしたというのである。半永久的に保存できる本と、刹那的な娯楽である今川焼の対比が目立つ。それぞれの乾湿、温度もまた対極的だ。
加えて、動詞・形容詞が主観的な点がこの句の主体の人間性を想像させるための大きな働きをしていることに注目したい。擬人法の「化けて」は薄らとした後ろめたさを茶化しているようにも見えるし、「愛し」はまっすぐすぎるほどまっすぐで、小さく丸く、湯気を放つ今川焼に向き合う姿が見えてくる。笑顔か、もしくは紳士的に、喜びを押し込めた真顔でいるのかもしれない。
ところで、「風流」の対義の「俗物的」は、俳句の世界に於いて、しばしば褒め言葉で、しばしば貶し言葉である。俗物的な俳句は概ね、掲句のように人間の欲求に基づく行為や、金銭にまつわることを題材としている。句会の場などで否定的な意味合いを強めて使うときは、時事や既視感のある若者像、恋愛像に向けられていることも多い。
和歌をルーツにする短歌よりも、俳諧をルーツにする俳句の方がより俗物的な要素は歓迎されているようにも見えるが、私は現代社会がより俗っぽさを求めているのではないかと考える。所謂風流な、雄大な題材は詠み尽くされたり、環境の変化によって過去のものとなったりと現実味を失い、身近にあるものを手繰り寄せた詩歌は自然と「俗物的」と呼ばれていた方向へ変化してきているのではないか。
ちなみに、私は句作の際に上品な俗っぽさを志している。主体に係る動詞は人間の営みそのものであり、生きること、生きていることを表現する上で、写生句にも大切な要素だと思っているが、ひとたび品を失えばナルシシズムが前面に押し出され、読者の嫌悪感すら買いかねない。もちろん磨き抜かれた語の選択が前提だが、掲句のような品性や愛嬌は、作者の人間性が醸し出しているのだろうか。知り合いの俳人たちが工夫している点があれば聞いて回りたいほどの、目下の課題である。
余談だが、短詩に取り組みはじめてから、詩を特に否定的な意味合いで批評するときの言葉をそれぞれ面白く思ったのを覚えている。先述の「俗物的」の他、切れがなく主述がまっすぐなときの「散文的」、詩情がありきたりなときの「牧歌的」などのことである。近年では、おそらく人称の非省略に関して、「JPOP的」などとも批評されているようだ。どれも場合によっては褒め言葉になりそうで、個人的にも成功していれば問題ないと思うが、これらの言葉で批評してきた先人たちが、ごく短い定型詩ならではの表現のどの要素に矜持を持ってきたのかが窺える。
なかなか形に残りづらいものではあるが、尊敬する俳人たちが俳句を否定するときに使った言葉をもっと知りたいと思っている。俳句とは何なのか、そこから大きな発見ができそうなのだ。俳句が座の文芸と呼ばれていて、句会に出ることが大切だと多くの人が説くのは、肯定以外の言葉を聞ける貴重な機会である、という面もあるのかもしれない。俳句の何が好きで、俳句で何をしたくて俳句を詠んでいるかを探っていきたい。
(野城知里)
【執筆者プロフィール】
野城知里(のしろ・ちさと)
2002年埼玉生。梓俳句会会員、未来短歌会会員。第12回星野立子新人賞、第70回角川俳句賞佳作。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
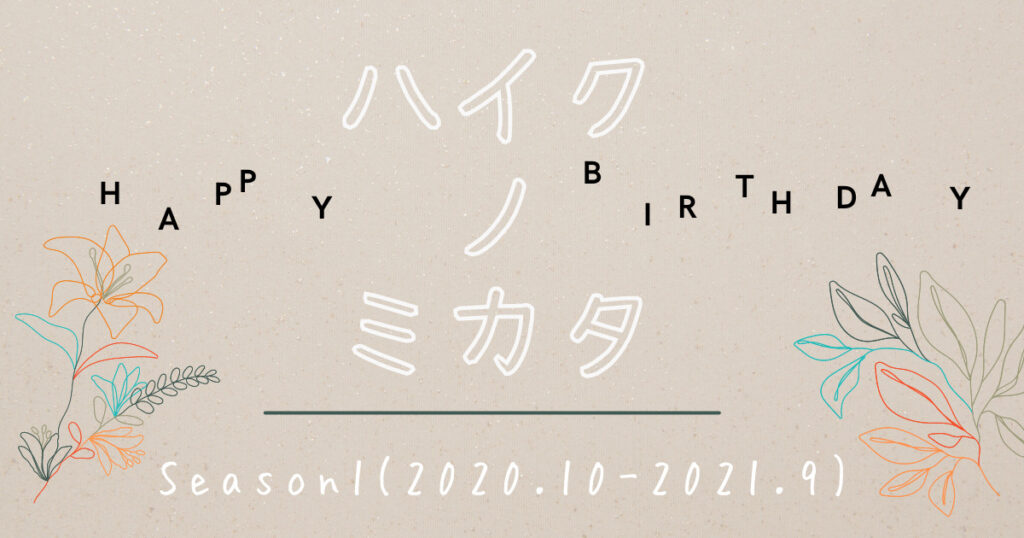
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
〔2月12日〕体内にきみが血流る正坐に耐ふ 鈴木しづ子
〔2月13日〕出雲からくる子午線が春の猫 大岡頌司
〔2月14日〕白驟雨桃消えしより核は冴ゆ 赤尾兜子
〔2月15日〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣
〔2月16日〕百合の香へすうと刺さってしまいけり 平田修
〔2月18日〕古本の化けて今川焼愛し 清水崑
〔2月19日〕知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる 村上海斗
〔2月20日〕銀行へまれに来て声出さず済む 林田紀音夫
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
【2024年12月の火曜日☆友定洸太のバックナンバー】
>>〔5〕M列六番冬着の膝を越えて座る 榮猿丸
>>〔6〕去りぎはに鞄に入るる蜜柑二個 千野千佳
>>〔7〕ポインセチア四方に逢ひたき人の居り 黒岩徳将
>>〔8〕寒鯉の淋しらの眼のいま開く 生駒大祐
>>〔9〕立子句集恋の如くに読みはじむ 京極杞陽
【2024年12月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔1〕大いなる手袋忘れありにけり 高濱虚子
>>〔2〕哲学も科学も寒き嚔哉 寺田寅彦
>>〔3〕教師二人牛鍋欲りて熄むことあり 中村草田男
>>〔4〕今年もまた梅見て桜藤紅葉 井原西鶴
【2024年12月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔1〕いつの日も 僕のそばには お茶がある 大谷翔平
>>〔2〕冬浪のつくりし岩の貌を踏む 寺山修司
>>〔3〕おもむろに屠者は呪したり雪の風 宮沢賢治
>>〔4〕空にカッターを当てて さよならエモーショナル 山口一郎(サカナクション)