
出雲からくる子午線が春の猫
大岡頌司
大岡頌司は三行表記での句集は『利根川圖志』を最後として一行表記に戻り、『寶珠花街道』(端溪社、昭和54年)、『犀飜』(端溪社、昭和58年)、『稱鄕遁花』(端溪社、昭和61年)、『勿來』(端溪社、昭和63年)、『渤海液』(端溪社、平成3年)と句集を刊行した。掲句は『犀飜』所収。『犀飜』を製本した昭和58年は寺山修司、高柳重信の両氏が逝去した年であり、その二年前の昭和56年には、大岡頌司はすでに『俳句評論』を辞している。
出雲には天上を追い出されたスサノヲによるヤマタノオロチ討伐、因幡の白兎などオホクニヌシにまつわる神話など、様々な神話が伝わっている。そこから「くる」ものというと、出雲大社からそれぞれの国へと帰る神が想起されるだろうが、掲句において出雲から「くる」ものは子午線だという。子午線は赤道と直角に交わるように地球の両極を結んだ線で、地球の経度や時間の基準となっている。子午線が「くる」と言ったときに時間が進んでいるような感覚があるのは、地球の自転のイメージを伴うからだろう。「出雲からくる」という言葉が持つ移動のイメージと「子午線」の動き、つまり地球が自転するイメージが合わさるのに加えて、出雲という土地の神話的な時間と子午線が動く物理的な時間とが重ね合わされ、句に空間的・時間的な奥行が生じている。
もう一点、中七の「が」という助詞について。空間的・時間的なイメージの奥行の中で出雲から地球へとズームアウトしていく上五中七の視点が、下五で一気に「春の猫」にクローズアップされる。上五中七で作り出されるイメージの世界に言葉として「春の猫」がいきなり放り込まれる面白さもあるとは思いつつ、それでも読者は現実の恋猫の様子を想像するだろう。文法上は出雲から来た子午線「が春の猫」であったことが下五で分かるという構造だが、あたかも子午線「が」今まさに春の猫に化けたかのような印象を受ける。上五中七で神から子午線へとイメージが変容するが、「神帰り」という冬季語を踏まえると、下五「春の猫」と季重なりになる。しかし、「が」+体言止めの形が唐突に響くことで、神→子午線→春の猫という変容の過程ではなく、子午線が春の猫に変化した瞬間が強調される。また、「出雲から」帰ってくる神が中七で「子午線」となり下五で「春の猫」となるというと、一読イメージがどんどん転回していく句のように見えるが、その実イメージがしっかりと像を結ぶ句だろう。「春の猫」は恋猫、つがいを求め落ち着かない猫だ。思えば、イザナギとイザナミの国生みに始まりスサノヲとクシナダヒメ、オホクニヌシとスセリビメのように、上五の「出雲」が引き出す神話の世界は男女関係の世界である。出雲から帰ってきた地での猫の恋は、その土地に新たな神話を作る営みなのかもしれない。
前回の結びに「大岡頌司にとって一行表記は『故郷』への単なる回帰なのか、それとも新たな表現の選択だったのかを考えていきたい」と述べたが、大岡頌司が一行表記に戻った動機を考察するつもりはない(もしかすると誤解を生んでしまったかもしれない)。大岡頌司が『寶珠花街道』を刊行したのは彼の父親が逝去した月のことであったが、実際どのような意図で三行表記を手放し一行表記に戻ったのか、作品から完全に解明することはできないだろう。私の関心は、彼の俳句がどのように作られるかということではなく、どのように読まれるかというところにある。
多行表記を表現史的な進歩と見るなら、その功績は俳句に視覚的効果を強く求めたということだろう。視覚的効果というと、蛾を象る表記や傾斜という内容に合わせた字下げなど高柳重信にカリグラムの俳句があるが、ここで言いたいのは文字で何か形を表現することではない。改行そのものの効果、一句の中の「切れ」を物理的に可視化したということだ。これは大岡頌司よりも高柳重信の多行表記に顕著だ。
一句の中で切れは一つ、「や」「かな」「けり」などの切れ字を使うポイントを感動の焦点とする、ということが俳句のセオリーとしてよく言われる。一方で、切れ字によって作られる切れとは関係なく、一句の中の言葉は意味のかたまりで分解することができる。また、俳句は五七五という定型を内在しており、切れ字云々の前に上五中七間、中七下五間には軽い「切れ」が意識される。五七五、言葉の意味のかたまり、切れ字という三つの次元の異なる「切れ」を重ねたりずらしたりすることで、様々な効果を演出することができる。これは句またがりの技法など、一行表記でも用いられる。しかし、多行表記では、切れ字以外の「切れ」が改行によって強調される。例えば、高柳重信の〈まなこ荒れ/たちまち/朝の/終りかな〉などは、言葉の意味の次元における「切れ」を改行によって前面に出している。また、言葉の意味の次元での「切れ」は、韻文ではなく、散文的なものである。五七五という韻文のフレームに散文的な意味の「切れ」を流し込むことで生じる緊張感も、形式の効力を十分に駆使したものだ。
しかし、大岡頌司の三行表記俳句はこの「切れ」の効果の発揮がその本質ではない。彼の三行表記は五・七・五に合わせて改行する句が多く、その韻律は一行表記の俳句と同様に響く。一行表記の俳句を読むときも五・七・五の切れ目を少なからず意識しているはずで、五・七・五に合わせた改行はそれを多少強調するだけだ。高柳重信の多行表記のような、形式がもたらす緊張はあまり感じられない。
『抱艫長女』より
山姥に
また水櫛の
刻きたる
*
ふりかへる
長き尾が欲し
枯野驛
*
『利根川志圖』より
由緖なき
瓦一枚
飾りけり
前回表題の〈すこし動く/春の甍の/動きかな〉では二行目を隔てた春の甍の動きへの再言及という三行表記の効果を指摘した。しかし、ここにあげた句は三行表記である必然性があまりないようにも思われる。例えば、〈由緖なき瓦一枚飾りけり〉と一行にすると「飾りけり」に力が掛かった句になり、「にけり」の詠嘆がより強く響くだろう。一方で、三行表記では句の終止感が弱まり、それぞれの行がある程度独立して響く。そのため、どこか言葉に力が掛かりきらない感覚があり、一句の重心が定まらない浮遊感がある。その浮遊感ゆえ、「ただ事」とも言われかねない内容をそのままに受け入れられている。これらの句は、一行表記、三行表記それぞれにそれぞれの詩的効果がある中で、いま三行表記で提示されているに過ぎないのではないか。
『寶珠花街道』より
我はいま半圓形のましらだけ
扇よりひとさし指をはなしけり
瀧道にそれゆくことの始めかな
『犀飜』より
春曉になげしめぐらし百事如意
死も死んで輝くものに笊の水
花の木にむせて男女となりゐたり
一行表記に回帰してから出した二冊の句集より何句か抽いた。〈扇より〉句は一行表記がひと息に読まれることによって、扇から指を離したその瞬間が読者に伝わる。本稿の表題の〈出雲からくる子午線が春の猫〉がイメージの変化を瞬間に圧縮しているのも同様である。これを三行表記にしたならば、「はなしけり」の瞬間性が失われるとともに、指を離したという内容も相まって不安定な印象をより抱かせる。〈死も死んで〉句は、三行表記にすると「死も死んで」と「輝くものに」の間に間が生じ、より思索的な雰囲気が生じるだろう。一方、一行表記では、死という概念の死とその先の生の輝き、そして笊の水が一瞬で結びつき、象徴的な意味の詩的強度が増している。
また、『寶珠花街道』には初出は三行表記だった句が一行表記に改められて収録されている。例えば、「俳句研究」(昭和49年3月)初出の〈わが庭の/だいだらぼちも/かくあらむ〉は『寶珠花街道』では〈わが庭のだいだらぼちもかくあらむ〉と一行表記にあらためられている。三行表記では訥々と言葉にしているような印象の「かくあらむ」は、一行表記ではより語調が強く響き「だいだらぼち」をより堅牢に想起させる。
このように、大岡頌司の三行表記と一行表記はどちらかに必然性がある二者択一のものではなく、それぞれに効果がある中でどちらが演出されるかという選択のように思われる。大岡頌司の一行表記への回帰は新たな表現の獲得というより、並列な演出法の転換だったのではないだろうか。
最後に、一行表記で選ばれなかった演出の一つを示そう。
『花見干潟』より
朝がおよぼす戶袋に
をさめてはみる
今朝のこぎつね
*
『抱艫長女』より
あらじんの
らあんぷは
いらんかね
*
『利根川志圖』より
なみうらに
またたぐひある
ふじをみるかな
これらの句は三行という表記方法自体に体をあずけ、各行の長さを自在に伸縮させて軽妙な韻律をなしている。内容についても、〈あらじんの〉〈なみうらに〉に顕著だが、意味やイメージを書きこむというよりも空虚さをそのまま韻律にのせている印象だ。言葉の意味を強調せず、語感や韻律が残る。余白であったものを本質に据えることで生じる空虚さ。この空虚の領域では、何かが実ることはないのかもしれないが、無限にあそびつづけられるのではないかと、外山一機「ねえさん」(「俳句」2024年12月号)を読んで思ったのでした。
外山一機「ねえさん」より
あれはねえ
あれは雪見だいふくの
たましい
*
ああ
そうか
これは与えないほうの神様
(大岡頌司の俳句の引用は『大岡頌司全句集』(浦島工作舎、2002年)による。また、全句集の入手法について酒卷英一郎さんに相談したところ、ご恵投くださった。ここに深く感謝申し上げます。)
(関灯之介)
【執筆者プロフィール】
関灯之介(せき・とものすけ)
2005年生れ。2020年秋より作句。楽園俳句会、東大俳句会所属。第1回鱗kokera賞村上鞆彦賞、第12回俳句四季新人賞、第3回楽園賞準賞。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
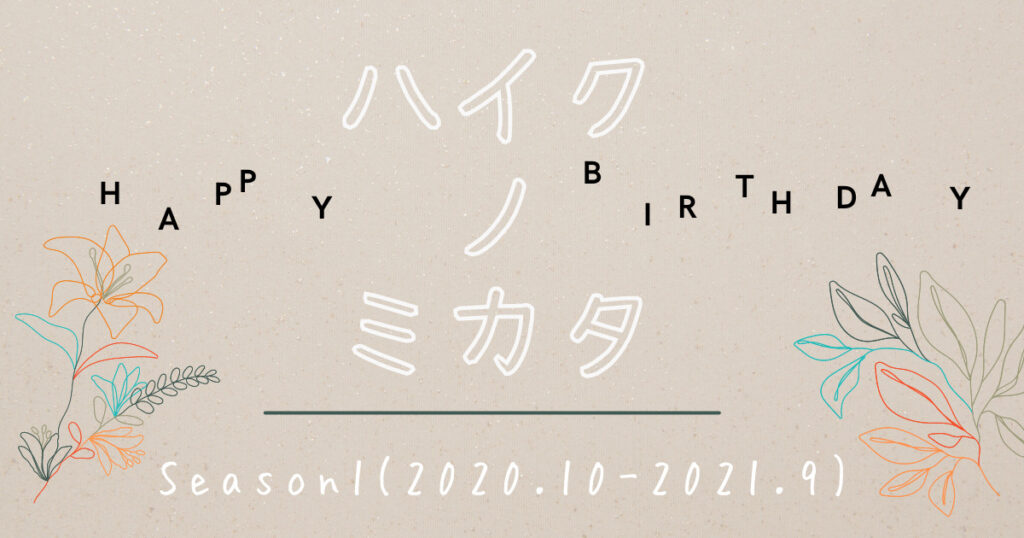
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
〔2月12日〕体内にきみが血流る正坐に耐ふ 鈴木しづ子
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
>>〔4〕水涸れて腫れるやうなる鳥の足 金光舞
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
>>〔9〕をちこちに夜紙漉とて灯るのみ 阿波野青畝
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
>>〔9〕千駄木に降り積む雪や炭はぜる 車谷長吉