
知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる
村上海斗
私が北海道の結社「雪華」に入会したのは、高校三年生のときだ。いくつもの結社を吟味して「雪華」に決めたわけではない。よきご縁があって入会したものと思っている。高校三年生の私が一人で「雪華」に入会するのは心細いものではなかった。たくさんの方々に面倒を見ていただいたり、句座を共にしたりして、そのご縁は今でも続いている。その中でも、私がひそかにロールモデルのように思っているのが、村上海斗さんだ。海斗さんのように俳句が上手になりたい、海斗さんのように振る舞いたいと、あこがれてやまない。本稿では、私の好きな海斗さんの句を、ひたすらに紹介したい。
海斗さんの句には、よく出てくるモチーフがある。まずはこれらの句を紹介しよう。
まだ地図は白紙の夜空星朧 「雪華」2020年7月号
ビーカーに一滴の空春夕焼 「雪華」2020年6月号
このような、空に関係する季語がよく詠まれる。「まだ地図は」の句は、何かまだはっきりしないものの、いくらかの希望をもって未来へ進んでいく、そのための準備期間にいるという感じがする。「ビーカーに」の句は、手元にあるビーカーの小さな水滴と、空全体の空気が一体となるような感覚がある。句の構造は二句とも似ていて、「地図は白紙の夜空」である、「ビーカーに一滴の空」がある、と断定するところに詩がある。そういうものの見方があるのだと驚かされる。単に美しいだけの句ではなく、新しい発見を詠んでいるところが好きだ。
単に美しいだけではない空の句は、他にもたくさんある。
生き死にのやうに息する冬銀河 「雪華」2022年3月号
日本のとけきつた海星朧 「雪華」2020年4月号
夕焼の行きて地球が真つ二つ 「アジール」創刊準備号
「生き死にの」の句は、生き物が生きるための根源的な動作であるはずの呼吸を「生き死にの」と直喩したところに詩がある。それを「冬銀河」と取り合わせたのもよい。冬銀河は、痛いほどの寒さと結びつく。美しさと生命の極限は、近いところにあるのかもしれない。「日本の」の句は、発想の逆転が好きだ。日本という島国は、海に浮かんでいるのではない。海に「とけきつ」ているのだと、この句は詠む。当たり前すぎて意識したことのないような事柄を、逆転の発想によって俳句に仕立て上げる……自分もやりたいものだと常々思う。「夕焼の」の句も、「地球」という大きな事柄と取り合わせている。地球が自転しているから夕焼が生まれ、夜になっていくのではない。季語「夕焼」が地球の上を進んでいくから、地球が昼と夜に「真つ二つ」に分かたれるのだ。
また、「日本の」にも出てくるように、海もモチーフに多い。
レモン水海から陸へ浮く身体 「雪華」2021年9月号
海が夢ならば都会は大枯野 「アジール」第3号
「レモン水」の句は、「身体」の描き方が好きだ。浮力のことを「海から陸へ浮く」と言っているのかもしれないし、生命が海から陸へと進化していった歴史を含意しているのかもしれない。「レモン水」と取り合わせるところに、海斗さんの句だという雰囲気を感じる。「海が夢ならば」の句は、一般的ではないことを断定したのがよい。海に夢を感じ、都会は「大枯野」だと言ってのけた。空にしろ海にしろ、俳句に詠もうとすると綺麗になりすぎて、詩らしくなくなったり、類想になってしまったりする。それを海斗さんは、いつもいつもワンダーをもって俳句に詠んでいる。これらの空や海の句は、読む人をあっというまに海斗さんの世界に引きずり込む。
さらに引きずり込まれるのは、ユニークな断定や因果関係の表現の力である。
知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる 「雪華」2022年3月号
本稿のタイトルに掲げた「知恵の輪」の句は、助詞「ば」の力が遺憾なく発揮されている。そこに明確で客観的な因果関係があるのではない。でも、そのように感じたのだという説得力がある。空間認識能力が低い私は、知恵の輪がひじょうに苦手だ。いくら解こうとしても全く解けない。そこに飽きっぽさも加わって、自力で知恵の輪が解けた経験はほとんどない。知恵の輪が解けた数少ない経験は、諦めて雑にカチャカチャ触っていたら、知らぬ間に解けていたというものだ。ああ、二月という、一年で最も短いこの月も、そうやって知らぬ間に終わっていくのだ。多少の満足感や達成感と、もう少し何かできたのではないかという後悔を残して。
最後に、海斗さんの句の中でときどき見られる、リフレインや対句表現を使った句の中で好きなものを挙げる。
初恋はマフラーほどくやうな恋 「雪華」2020年4月号
淡雪の甘さビブラートの甘さ 「アジール」創刊準備号
猫は死がわかる秋刀魚は骨となる 「アジール」第8号
秋刀魚焼く脳死確認せずに焼く 「雪華」2019年11月号
「恋」「甘さ」を詠んだ先の二句も、「秋刀魚」と「死」を詠んだ後の二句も、モチーフは対照的ながら、大好きな句たちだ。高校生のときの私が直面した課題は、「空や海を詠むと綺麗になりすぎる」の他に、「恋愛を詠むと甘ったるくなりすぎる」というものもあった。そこで海斗さんの句を読むと、どうだろう。「恋」や「甘さ」をダイレクトに詠み込みながら、少しも甘ったるくなく、ここちよい余韻の残る句になっている。「秋刀魚」と「死」を詠んだ二句もそうだ。「死」をダイレクトに詠み込みながらも、句から受け取る雰囲気は、死の悲しさとか死の恐ろしさといったものに終始しない。身近なところにある死を、諧謔性をまとわせて詠んでいる。これらの句は、対句表現が効いているからこそ、凡庸な恋愛や死の句のレベルにとどまらず、読み手の心に訴えかける力がある。
以上、私の手元にある「雪華」誌と「アジール」誌から好きな句を抜き出して紹介してきた。私が高校生のときから嵌り続けている海斗さんの世界に、誰か一人でも引きずり込むことができたら嬉しい。
(島崎寛永)
【執筆者プロフィール】
島崎寛永(しまざき・ひろなが)
2002(平成14)年、北海道札幌市に生まれる。2017(平成29)年、俳句を始める。2019(令和元)年、雪華に入会。2020(令和2)年、大学進学のため茨城県へ。ポプラに入会。2025(令和7)年、雪華同人。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
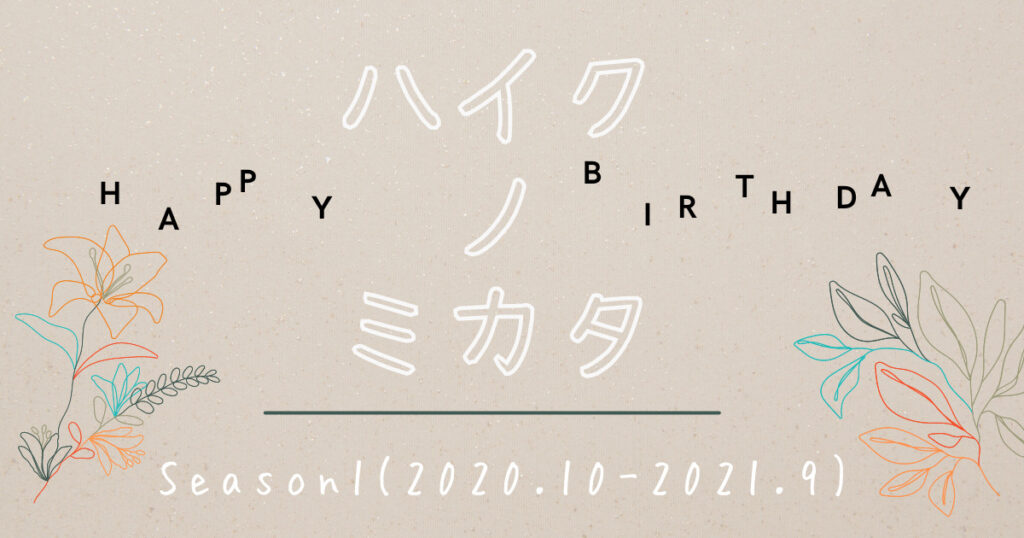
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
〔2月12日〕体内にきみが血流る正坐に耐ふ 鈴木しづ子
〔2月13日〕出雲からくる子午線が春の猫 大岡頌司
〔2月14日〕白驟雨桃消えしより核は冴ゆ 赤尾兜子
〔2月15日〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣
〔2月16日〕百合の香へすうと刺さってしまいけり 平田修
〔2月18日〕古本の化けて今川焼愛し 清水崑
〔2月19日〕知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる 村上海斗
〔2月20日〕銀行へまれに来て声出さず済む 林田紀音夫
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
>>〔4〕水涸れて腫れるやうなる鳥の足 金光舞
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
>>〔9〕をちこちに夜紙漉とて灯るのみ 阿波野青畝
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
>>〔9〕千駄木に降り積む雪や炭はぜる 車谷長吉