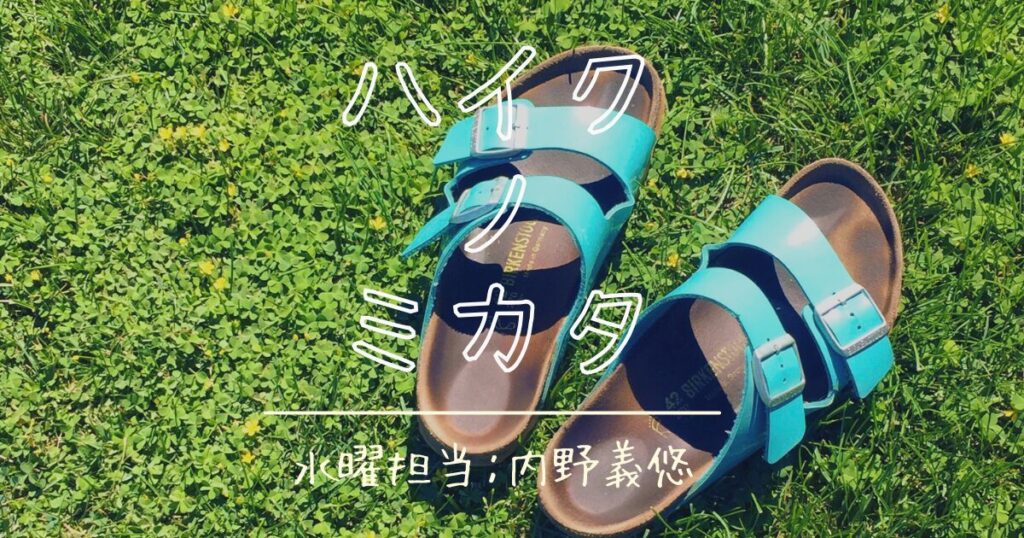
知り合うて別れてゆける春の山
藤原暢子
今回『ハイクノミカタ』の執筆の機会を頂いて、さて何を書こう?と悩んだ。
担当回を貫く何らかのテーマがあっても良いのかなと思い、今の自分にとって関心のある事柄にまつわる俳句を取り上げてみることにした。すなわち「馬」と「旅」である。
このうち「馬」に関しては、既にセクト・ポクリットの中で笠原小百合さんが『競馬的名句アルバム』という不定期連載を執筆されているので内容重複の可能性も鑑みそちらにお任せすることとして、ぼくは今回「旅」をテーマとした俳句を鑑賞してゆきたいと思う。
奇しくも今年、学生時代から続けている日本分割一周の旅が十五年目を迎えた。句歴がようやく七年目なので、俳句の倍以上の期間を旅のことを考えつつ生きてきたということになる。
その間大小あわせて二百近い旅を経て、残る目的地は三ヶ所(網走~オホーツク海沿岸~宗谷岬、奄美大島、八重山諸島)のみとなった。
やや大袈裟な表現とはなるが、ここまでくると人生(或いは生き方)とも切り離しがたくなってくる面もある。
せっかくなので今回の執筆を良き機会ととらえ、俳句を通じて自分の人生に密に根付いた「旅」というものが何なのか、改めてゆっくり考えてみたいと思う。
ひとつの趣味という意味では私的なテーマだが、旅とは普遍性を持つ行為でもあると思うので、しばらくお付き合い頂けるとうれしい。
さて、前置きが長くなったがそろそろ句の鑑賞に移りたい。
知り合うて別れてゆける春の山 藤原暢子
掲句、直接的に「旅」を詠んだ句ではない。しかし、そこには一期一会という旅の本質が間違いなく詠み込まれている。
この情感は、旅の中でその土地の人々や、たまたま目的地を同じくした旅人との交流を経験したことのある人には大いに共感してもらえるものだと思う。
人生の中でのほんの一瞬、わずかに重なるだけの旅先での出会いは、前提として「別れ」の上に成立している。そこには通り過ぎてゆくことでしか記憶として昇華されない儚さがある。
また、この句をさらに大きくとらえるならば、中七までの措辞は日本に於ける「春」という季節の象徴的な場面であるとも読める。
卒業や入学、就職などに代表されるような様々な生活環境の変化を理由とする「出会い」や「別れ」は、日本人にとってこの季節をひときわ特別なものとしている。
だからこそ俳句作品としてそれを詠み込んだときには、読み手に過剰なセンチメンタリズムを感じさせてしまう危険性も孕んでいると言えよう。
しかしこの句に於いては、その「出会い」と「別れ」を春の山を往く道程の一場面の中に巧みに落とし込んで切り取っている。過不足のない平明な詠みぶりもあり、必要以上にベタベタとしていない。人生に於いても幾度となく繰り返される場面を、数多の生命の巡る「春の山」がやさしく大きく包み込んでいる。
掲句の作者である藤原暢子さんは第十回北斗賞を受賞された俳人としてのみならず、写真家としてもご活躍されている才人だ。
また、掲句の収録された句集『からだから』のあとがき冒頭に「旅が趣味なら、俳句やってみない?」という誘い文句で俳句を始めた、と書かれている通りの生粋の旅人でもある。
海外諸国にも造詣が深く、特にポルトガルにはしばらくお住まいになられていたこともあるという、まさにグローブトロッターだ。
暢子さんとは何度か句座をご一緒させて頂いたことがあるが、句会後の雑談などの折に暢子さんの口から語られる旅先でのエピソードや風景は、その句柄と同じくとても心地良く、そして広がりを持ちながらぼくの耳に響いてきた。
まさにぼくにとって暢子さんは、密かに私淑している「旅の先生」とも言える存在なのだ。
さて、『からだから』には暢子さんの旅の途中で生まれたと思われる作品が他にも数多く収録されている。その一部を抄出してみたい。
どこからを旅と呼ばうか南風 藤原暢子
夏至歩きたがる体をつれてゆく 同
草の絮飛ぶ行き先に迷ふとき 同
人日の山より人の村を見る 同
水温むところを今日の住処とす 同
旅つづくのも佐保姫のいたづらか 同
驢馬に道たづねてゐたる春野かな 同
花大根咲く今日からは風来坊 同
どの句をみても「さぁ旅に出るぞ!」といった力みが全く感じられない。まさに行雲流水といった空気の中にある。
それは暢子さんにとって、もはや旅が暮らしの一部として溶け込んでいるということの証左なのだろう。
その日歩き出せばそれが旅の始まりであり、日が暮れた頃に辿り着いた場所が目的地だ。
そして翌朝目を覚ましてまた歩みを続けるのも、或いはそこに留まるのも、全てをひっくるめて「旅」なのだということを暢子さんの俳句は教えてくれる。
「生きることそれ自体が旅」とでも言わんばかりのそんな境地に、今はただひたすら憧れるばかりだ。
(内野義悠)
【執筆者プロフィール】
内野義悠(うちの・ぎゆう)
1988年 埼玉県生まれ。
2018年 作句開始。炎環入会。
2020年 第25回炎環新人賞。炎環同人。
2022年 第6回円錐新鋭作品賞 澤好摩奨励賞。
2023年 同人誌豆の木参加。
第40回兜太現代俳句新人賞 佳作。
第6回俳句四季新人奨励賞。
俳句同人リブラ参加。
2024年 第1回鱗kokera賞。
俳句ネプリ「メグルク」創刊。
炎環同人・リブラ同人・豆の木同人。
俳句ネプリ「メグルク」メンバー。
現代俳句協会会員・俳人協会会員。
馬好き、旅好き。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
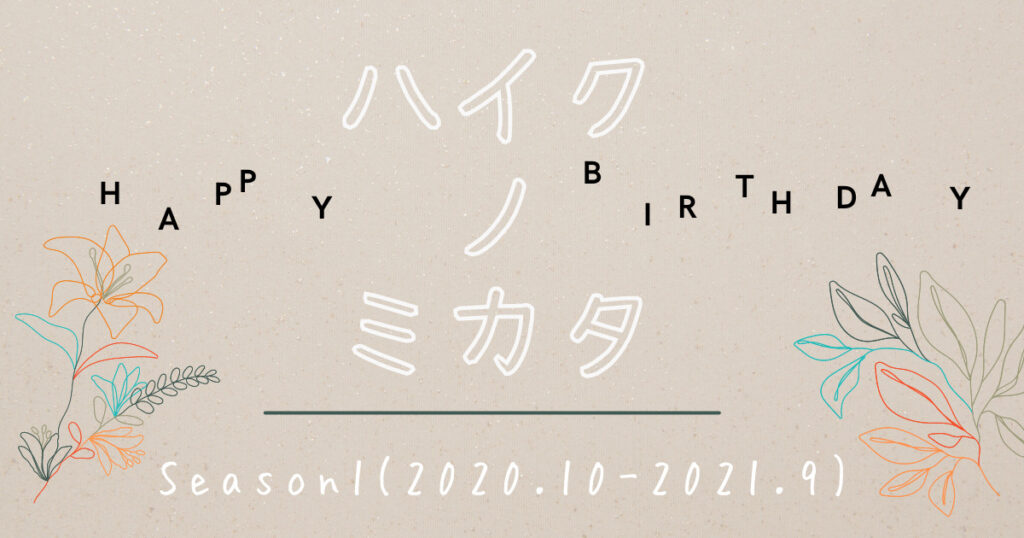
【2025年3月のハイクノミカタ】
〔3月1日〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理
〔3月2日〕どん底の芒の日常寝るだけでいる 平田修
〔3月3日〕走る走る修二会わが恋ふ御僧も 大石悦子
〔3月4日〕あはゆきやほほゑめばすぐ野の兎 冬野虹
〔3月5日〕望まれて生まれて朧夜にひとり 横山航路
〔3月6日〕万の春瞬きもせず土偶 マブソン青眼
〔3月8日〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子
〔3月9日〕木枯らしの葉の四十八となりぎりぎりでいる 平田修
〔3月10日〕逢ふたびのミモザの花の遠げむり 後藤比奈夫
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
〔2月12日〕体内にきみが血流る正坐に耐ふ 鈴木しづ子
〔2月13日〕出雲からくる子午線が春の猫 大岡頌司
〔2月14日〕白驟雨桃消えしより核は冴ゆ 赤尾兜子
〔2月15日〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣
〔2月16日〕百合の香へすうと刺さってしまいけり 平田修
〔2月18日〕古本の化けて今川焼愛し 清水崑
〔2月19日〕知恵の輪を解けば二月のすぐ尽きる 村上海斗
〔2月20日〕銀行へまれに来て声出さず済む 林田紀音夫
〔2月21日〕春闌けてピアノの前に椅子がない 澤好摩
〔2月22日〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨
〔2月23日〕私ごと抜けば大空の秋近い 平田修
〔2月24日〕薄氷に書いた名を消し書く純愛 高澤晶子
〔2月25日〕時雨てよ足元が歪むほどに 夏目雅子
〔2月27日〕お山のぼりくだり何かおとしたやうな 種田山頭火
〔2月28日〕津や浦や原子爐古び春古ぶ 高橋睦郎