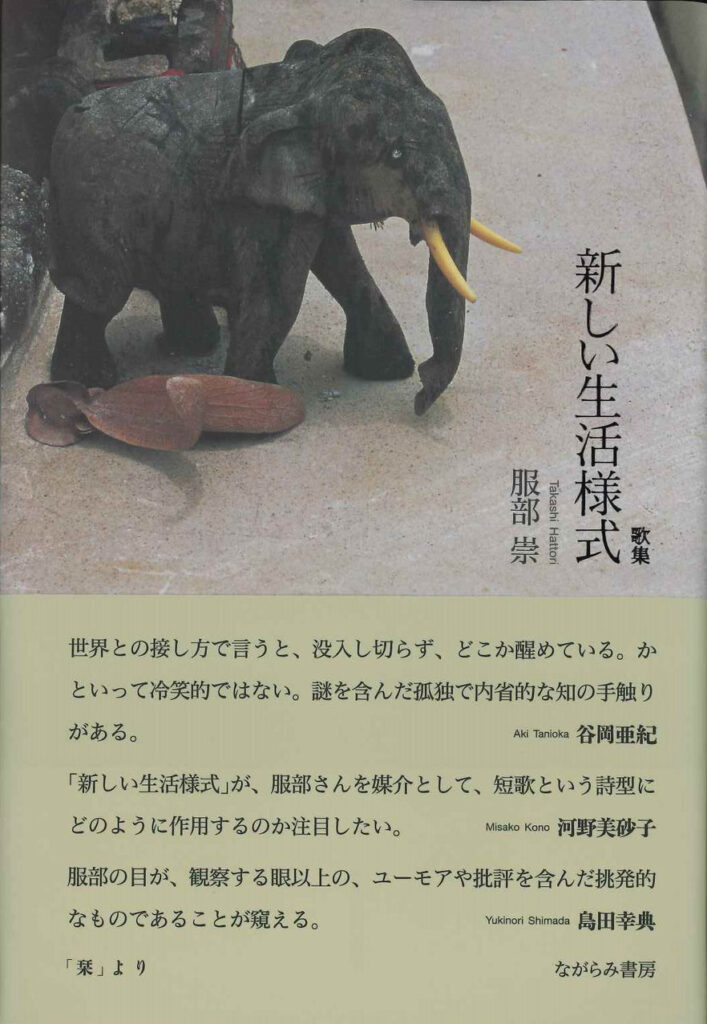毎月第1日曜日は、歌人・服部崇さんによる「新しい短歌をさがして」。アメリカ、フランス、京都そして台湾へと動きつづける崇さん。日本国内だけではなく、既存の形式にとらわれない世界各地の短歌に思いを馳せてゆく時評/エッセイです。
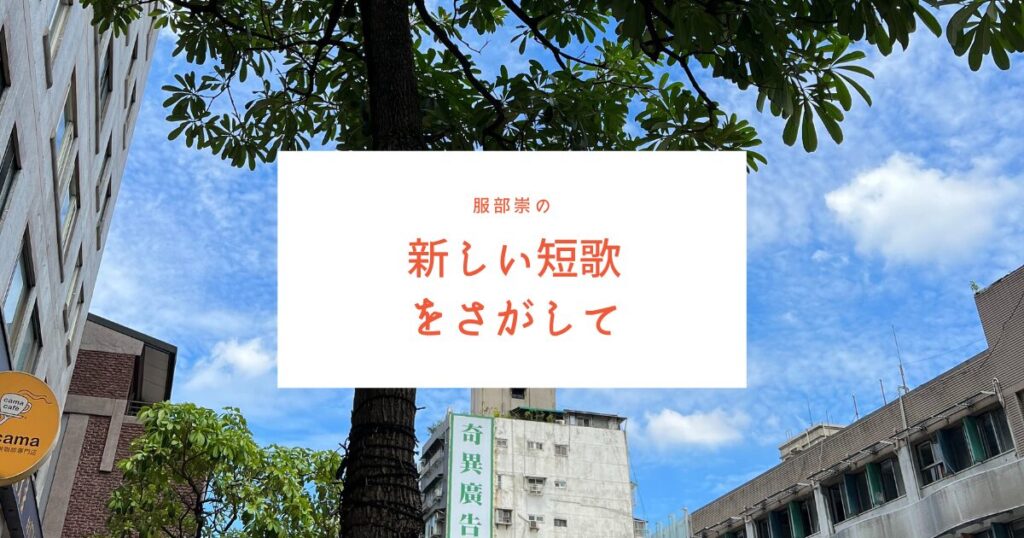
【第34回】
沖縄を知ること──屋良健一郎『KOZA』(2025、ながらみ書房)を読む
筆者は、沖縄を何度か訪れたことはあるが、沖縄の歴史を十分に知っているとは言いがたい。そのような中で、このたび、屋良健一郎の第一歌集『KOZA』を読んだ。筆者がコザを訪れた際に感じた街の雰囲気がこの歌集を読み進むうちに何度も思い出された。
同歌集の著者略歴には次のように書かれている。
1983年、沖縄県沖縄市に生まれる。2004年に竹柏会「心の花」入会、佐佐木幸綱に師事。2005年、「第5回心の花賞」受賞。2013年に東京大学大学院人文社会系研究科を単位取得退学、名桜大学国際学群講師となる。現在は名桜大学国際学部上級准教授。専門は日本史・琉球史。琉球の和歌・和文に関する共著に『訳注琉球文学』(勉誠出版、2022年)、『琉球文学大系24琉球和文学 上』(ゆまに書房、2024年)がある。
歌集の書名になっている「KOZA」は沖縄本島中部に位置する「コザ」を指しているのだろう。米軍が越来村の胡屋地区をKOZAと呼んだことをきっかけに、一般の人々もコザと呼ぶようになったらしい。コザ市は1974年4月に隣の美里村と合併し沖縄市となっている。コザ暴動(あるいはコザ騒動)は1970年12月に起こっている。
会うたびに「ロンタイノーシー」と笑みかける祖父母はKOZAの商人なりき
暴動を騒動と言い換える父 われをぶつことすらなくなりて
一首目では、祖父母が米軍の兵士に対し「ロンタイノーシー(Long time no see)」と「笑み」を浮かべて話しかける。二首目では、父がコザ暴動ではなくコザ騒動というよりマイルドな言い方を用いる。祖父母や父に対して批判的ながらも自省的に詠っている。
「勝つといいわねえ」の主語を探りながら諾いながら よける梅干し
花火待つ空は無垢なり「オスプレイ欲しい人?」と言われあまた手を挙ぐ
誰を許し誰を許さず 戦後民主主義の眼鏡をぼくらはかけて
一首目は、選挙の際の会話を題材とした一首。賛成派と反対派に分かれている。誰に投票しようとしているのかを探る様子が詠われている。二首目は、若者たちがギャグを楽しむ日常を切り取った。三首目では、戦後民主主義の教育を受けている自らおよび周りの人たちに視線が向いている。
無知こそが無傷の秘訣たる島にわれは戰もアメリカ世も知らず
アメリカをヤマトを責める沖縄に支配者たりし世は遠くて
これらの二首においては「世」に「ゆー」のルビが振られている。方言の力を感じさせる。沖縄の歴史が一首に重くのしかかっている。方言に関しては、次のような一首にも目がとまった。「ぬーでぃーちーちー」がどのような意味の方言なのかはわからないが、不思議と痛みが感じられる。
未遂なる愛を反芻しておればぬーでぃーちーちーしてくる夜半
まったく歯が立たなかったのは次の一首。
わわわYわわうとわるさわわぬYわわたつわくるわわさりわY
この一首について、栞に文章を寄せている中程昌徳は「歌の意味するところはすぐに汲み取れる」と書いている。沖縄に関する知識の度合いによって理解が異なってくるようである。栞に書かれている「歌の意味するところ」はここでは書かずにおく。
文化財保護法により「さん」付けの頃のメールは残しています
歌集の巻末の初出一覧によると、この一首の初出は「本郷短歌」創刊号(二〇一二年)である(手元に「本郷短歌」がないため、再確認はできていない。)。「文化財」としているのは自らのメールか、それとも相手のメールか。両方か。
以上、屋良健一郎『KOZA』からの十首選である。沖縄を知ることは屋良の短歌を理解することに役立つことは確かであろう。今回、沖縄に関する知識不足を深く認識した。沖縄を知ることに努めていきたい。

『KOZA』の語源・意味は諸説あって、正解がない、というのが定説である。
歌集のタイトルに『KOZA』を選んだのは、分からなさこそが沖縄の核心だという作者の思いがあるからにちがいない。父の沖縄、祖父の沖縄、さらには尚文子の沖縄、時代の違うそれぞれの沖縄の手前に、現在を生きる屋良健一郎の沖縄がある。本歌集は、その沖縄を多様な角度で歌い切った作者渾身の第一歌集である。
(帯文 佐佐木幸綱)
屋良健一郎歌集『KOZA』
ながらみ書房 、2025年
ISBN 978-4-86629-294-6
172ページ 2,750円(税込)
【執筆者プロフィール】
服部崇(はっとり・たかし)
「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)、第二歌集『新しい生活様式』(2022、ながらみ書房)。X:@TakashiHattori0
【「新しい短歌をさがして」バックナンバー】
【33】「年代」による区分について――髙良真美『はじめての近現代短歌史』(2024、草思社)
【32】社会詠と自然詠──大辻隆弘『橡と石垣』(2024、砂子屋書房)を読む
【31】選択と差異――久永草太『命の部首』(本阿弥書店、2024)
【30】ルビの振り方について
【29】西行「宮河歌合」と短歌甲子園
【28】シュルレアリスムを振り返る
【27】鯉の歌──黒木三千代『草の譜』より
【26】西行のエストニア語訳をめぐって
【25】古典和歌の繁体字・中国語訳─台湾における初の繁体字・中国語訳『萬葉集』
【24】連作を読む-石原美智子『心のボタン』(ながらみ書房、2024)の「引揚列車」
【23】「越境する西行」について
【22】台湾短歌大賞と三原由起子『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022)
【21】正字、繁体字、簡体字について──佐藤博之『殘照の港』(2024、ながらみ書房)
【20】菅原百合絵『たましひの薄衣』再読──技法について──
【19】渡辺幸一『プロパガンダ史』を読む
【18】台湾の学生たちによる短歌作品
【17】下村海南の見た台湾の風景──下村宏『芭蕉の葉陰』(聚英閣、1921)
【16】青と白と赤と──大塚亜希『くうそくぜしき』(ながらみ書房、2023)
【15】台湾の歳時記
【14】「フランス短歌」と「台湾歌壇」
【13】台湾の学生たちに短歌を語る
【12】旅のうた──『本田稜歌集』(現代短歌文庫、砂子屋書房、2023)
【11】歌集と初出誌における連作の異同──菅原百合絵『たましひの薄衣』(2023、書肆侃侃房)
【10】晩鐘──「『晩鐘』に心寄せて」(致良出版社(台北市)、2021)
【9】多言語歌集の試み──紺野万里『雪 yuki Snow Sniegs C H eг』(Orbita社, Latvia, 2021)
【8】理性と短歌──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)(2)
【7】新短歌の歴史を覗く──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)
【6】台湾の「日本語人」による短歌──孤蓬万里編著『台湾万葉集』(集英社、1994)
【5】配置の塩梅──武藤義哉『春の幾何学』(ながらみ書房、2022)
【4】海外滞在のもたらす力──大森悦子『青日溜まり』(本阿弥書店、2022)
【3】カリフォルニアの雨──青木泰子『幸いなるかな』(ながらみ書房、2022)
【2】蜃気楼──雁部貞夫『わがヒマラヤ』(青磁社、2019)
【1】新しい短歌をさがして
挑発する知の第二歌集!
「栞」より
世界との接し方で言うと、没入し切らず、どこか醒めている。かといって冷笑的ではない。謎を含んだ孤独で内省的な知の手触りがある。 -谷岡亜紀
「新しい生活様式」が、服部さんを媒介として、短歌という詩型にどのように作用するのか注目したい。 -河野美砂子
服部の目が、観察する眼以上の、ユーモアや批評を含んだ挑発的なものであることが窺える。 -島田幸典