
体内にきみが血流る正坐に耐ふ
鈴木しづ子
表現者であることは、鑑賞されることである。嫌な言い方をすれば、「好き勝手解釈されること」「好奇の目で見られること」でもある。
私は幼少のころから表現することが好きだった。字を書けない年からはちゃめちゃな物語をつくっては弟に聞かせ、隙あらば自由帳に絵を描き、ピアノを弾いて音楽に自分を乗せ、クラシックバレエを踊って全身で何かを表現しようとした。小説を書きたくて高校では文芸部に入った。様々に表現を続けてきた私が、初めて「鑑賞されること」を意識したのは、恥ずかしくも高校三年生のときだ。私は自衛隊を題材にした小説を書き、高文連の大会に提出した。支部予選で佳作をいただいたその作品に、審査員の一人から以下のような鑑賞文が寄せられた。
最後の6行を言いたかったと思うが、最後をもっと膨らませてほしかった。女子がこの細部を描けたのは素晴らしい。
この鑑賞文を読んだときのことを、私はよく覚えている。大会から数日か一週間くらい経ってからのことで、部員全員の各作品に対する鑑賞文を、部長だった私がまとめてどさりと受け取った。同期の部員とそれを仕分け、この鑑賞文は私ではなく同期が先に目にしたのだった。私の小説の内容も、佳作をとったことももちろん知っている同期は、この鑑賞文に目を通し、「女子が、ね」とぼそっと呟いた。仕分け作業が終わって教室に戻り、鑑賞文を読み直した。初読で、「女子が」を私は読み飛ばした。そういえば同期が何か言っていたなと思い返すと、「ジョシ」と言っていた気がする。助詞について触れた鑑賞文はないなと思いながら、もう一度読み直し、初めて私の脳内で「女子」と変換された。「この細部を描けたのは素晴らしい」と、この審査員は手放しに私を褒めたのではなく、私が「女子」だから褒めたのだと、初めて気づいた。高文連は、ペンネームではなく、本名で作品を提出する。普段の部誌ではペンネームで、高文連では本名で作品を発表することに、それまでの私は特に何も思ったことはなかった。しかしこのとき初めて、作品には自分の名前が連なり、それは私の作品に「女子の作品」であるという価値が付与されることであると気づいた。私が俳号を「島崎寛永」に決めたのは、そのころである。
前置きが長くなったが、これが、表現者であることは鑑賞されることであると気づいた、私の原体験である。そして、そのことをまた強く意識したのが、鈴木しづ子の句との出会いである。鈴木しづ子は、女性の立場から、身体感覚や男女の関係を詠み、その最後はよく知られていないミステリアスな俳人だと、それくらいの前提知識をもって私は『夏みかん酢つぱしいまさら純潔など』を手にとった。2019年に河出文庫から出ているこの本は、鈴木しづ子の第一句集『春雷』および第二句集『指環』の句を初めて文庫化し、さらに川村蘭太による評伝「鈴木しづ子追跡」を収録している。文庫の書名にもなっている〈夏みかん酢つぱしいまさら純潔など〉の句と、表紙になっているしづ子の、確固たる芯と美しさの表れた写真に強いインパクトを受けて、私はこの本を読んだ。そこで好きだと思った句の一つが、表題にした〈体内にきみが血流る正坐に耐ふ〉である。
1919年、大正の最後の年に生まれ、昭和の時代を生きたしづ子は、『樹海』主宰の松村巨湫に師事し、句歴わずか3年前後、21歳にして第一句集を出版した。その6年後に第二句集を出版し、直後に一切の消息を絶つ。第一句集を出したころ彼女は、ダンスホールの踊り子をしていたとか、娼婦をしていて一人のアメリカ兵と恋に落ちたと言われている。詳細を裏付ける証拠はないが、とにかく、川村の言葉を借りれば「夜の生活者」であったらしい。第一句集『春雷』に収録された句から、以下を引用する。
葉桜の幹の太きにある落暉
嫁く友のくちびるちさしつばくらめ
銹あらき鋳物の肌と夏草と
あきのあめ衿の黒子をいはれけり
くちびるのかはきに耐ゆる夜ぞ長き
煖房のおよばぬ隅に着更へする
この句群から、私はしづ子のミステリアスな側面とか、女性性をさほど強くは受け取らなかった。当初私がもっていたしづ子への印象よりも、卑近な身体感覚や人間関係と、季語との取り合わせの妙に感動し、その印象が強くあった。しづ子の人生を背景として鑑賞することもできるだろうが、それよりも、句一つ一つをじっくり鑑賞した方がよいと直感した。例えば、同じ「くちびる」を詠み込んだ句でも、〈嫁く友のくちびるちさしつばくらめ〉は、くちびるを客体化し、「つばくらめ」のせわしないくちばしを想起させるような句だ。それに対して〈くちびるのかはきに耐ゆる夜ぞ長き〉は、自分のくちびるを主観的に詠んだ句だと思う。くちびるが乾いた原因や、それに耐えながら夜長をどう過ごしているのだろうと、様々に想像させる。これらは「くちびる」という身体の部分を、季語と取り合わせて異なる視点から詩に仕立て上げた句だ。ここにしづ子の生き方や当時の状況を結びつける必要はない。もちろんそれも一つの読み方だが、それが読み方の正解ではないと思う。
次に、第二句集『指環』に収録された句から、以下を引用する。
体内にきみが血流る正坐に耐ふ
情慾や乱雲とみにかたち変へ
葉の蔭にはづす耳環や汗ばみて
雪こんこん死びとの如き男の手
菊は紙片の如く白めりヒロポン欠く
コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ
夏みかん酢つぱしいまさら純潔など
全体から、第一句集とは違う雰囲気が漂う。この句群を読んで私は、しづ子の生き方を背景として強く意識した。〈体内にきみが血流る正坐に耐ふ〉で詠まれた「きみ」とは恋人、または誰か肉体関係をもった男のことだろうと思った。自分の身体と男の身体の重なりをこのように熱情的に詠むのだ、そして下五ではその苦しさを、やはり身体感覚と結びつけて詠むのだと思った。
それから、この本の後半部分、川村の「鈴木しづ子追跡」を読んで、私は自分の鑑賞態度を反省することになる。それは、『樹海』誌の1948年7月号に掲載された、しづ子自身の自句自解である。孫引きで恐縮だが、一部を以下に示す。
仮令一瞬でもよい、體の支柱が、心の支柱が欲しい、欲しい、いまさらの如く、叛いていくとせ、血を分けたはらからが、したはしい。ああ母は、既にゐなかつたのだ! 母も――このやうに泪を流して私をこの世に送り出したのか。私も母とおなじみちをたどるのか。母よ、何故生きてゐてはくれなかつたのだ。私は訴へるところがないではないか。(中略)激しい感情の渦巻にもはや己れ一個のみではない血脈の流れはときには熱くときには冷たく明瞭な心音をひびかせてこの五體を壓迫しつづけてやまない。
この句の「きみ」は男ではなく、母であった。これは母を失ったしづ子の悲しみを激烈に表現した句であった。作者本人の自句自解を正解のように捉えることは必ずしも適切ではないが、しかし私は、この文章を読んで驚いた。そして、しづ子の人生を背景に、自分勝手な鑑賞をしていたことを反省した。自分のもっている情報と恣意的に結びつけて、私はただ一つの読み方を辿ることしかできなかった。他に読み方があるのだろうか、もっとこの句に広がりや深みはないだろうかと、考えることができなかった。そのことに私は深く反省した。その反省、すなわち作品そのものと作者の情報を身勝手に結びつけ、一辺倒の鑑賞しかしないという所業は、私が過去に受けたことのあるものであった。それを私は、気づかぬうちに自分自身がおこなっていた。
作品は、発表した瞬間に作者の手元を離れ、大海に放り出される。作品は鑑賞者の手に委ねられ、どんな鑑賞をも引き受けることになる。鑑賞者は自由であるが、作者の手元を離れた作品に対して、過度に作者と結びつけて鑑賞することは私は好まない。今も私は「女性らしい」とか「若者らしい」といった言葉と共に鑑賞を受けることがよくある。初めて会う人に「俳号を見て高齢の男性かと思っていたら、可愛らしいお嬢さんだったのね」と言われることもある。「女の格好をしている男性かと思った」と言われたこともある。そういう言葉たちに、どう向き合っていけばよいか、私は結論づけることができていない。これからも「表現する」ことを続けていくなかで、いつか結論が出るのかどうかもわからない。ただ、「鑑賞される」ことを考えるうえで、鈴木しづ子の存在は、一つの道しるべになるのではないかと、私は思っている。
(島崎寛永)
【執筆者プロフィール】
島崎寛永(しまざき・ひろなが)
2002(平成14)年、北海道札幌市に生まれる。2017(平成29)年、俳句を始める。2019(令和元)年、雪華に入会。2020(令和2)年、大学進学のため茨城県へ。ポプラに入会。2025(令和7)年、雪華同人。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
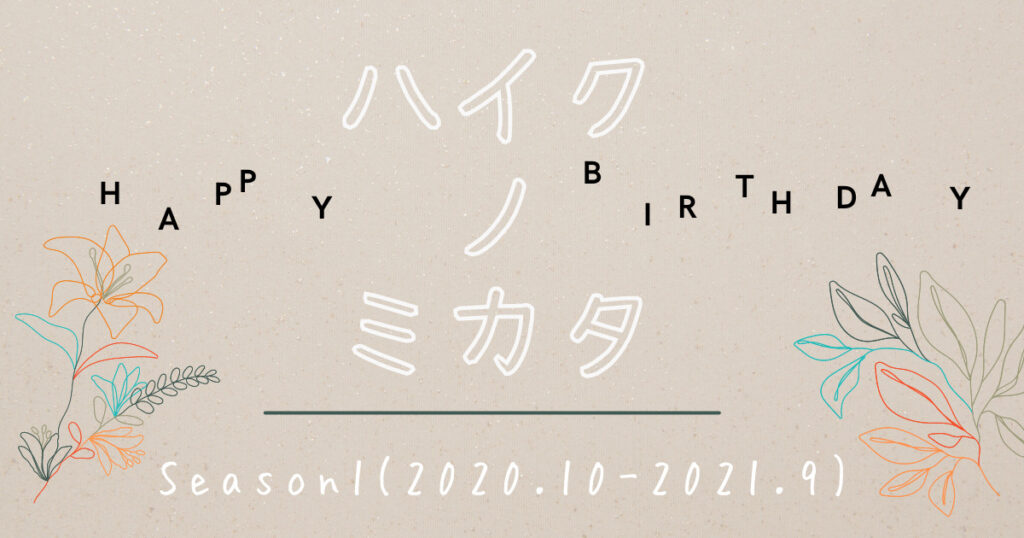
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗
〔2月8日〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明
〔2月9日〕はつ夏の風なりいっしょに橋を渡るなり 平田修
〔2月11日〕追羽子の空の晴れたり曇つたり 長谷川櫂
【2025年1月の火曜日☆野城知里のバックナンバー】
>>〔1〕マルシェに売る鹿の腿肉罠猟師 田中槐
>>〔2〕凩のいづこガラスの割るる音 梶井基次郎
>>〔3〕小鼓の血にそまり行く寒稽古 武原はん女
>>〔4〕水涸れて腫れるやうなる鳥の足 金光舞
【2025年1月の水曜日☆加藤柊介のバックナンバー】
>>〔5〕降る雪や昭和は虚子となりにけり 高屋窓秋
>>〔6〕朝の氷が夕べの氷老太陽 西東三鬼
>>〔7〕雪で富士か不二にて雪か不尽の雪 上島鬼貫
>>〔8〕冬日宙少女鼓隊に母となる日 石田波郷
>>〔9〕をちこちに夜紙漉とて灯るのみ 阿波野青畝
【2025年1月の木曜日☆木内縉太のバックナンバー】
>>〔5〕達筆の年賀の友の場所知らず 渥美清
>>〔6〕をりをりはこがらしふかき庵かな 日夏耿之介
>>〔7〕たてきりし硝子障子や鮟鱇鍋 小津安二郎
>>〔8〕ふた葉三葉去歳を名残の柳かな 北村透谷
>>〔9〕千駄木に降り積む雪や炭はぜる 車谷長吉