
無人踏切無人が渡り春浅し
和田悟朗
作者は1923年兵庫県神戸市生まれ。大学時代の恩師がきっかけで二十代後半に句作開始。橋閒石の「白燕」に入り、同時期に赤尾兜子選の毎日新聞神戸俳壇に投句開始。のちに「白燕」同人となったほか、高柳重信の「俳句評論」や赤尾兜子の「渦」に創刊同人として参加。後に「風来」を創刊・主宰。仕事の関係でアメリカはミネソタ州に家族とともに移住した三年ほどを除いて主に神戸を中心に関西に軸足を置いて活躍した俳人である。
掲句は第6句集『少閒』収録。「無人」のリフレインがぱっと目を引くのはもちろんのこと、まだ春の気配を感じにくい寒々とした踏切を見つめる詠者の寄る辺ない心持ちが伝わってくる魅力的な句である。
初読時はまず誰も渡っていない状態を「無人が渡り」という把握した捻り方を気に入って印をつけていた。私がこの句と出会ったのは森澤程さんの『和田悟朗の百句』(ふらんす堂)だったので、恥ずかしながら解説の段を読んで初めて「無人踏切」への違和感に気づいた。よくよく考えてみれば私は生まれてこのかた無人の踏切以外見たことがない。有人踏切はその名の通り人力で遮断機を上げ下げするもので、もう今ではほとんど見かけないがまだ稼働しているものもあるにはあるらしい。有人踏切は昭和36年頃から徐々に無人踏切と入れ替わりその数を減少させており、掲句が書かれた昭和59~64年頃にはおそらく昔懐かしい存在となっていたのではなかろうか。
有人踏切の話はともかくとして、私にはこの句を忘れられない理由がある。昨年、先述した『和田悟朗の百句』の勉強会に参加した際に掲句についてとある(生前の悟朗を知る)参加者から「この句について語るには兜子先生の死に触れないわけにはいかない」という旨の発言を受けたからである。赤尾兜子は昭和56年3月17日に兵庫県神戸市の御影駅付近の踏切にて急逝した。悟朗は兜子の葬儀委員長や「渦」雑詠欄の選者を兜子亡き後約9ヶ月ほどつとめている。データに明確に残っている発言ではないため私のうろ覚えで申し訳ないが、少なくとも私はその方の発言を耳にして掲句から得る感覚ががらりと変容した。
近年、作品への態度として詠者≠作者であるべきだという考えは特に若手の間ではマジョリティになったと言っても過言では無かろう。私自身そうあるべきだと思いながら他者の作品に接してきたがその一方で句によっては”誰が書いたのか”を意識した方が作品がさらに輝くこともあると考えたりもしており、先程の発言はその意識をさらに強めるきっかけとなった。
悟朗の句にはレトリックな句もいくつか見られたため掲句の眼目はあくまでリフレインのおもしろさにあり、少し不安定な手触りがあるのは季語「春浅し」によるものだと解釈していたが決してそうではないのだ。
悟朗句は〈少年をこの世に誘い櫻守〉など少年詠が多いのは有名だが、太平洋戦争や阪神・淡路大震災を経験しているほか10代のうちに父親を亡くしているためか死を意識した句も多い。
「無人」という言葉を目にする機会が最近増えた気がする。無人駅、無人改札、無人販売所、無人運転…。人手不足と技術躍進の賜物である。この便利で無機質なイメージの「無人」は掲句だと「無人踏切」の「無人」にあたる。では「無人が渡り」の「無人」はどうかと言うと単に人がいないという状態としての「無人」である。何を当たり前のことをと思われるだろうがどうかどうかこのままブラウザバックしないでもらえることを願う。前者の「無人」は「人力に頼らない」という意味合いでの「無人」だが、後者の「無人」はただ人がいないという状態を表しており似たような用法として「無人島」の「無人」があげられる。
だから何なんだと、全く同じ言葉を全く同じ用法で繰り返しても面白くならないからそりゃそういうずらし方をするだろうと言いたくなる気持ちもわかるが、結局私の言いたかったことは
①リフレインを用いたこと
②リフレインの対象が「無人」という言葉であったこと
③組み合わされる素材として「踏切」を選択したこと
上記の3要素のどれが欠けても掲句は成り立たなかったということである。
③についてあまり触れなかったが、生きれば生きるだけ日常で関わるありとあらゆる物事に辞書的な意味合い以外の何かが降り積るのだとしたら、見える世界は自分の中でもきっとどんどん変わるし、私には見えないものを人は見ているのだろう。目の前の作品を作者と切り離して読むということは読み手である私が私以外の誰ぞが書いた1行を通して私の感覚を取り出すという作業だとすると、それに対して作者の情報を乗せてその人の作品を読むことはいわば作者の目を借りようと精一杯試みることだ。ただ「作者の目を借りる」と言っても読み手の邪推にすぎず結局作者の情報を断片的にあてはめて読むことになるので薄っぺらく予定調和的な決めつけになりかねない危うさがあるのは否めない。それでも私はどちらの態度も忘れず読んでいきたい。作者のそれまでの生の全てがどんな形であれ現れていると信じたいのだ。
何だかありきたりで穏当な結論になってしまい、非常に恥ずかしい。
私は関西在住で特に関西愛があるという訳でもないが関西から離れる予定も気概も無いのでこれからもずっと関西で生きるのだろうと漠然と考えている。
それゆえ、次回以降も関西に縁のある俳人の作品をとりあげる予定です。
お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
(川田果樹)
【執筆者プロフィール】
川田果樹(かわた・かき)
2003年生。兵庫県出身。2019年に俳句甲子園をきっかけに句作開始。「麒麟」会員。関西大学俳句会「ふらここ」共同代表。第十八回鬼貫青春俳句大賞受賞。
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓
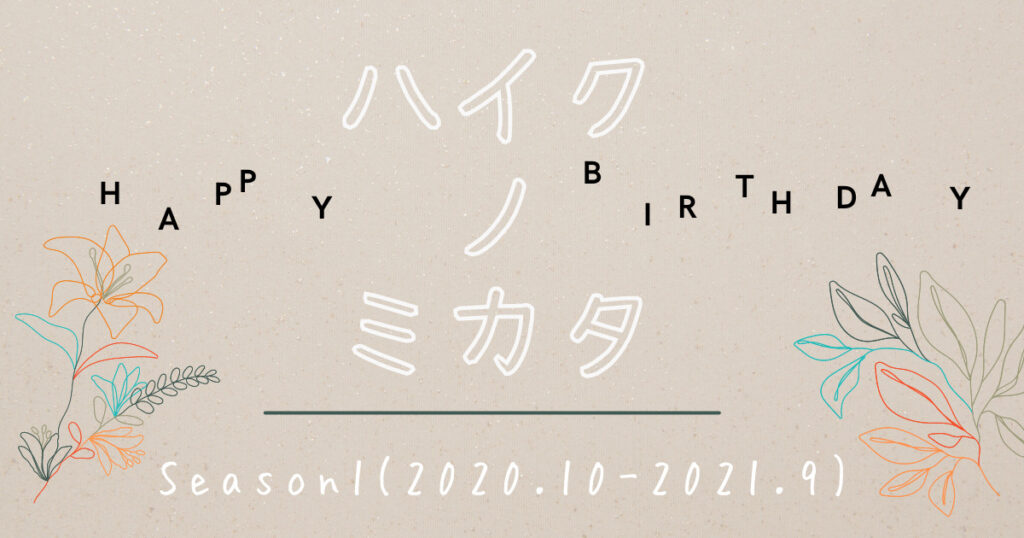
【2025年2月のハイクノミカタ】
〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子
〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修
〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直
〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎
〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子
〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司
〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗