
七夕や若く愚かに嗅ぎあへる
高山れおな
(『荒東雑詩』)
七夕は秋の季語である。現在は新暦の7月7日に行うため、夏に詠む人も増えている。仙台や一部の地域では、旧暦に合わせ8月に七夕祭が開催される。旧暦7月7日は新暦の8月半ば頃で、立秋を過ぎた夜は涼しい。天の川がくっきりと見え始める頃である。
七夕の行事は、古代中国の伝説に基づいており、万葉集の時代に漢詩とともに広められた。もともと古代日本には、神に捧げる衣を織り、神と一夜を過ごす棚機つ女(たなばたつめ)と呼ばれる巫女がいたため、その信仰と結びついた。七夕の日に裁縫の上達を願う乞巧奠(きっこうでん)も宮中に取り入れられ、冷泉家では現在も行なわれている。梶の葉に歌を書いて星に手向ける風習もある。いつしか笹の葉に短冊を結び願い事をする庶民の行事となった。江戸時代には、七夕の夜に向けて「笹売り」「短冊売り」が通りを行き交った。
万葉集の時代は、中国の文化を取り入れ、それを楽しむことが風流とされた。奈良時代に導入された暦に従って歌を詠むことは、政治的な意味合いもあった。七夕もまた、宮廷歌人によって広められた。詠み継がれてゆく過程で日本独特の七夕の思想が生まれてゆく。例えば、中国では牽牛(彦星)が鵲の橋を渡って織女に逢いにゆくのに対し、日本では舟を漕いで渡ってゆく。〈天の川霧立ちわたる今日今日と我が待つ君し舟出すらしも(『万葉集』巻九 藤原房前)。天の川に霧が立ったのは、彦星が舟を漕ぎだしたからだと詠まれている。〈この夕降りくる雨は彦星の早漕ぐ舟の櫂の散りかも(『万葉集』巻十 作者未詳)〉。彦星の櫂の雫により雨が降ったとも。
古代日本では、男女の逢瀬は月夜の晩に限られている。〈万代に照るべき月も雲隠り苦しきものぞ逢はむと思へど(『万葉集』巻十 柿本人麻呂歌集)〉。七夕の夜に月が雲に隠れてしまい逢えないことが詠まれている。現代でも雨が降ると二人は逢えないという考え方がある。その一方で、七夕の雨は彦星が逢いに行ったからという解釈があるのが面白い。その夜だけは、雨夜の禁忌を冒してでも逢いに行くことが許されていたとも理解できる。題詠で詠まれていた七夕の恋はやがて個人に引き付けて詠まれるようになる。
〈天の川去年の渡りで移ろへば川瀬を踏むに夜ぞ更けにける(『万葉集』巻十 作者未詳)〉。去年と舟の渡し場が変わってしまったので、歩いて渡ろうとしたら夜が明けてしまい、逢いに行けなかったという言い訳めいた歌もある。明け方、彦星が帰れないように波が荒くなればいいのにという歌も。七夕が恋人との逢瀬を願う詠み方へと変わっていった。
平安時代になると、七夕は本命の恋人と逢う夜となる。束の間の逢瀬の喜びを詠んだり、一人で過ごす淋しさを詠んだり。現代のクリスマスイブのような感覚である。平安時代の私歌集や日記には、七夕の夜を誰と過ごすか、過ごしたかを巡る熾烈な恋の争いが記されている。上流階級の姫君はひたすら夫を待つ。夫もまた、後ろ盾となる正妻に真っ先に逢いにゆく。中流階級となると男も女も複数の恋人がいるため、事前に逢う約束を取り交わす。断り文句もまた、舟が混み合っているとか涙で川が増水しているとか、七夕らしい言葉を連ねる。本命に断られると二番目、三番目へと誘いの歌を送る。人気者になると、一晩に複数掛け持ちをする人も。とある色好みの男は、宵の時間に本命宅へ行き、9時ごろに上司に呼び出されたとか言い訳し妾宅へ、12時頃に宿直を抜けて来たのでと言いさらに別宅へ。秋の夜長だからできる技でもあり、女へのまめさは風流人の条件でもあった。女も負けてはおらず、本命に振られたため、二番目の男と宵を過ごし、体調不良を言い訳に帰した後、待機していた若い男を引き入れ、明け方近くに本命が来たことを理由に帰す。本命には「寝ずに待っていて良かった」とか「朝まで一緒に居られる私こそが貴方の本命なのですね」などという。勅撰和歌集には描かれない色好みの歌物語は、どこまでが本当なのかは分からない。現実は、七夕の夜に逢えず嘆く歌が多い。また、万障繰り合わせてやってきた男に、彦星と同じで年に一度しか逢いに来てはくれないと非難する歌もある。男もまた、情が冷めた女でも七夕の夜だけは逢いにゆく。優しさと矜持と情欲が入り混じる夜なのだ。
七夕や若く愚かに嗅ぎあへる
高山れおな
作者は、昭和43年茨城県生まれ。20歳の頃より俳句を作り始め、同人誌「豈」に参加。二十代の締め括りに第一句集『ウルトラ』を出版。〈菊の香や眉間よりビーム出さうなり れおな〉〈墨東に絵の餅を焼く絵の火かな れおな〉は、機知というよりは尖りのある句。〈日の春をさすがいづこも野は厠 れおな〉は、其角の〈日の春をさすがに鶴の歩み哉〉の本歌取り。〈極楽へ葱売りにゆく静かきよ れおな〉は、永田耕衣の〈夢の世に葱を作りて寂しさよ〉への挨拶句。古典の知識を垣間見せつつ独自の表現を生み出している。37歳の時に出版した『荒東雑詩』は、詞書とセットになった詠み方が話題となった。知識がないと理解できない句も多いのだが、分かりやすい句でいうと〈たんぽぽのたんのあたりが麿ですよ れおな〉であろうか。坪内稔典氏の〈たんぽぽのぽぽのあたりが火事ですよ〉を踏まえている。さらには、〈磨、変? れおな〉なんていう句も。
七夕の句は、離れ離れになった男女が年に一度逢える日という知識さえあれば理解できる。真面目に仕事ばかりしていた織姫と牽牛なのだが、恋をしたために仕事がおろそかになった。怒った天帝は、天の川を流し二人を引き離した。この伝承を踏まえ、現代の若き男女が互いの匂いを貪っている場面を描いたのだ。情欲の愚かさを嗅ぎ合うと表現したことで、人ではない獣に成り下がっているかのような行為が浮かぶ。性行為とは、動物的な本能なので〈愚か〉と非難されるのはどうなのかと引っかかりを覚える。そこが作者の狙いではないだろうか。七夕の男女は、年に一度しか逢えなくても一途なのだ。浮気などはしない。動物もまたパートナーを変えない種類が存在する。発情期は年に一度。そして動物には、恋愛感情や性の快楽が無い。七夕は、人以前の恋なのだ。
平安貴族たちが、七夕の夜に過ごす相手を必死に探すのもまた、崇高な恋ではなく、疑似恋愛である。恋を演じることは風流人の条件である。恋をしていること、一緒に過ごす相手がいることは、虚栄でもある。子孫を残すためだけに逢う相手だって存在する。確かに愚かなことである。
現代では、七夕の夜は恋人と一緒に過ごさなくてはならないという風習はない。だけれども、一人で過ごすのは淋しいものだ。茨城県土浦市では8月に七夕祭が開催されていた。盆を控えた夏休みの半ばである。この日、恋人と手を繋いで歩行者天国の街を歩くのが少女の夢であった。商店街の各店舗自慢の吹き流しが湖からの風に煽られ空を彩る。赤や青のかき氷を食べながら短冊に願い事を書く。「ずっと一緒にいられますように」と。
高校二年生の夏だった。昼間のドラマを見ていたら電話が鳴った。「あのさ、演劇部のミエちゃんの同級生で川島っていうんだけど、土浦で遊ばない」という。ミエちゃんは、私の2つ上の先輩で男友達の多い人であった。川島さんは、ひょろりと背の高いルパン三世に似た男性である。「ああ、かっちゃんって呼ばれてた先輩ですよね」「そうそう、そのかっちゃんだよ。土浦まで30分ぐらいで来られるかい?一緒に七夕を見ようよ」。かっちゃんのことは何とも思っていなかったのだが、暇だったので出かけて行った。就職して少し大人っぽくなったかっちゃんは、眩しく見えた。壁に寄り掛かって煙草をふかす姿も格好良い。出店では、羽の付いたイヤリングを買ってくれた。お洒落な喫茶店に入りアイスコーヒーを飲んだ。背伸びをしてシロップもミルクも入れない焦げ茶色の飲み物は、ほろ苦かった。「なぜ誘ってくれたの?」「ミエちゃんに振られちゃったから」「私は補欠だったのね」「じゃあ君は何で来たの?」「暇だったから」「それでいいじゃん。恋人の居ない淋しい者同士、楽しく過ごそうぜ」。その時点では、好きではなかったからだろうか。些細な人間関係の悩みや家族への愚痴などを打ち明け合った。あれ?何だか似た者同士かもと思い、恋に落ちたのは私だけ。かっちゃんは、子供っぽい女の子だなと思っていたらしい。それっきりになるのが嫌で再び逢う約束をした。
二学期が始まった頃に「俺と付き合う気ある?」と聞かれた。「付き合ってくれるの?」と聞き返してしまった。週に一度逢えたのは、最初の数か月だけ。かっちゃんの体調不良や転職によりクリスマスもバレンタインデーも逢えなかった。別れては寄りを戻す期間が続いた。高校三年生の8月、夏期講習の帰りに七夕祭の街を一人で歩いた。もう逢えない予感がして、涙が止まらなくなった。かっちゃんはきっと、私のことなど好きではなかったのだ。恋人がいないのが恥ずかしくて、気のある素振りを見せた私と付き合ってくれただけなのだ。はらはらと風に絡む吹き流しを見ながら決意した。沢山の恋をして、大人の女になろうと。それが、愚かで不毛な恋歴の始まりであった。
彦星のように逢えない人を好きになっては泣いて、少しだけ好きな男と夜を埋め、分かり合えずに苦しむ、そんな愚かな連鎖。天の川を隔てた遠距離恋愛なら逢えない淋しさも我慢できた。逢える距離にいて逢えないことが辛かった。匂いを嗅ぎ合うだけの関係でもいいから逢える日が知りたかった。終わりの見えない孤独の川を縫うように一艘の舟が迷い込んで来たら、それは呼び寄せてしまうだろう。恋人と逢える日として定められた行事の夜に逢いに来ない男など、特別な理由のない限りは、捨ててしまって良いのだ。それでも恋をしている時は、逢えた日のすべてが七夕の夜となる。
(篠崎央子)
【篠崎央子さんの句集『火の貌』はこちら↓】
【執筆者プロフィール】
篠崎央子(しのざき・ひさこ)
1975年茨城県生まれ。2002年「未来図」入会。2005年朝日俳句新人賞奨励賞受賞。2006年未来図新人賞受賞。2007年「未来図」同人。2018年未来図賞受賞。2021年星野立子新人賞受賞。俳人協会会員。『火の貌』(ふらんす堂、2020年)により第44回俳人協会新人賞。「磁石」同人。
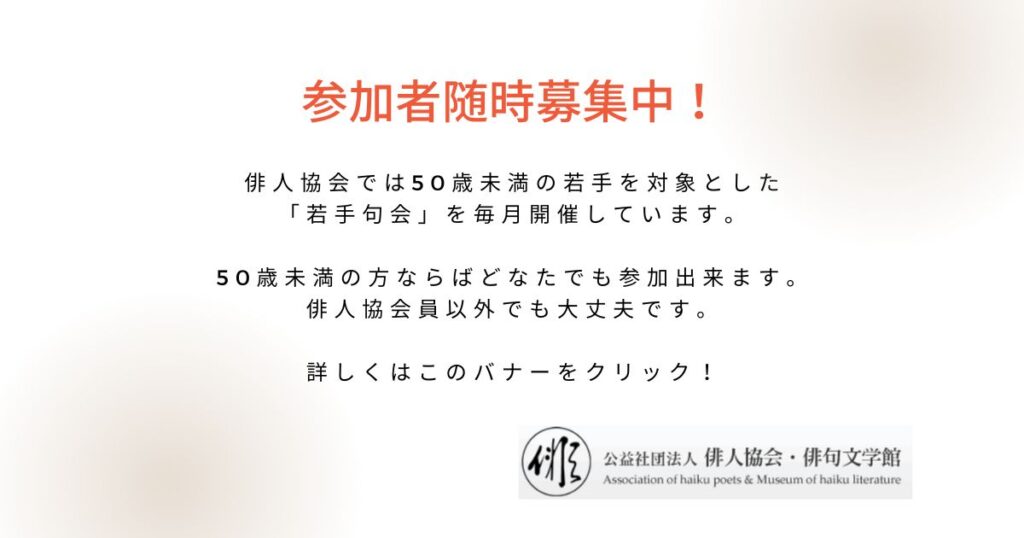
2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓

【篠崎央子のバックナンバー】
>>〔145〕宵山の装ひ解かず抱かれけり 角川春樹
>>〔144〕ぬばたまの夜やひと触れし髪洗ふ 坂本宮尾
>>〔143〕蛍火や飯盛女飯を盛る 山口青邨
>>〔142〕あひふれしさみだれ傘の重かりし 中村汀女
>>〔141〕恋人はめんどうな人さくらんぼ 畑耕一
>>〔140〕花いばら髪ふれあひてめざめあふ 小池文子
>>〔139〕婚約とは二人で虹を見る約束 山口優夢
>>〔138〕妻となる人五月の波に近づきぬ 田島健一
>>〔137〕抱きしめてもらへぬ春の魚では 夏井いつき
>>〔136〕啜り泣く浅蜊のために灯を消せよ 磯貝碧蹄館
>>〔135〕海市あり別れて匂ふ男あり 秦夕美
>>〔134〕エリックのばかばかばかと桜降る 太田うさぎ
>>〔133〕卒業す片恋少女鮮烈に 加藤楸邨
>>〔132〕誰をおもひかくもやさしき雛の眉 加藤三七子
>>〔131〕海苔あぶる手もとも袖も美しき 瀧井孝作
>>〔130〕鳥の恋いま白髪となる途中 鳥居真里子
>>〔129〕魚は氷に上るや恋の扉開く 青柳飛
>>〔128〕寒いねと彼は煙草に火を点ける 正木ゆう子
>>〔127〕純愛や十字十字の冬木立 対馬康子
>>〔126〕冬河原のつぴきならぬ恋ならめ 行方克巳
>>〔125〕忽然と昭和をはりぬ夕霧忌 森竹須美子
>>〔124〕恋にしてわざと敗けたるかるた哉 羅蘇山人
>>〔123〕クリスマス「君と結婚していたら」 堀井春一郎
>>〔122〕毛糸玉秘密を芯に巻かれけり 小澤克己
>>〔121〕恋の刻急げ アリスの兎もぐもぐもぐ 中村憲子
>>〔120〕デモすすむ恋人たちは落葉に佇ち 宮坂静生
>>〔119〕美しき時雨の虹に人を待つ 森田愛子
>>〔118〕弟へ恋と湯婆ゆづります 攝津幸彦
>>〔117〕にんじんサラダわたし奥様ぢやないぞ 小川楓子
>>〔116〕山椒の実噛み愛憎の身の細り 清水径子
>>〔115〕恋ふたつ レモンはうまく切れません 松本恭子
>>〔114〕あきざくら咽喉に穴あく情死かな 宇多喜代子
>>〔113〕赤い月にんげんしろき足そらす 富澤赤黄男
>>〔112〕泥棒の恋や月より吊る洋燈 大屋達治
>>〔111〕耳飾るをとこのしなや西鶴忌 山上樹実雄
>>〔110〕昼の虫手紙はみんな恋に似て 細川加賀
>>〔109〕朝貌や惚れた女も二三日 夏目漱石
>>〔108〕秋茄子の漬け色不倫めけるかな 岸田稚魚
>>〔107〕中年や遠くみのれる夜の桃 西東三鬼
>>〔106〕太る妻よ派手な夏着は捨てちまへ ねじめ正也
>>〔105〕冷房とまる高階純愛の男女残し 金子兜太
>>〔104〕白衣とて胸に少しの香水を 坊城中子
>>〔103〕きつかけはハンカチ借りしだけのこと 須佐薫子
>>〔102〕わが恋人涼しチョークの粉がこぼれ 友岡子郷
>>〔101〕姦通よ夏木のそよぐ夕まぐれ 宇多喜代子
>>〔100〕水喧嘩恋のもつれも加はりて 相島虚吼
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】

