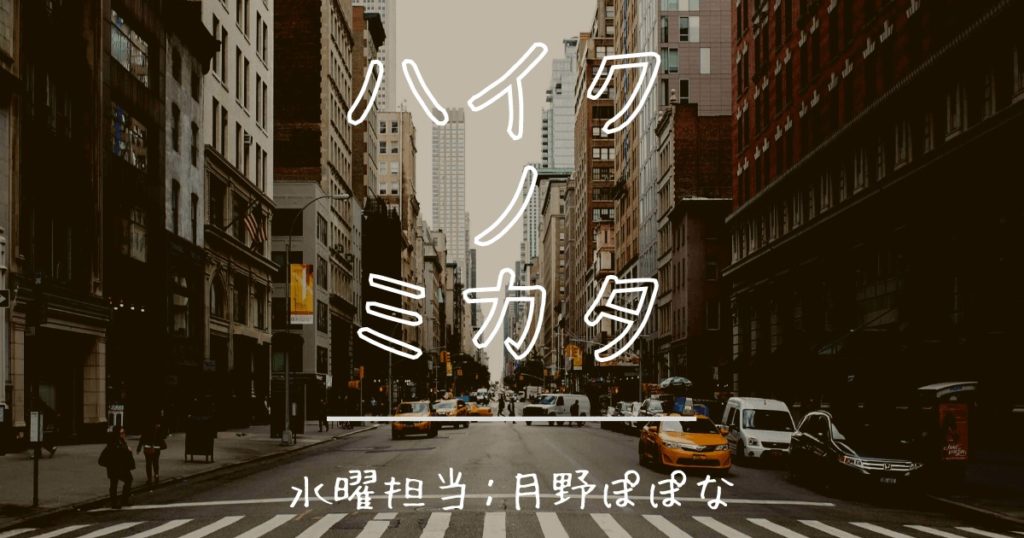
武具飾る海をへだてて離れ住み
加藤耕子
本日5月5日は「端午の節句」。日本において男児の健やかな成長を願う日であり、男児をもつ家族にとってはとても重要であり、男児にとっては楽しい節句。ちょうど女児にとっての3月3日の雛祭のようである。
それとともに5月5日は、日本における国民の祝日「こどもの日」でもある。国の祝日法によると「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日だという。
1948年に「こどもの日」を制定する際、古代中国から伝来し、かつて江戸時代から明治時代の初期まで祝日であった五節句、つまり人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)のうちの「端午の節句」、5月5日が選ばれたという。
「端午の節句」の「端午」とは、中国の古い暦の「牛」の月である5月の、「端」つまり最初の午の日という意味。
さて、その「端午の節句」はなぜ男児の祭となったのだろう。
古代中国では、季節の変わり目である節句に、病気や邪気から身を守るための行事がおこなわれていたが、特に、病気が流行りやすく死者も多いため「忌み月」と呼ばれたていた旧歴の5月の「端午の節句」には、邪気をはらうために菖蒲を飾ったり、菖蒲酒を飲んだりしていた。この風習が奈良・平安時代に日本に伝わり、健康と厄除け祈願として貴族たちの間に広まったという。
そのため、この節句は「菖蒲の節句」とも呼ばれる。江戸時代には語呂合わせで「尚武の節句」とも呼ばれ、武士の間で盛んに祝われるようになり、自然に「男児の祭」と意識されるようになったという。
これは、ちょうど、中国において上巳の(3月3日)に行われていた不浄を払う習わしに由来する、平安時代の「流し雛」が、江戸時代に「人形遊び」と結びつき、「雛祭」という「女児の祭」になった経緯と似ていて興味深い。
男児を持つ家庭では、屋外には鯉のぼりを、屋内には武者人形を飾り、柏餅やちまきを食べ、菖蒲湯に入り、男児の出世と健康を祈る。
武具飾る海をへだてて離れ住み
〈武具飾る〉は、季語「武者人形」の傍題。句中の動作の主は、兜や鎧を、男児のために飾っている。日本は島国であり、周りを海に囲まれているため、〈海をへだてて離れ住み〉からは、句中の動作の主とその家族が、外国に暮らしていることがわかる。世界中どこに住んでいても変わらない、子供の健康を願う親の気持ちが伝わってくる。
「端午の節句」と「こどもの日」である今日、すべての子どもたち、そしてそのご家族のご健康とご多幸をお祈りして、良い1日を!
(月野ぽぽな)
【執筆者プロフィール】
月野ぽぽな(つきの・ぽぽな)
1965年長野県生まれ。1992年より米国ニューヨーク市在住。2004年金子兜太主宰「海程」入会、2008年から終刊まで同人。2018年「海原」創刊同人。「豆の木」「青い地球」「ふらっと」同人。星の島句会代表。現代俳句協会会員。2010年第28回現代俳句新人賞、2017年第63回角川俳句賞受賞。
月野ぽぽなフェイスブック:http://www.facebook.com/PoponaTsukino
【月野ぽぽなのバックナンバー】
>>〔30〕追ふ蝶と追はれる蝶と入れ替はる 岡田由季
>>〔29〕水の地球すこしはなれて春の月 正木ゆう子
>>〔28〕さまざまの事おもひ出す桜かな 松尾芭蕉
>>〔27〕春泥を帰りて猫の深眠り 藤嶋務
>>〔26〕にはとりのかたちに春の日のひかり 西原天気
>>〔25〕卒業の歌コピー機を掠めたる 宮本佳世乃
>>〔24〕クローバーや後髪割る風となり 不破博
>>〔23〕すうっと蝶ふうっと吐いて解く黙禱 中村晋
>>〔22〕雛飾りつゝふと命惜しきかな 星野立子
>>〔21〕冴えかへるもののひとつに夜の鼻 加藤楸邨
>>〔20〕梅咲いて庭中に青鮫が来ている 金子兜太
>>〔19〕人垣に春節の龍起ち上がる 小路紫峡
>>〔18〕胴ぶるひして立春の犬となる 鈴木石夫
>>〔17〕底冷えを閉じ込めてある飴細工 仲田陽子
>>〔16〕天狼やアインシュタインの世紀果つ 有馬朗人
>>〔15〕マフラーの長きが散らす宇宙塵 佐怒賀正美
>>〔14〕米国のへそのあたりの去年今年 内村恭子
>>〔13〕極月の空青々と追ふものなし 金田咲子
>>〔12〕手袋を出て母の手となりにけり 仲寒蟬
>>〔11〕南天のはやくもつけし実のあまた 中川宋淵
>>〔10〕雪掻きをしつつハヌカを寿ぎぬ 朗善千津
>>〔9〕冬銀河旅鞄より流れ出す 坂本宮尾
>>〔8〕火種棒まつ赤に焼けて感謝祭 陽美保子
>>〔7〕鴨翔つてみづの輪ふたつ交はりぬ 三島ゆかり
>>〔6〕とび・からす息合わせ鳴く小六月 城取信平
>>〔5〕木の中に入れば木の陰秋惜しむ 大西朋
>>〔4〕真っ白な番つがいの蝶よ秋草に 木村丹乙
>>〔3〕おなじ長さの過去と未来よ星月夜 中村加津彦
>>〔2〕一番に押す停車釦天の川 こしのゆみこ
>>〔1〕つゆくさをちりばめここにねむりなさい 冬野虹