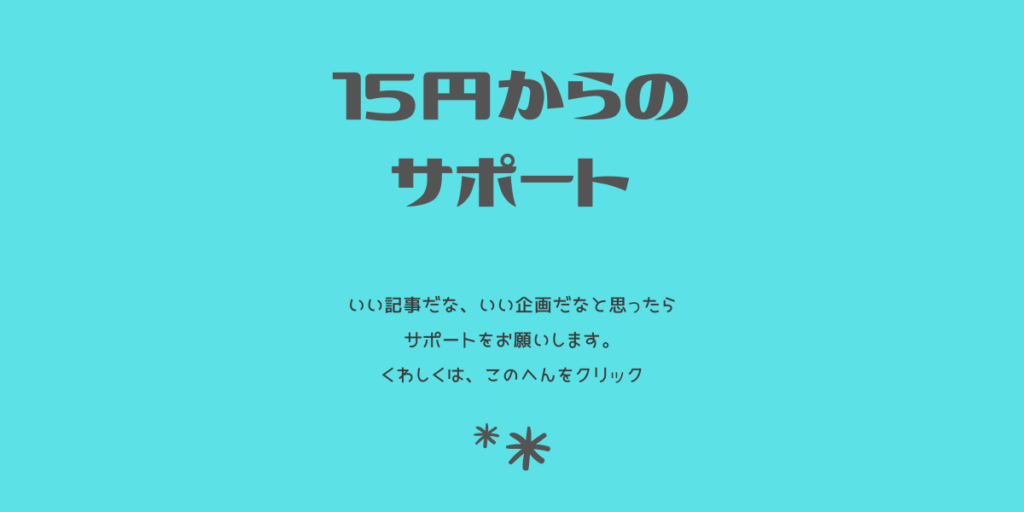夫いつか踊子草に跪く
都築まとむ
我が家の農場内でもあちこちに踊子草の花が見られる季節になった。群落を形成するというほどではないが、こちらに数株、あちらにも、という感じで、目立たない花をひっそりと咲かせている。
踊子草という名前は、花のかたちが笠を被って踊るように見えるからだという。言われてみれば確かにそんな風にも見えて、粋な名前をつけたものだと思う。
夫いつか踊子草に跪く
「いつか」は過去、未来のどちらにも使われるが、ここでは未来と取るのが自然だろう。すなわち、掲句は夫に対する予言だ。だが句からうかがえるのは、夫が踊子草に跪くであろうということだけで、その背後にある感情については読者の想像に任されている。
この「夫」の人物像であるが、私は妻に対して少し威張っているような男性を想像した。踊子草は葉の付け根に花をつけるのだが、その控えめな花を高みから見下ろすような、そんな男だ。もしかしたら、踊子草などという地味な花には目もくれないかもしれない。
そんな男がいつか踊子草に跪くようになる。それは老いのせいかもしれないし、他の原因からかもしれない。いくら跪いても、踊子草より低くはなれないのだが、精一杯身を縮めている図を想像すると、哀れみともおかしみともつかぬ思いが湧き上がってくる。
この句は他の植物、たとえば日日草や弟切草などに置き換えると、まったく違った雰囲気になる。それは、踊子草の「踊子」のイメージ、季語の踊子ではなく、男性の享楽のために消費されざるを得なかった踊子、そんなイメージが句の背景に色濃く感じられ、そこから掲句全体が呪いの言葉のような響きを持ち始めるのである。
「塩辛色」(2014年)所収。
(鈴木牛後)
【執筆者プロフィール】
鈴木牛後(すずき・ぎゅうご)
1961年北海道生まれ、北海道在住。「俳句集団【itak】」幹事。「藍生」「雪華」所属。第64回角川俳句賞受賞。句集『根雪と記す』(マルコボ.コム、2012年)、『暖色』(マルコボ.コム、2014年)、『にれかめる』(角川書店、2019年)。
【鈴木牛後のバックナンバー】
>>〔36〕でで虫の繰り出す肉に遅れをとる 飯島晴子
>>〔35〕干されたるシーツ帆となる五月晴 金子敦
>>〔34〕郭公や何処までゆかば人に逢はむ 臼田亜浪
>>〔33〕日が照つて厩出し前の草のいろ 鷲谷七菜子
>>〔32〕空のいろ水のいろ蝦夷延胡索 斎藤信義
>>〔31〕一臓器とも耕人の皺の首 谷口智行
>>〔30〕帰農記にうかと木の芽の黄を忘ず 細谷源二
>>〔29〕他人とは自分のひとり残る雪 杉浦圭祐
>>〔28〕木の根明く仔牛らに灯のひとつづつ 陽美保子
>>〔27〕彫り了へし墓抱き起す猫柳 久保田哲子
>>〔26〕雪解川暮らしの裏を流れけり 太田土男
>>〔25〕鉄橋を決意としたる雪解川 松山足羽
>>〔24〕つちふるや自動音声あかるくて 神楽坂リンダ
>>〔23〕取り除く土の山なす朧かな 駒木根淳子
>>〔22〕引越の最後に子猫仕舞ひけり 未来羽
>>〔21〕昼酒に喉焼く天皇誕生日 石川桂郎
>>〔20〕昨日より今日明るしと雪を掻く 木村敏男
>>〔19〕流氷は嘶きをもて迎ふべし 青山茂根
>>〔18〕節分の鬼に金棒てふ菓子も 後藤比奈夫
>>〔17〕ピザーラの届かぬ地域だけ吹雪く かくた
>>〔16〕しばれるとぼつそりニッカウィスキー 依田明倫
>>〔15〕極寒の寝るほかなくて寝鎮まる 西東三鬼
>>〔14〕牛日や駅弁を買いディスク買い 木村美智子
>>〔13〕牛乳の膜すくふ節季の金返らず 小野田兼子
>>〔12〕懐手蹼ありといつてみよ 石原吉郎
>>〔11〕白息の駿馬かくれもなき曠野 飯田龍太
>>〔10〕ストーブに貌が崩れていくやうな 岩淵喜代子
>>〔9〕印刷工枯野に風を増刷す 能城檀
>>〔8〕馬孕む冬からまつの息赤く 粥川青猿
>>〔7〕馬小屋に馬の表札神無月 宮本郁江
>>〔6〕人の世に雪降る音の加はりし 伊藤玉枝
>>〔5〕真っ黒な鳥が物言う文化の日 出口善子
>>〔4〕啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々 水原秋桜子
>>〔3〕胸元に来し雪虫に胸与ふ 坂本タカ女
>>〔2〕糸電話古人の秋につながりぬ 攝津幸彦
>>〔1〕立ち枯れてあれはひまはりの魂魄 照屋眞理子
【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】